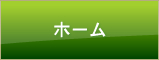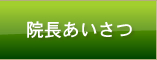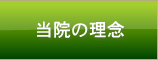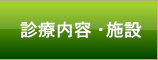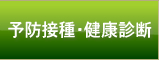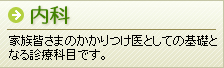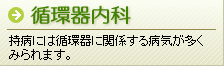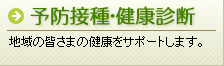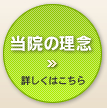広島市南区にある「なかた内科循環器クリニック」は、内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・健康診断や各種予防接種を行っております。

![]()
広島市南区旭一丁目5-31 TEL:082-298-7799
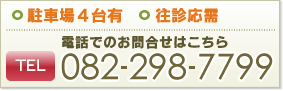
当院は、気軽に病気や健康の相談ができ、家族皆さまが利用できるクリニックを目指しております。
「迷ったときのかかりつけ医③ 内科編」(南々社) に掲載されました。(P188~195)
◆感染対策にご協力ください。
院内でのマスク着用に、ご理解とご協力をお願いいたします。
発熱や風邪症状などがみられる方は、直接来院ぜず、まずはお電話でのご相談をお願いします。
◆令和6年度インフルエンザ予防接種のお知らせ
令和6年10月15日(火)から、インフルエンザ予防接種を開始します。
予約は実施しておりません。診療時間内に来院して下さい。
もしも当日分のワクチンが無くなった場合、その日は終了となりますので、早めの来院をお願いします。
予防接種は、ワクチンが無くなり次第、予告なく終了となりますので、ご了承下さい。
◆令和6年度新型コロナ予防接種のお知らせ
令和6年10月15日(火)から、新型コロナ予防接種を開始します。
予約制で行いますので、詳しくは当院にお問い合わせください。
◆ 高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種化のお知らせ
平成26年10月15日から、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種が予防接種法に基づく定期予防接種になります。
しばらくは経過措置が設けられ、年齢に応じて順次接種対象者となります。
自己負担金4,600円が必要です。(生活保護世帯に属する人、市民税所得割非課税世帯に属する人は、無料。)
「臨時休診のお知らせ」
2025年4月7日(月)
院長不在のため、休診となります。
2024. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月28日(土)までの診療となります。
年始は、1月6日(土)から診療致します。
2024. 08. 09 「お盆の日程のお知らせ」
8月11日(日)から16日(金)まで休診します。 17日(土)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2023. 12. 20 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月28日(木)午前までの診療となります。
年始は、1月4日(木)から診療致します。
2023. 08. 12 「お盆の日程のお知らせ」
8月13日(日)から16日(水)まで休診します。 17日(木)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2023. 05. 01 「ゴールデンウイークの日程のお知らせ」
5月3日(水)から5月7日(日)まで休診します。宜しくお願いします。
2022. 12. 26 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月28日(水)までの診療となります。
年始は、1月4日(水)から診療致します。
2022. 08. 06 「お盆の日程のお知らせ」
8月13日(土)から16日(火)まで休診します。 17日(水)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2021. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月28日(火)までの診療となります。
年始は、1月4日(火)から診療致します。
2021. 08. 12 「お盆の日程のお知らせ」
8月13日(金)から16日(月)まで休診します。 17日(火)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2020. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月29日(火)午前までの診療となります。
年始は、1月4日(月)から診療致します。
2020. 08. 11 「お盆の日程のお知らせ」
8月13日(木)から16日(日)まで休診します。 17日(月)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2019. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月28日(土)まで診療、12月29日(日)から1月3日(金)まで休診します。 1月4日(土)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2019. 08. 10 「お盆の日程のお知らせ」
8月11日(日)から16日(金)まで休診します。 17日(土)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2019. 03. 22 「ゴールデンウイークの日程のお知らせ」
ゴールデンウイークは、暦通り、4月28日(日)から5月6日(月)まで休診となります。宜しくお願いします。
2018. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月29日(土)まで診療、12月30日(日)から1月3日(木)まで休診します。 1月4日(金)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2018. 11. 26 「休診のお知らせ」
12月15日(土)は、院長不在のため休診します。
2018. 08. 09 「お盆の日程のお知らせ」
8月11日(土)から15日(水)まで休診します。 16日(木)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2017. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月29日(金)まで診療、12月30日(土)から1月3日(水)まで休診します。 1月4日(木)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2017. 08. 08 「お盆の日程のお知らせ」
8月13日(日)から16日(水)まで休診します。 17日(木)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2016. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月29日(木)まで診療、12月30日(金)から1月3日(火)まで休診します。 1月4日(水)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2016. 08. 09 「お盆の日程のお知らせ」
8月13日(土)から16日(火)まで休診します。 17日(水)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2015. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月29日(火)まで診療、12月30日(水)から1月3日(日)まで休診します。 1月4日(月)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2015. 08. 12 「お盆の日程のお知らせ」
8月13日(木)から16日(日)まで休診します。 17日(月)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2014. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月29日(月)まで診療、12月30日(火)から1月4日(日)まで休診します。 1月5日(月)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2014. 08. 12 「お盆の日程のお知らせ」
8月14日(木)から17日(日)まで休診します。 18日(月)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2013. 12. 28 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月28日(土)まで診療、12月29日(日)から1月3日(金)まで休診します。 1月4日(土)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2013. 08. 12 「お盆の日程のお知らせ」
8月13日(火)から15日(木)まで休診します。 16日(金)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2013. 01. 15
院内広報誌「じゅんくり」第32号(1月号)を発行しました。
特集:「ノロウイルスへの対策」(感染性胃腸炎)について
料理レシピ:
「豚肉とカブの中華風巻き」
「じゅんくり」は、院内待合にて配布しております。
2012. 12. 29 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月29日(土)まで診療、12月30日(日)から1月3日(木)まで休診します。 1月4日(金)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2012. 10. 03
院内広報誌「じゅんくり」第31号(10月号)を発行しました。
特集:「インフルエンザ予防接種について」~2012年度
料理レシピ: 「チキンのたっぷりきのこクリームソース」
「じゅんくり」は、院内待合にて配布しております。
2012. 08. 12 「お盆の日程のお知らせ」
8月14日(火)から16日(木)まで休診します。 17日(金)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2012. 07. 25
院内広報誌「じゅんくり」第30号(7月号)を発行しました。
特集:
「熱中症」について~湿度や風通しにもご注意を~
料理レシピ: 「茄子とズッキーニの和風炒め」
2012. 05. 07
院内広報誌「じゅんくり」第29号(5月号)を発行しました。
特集:「高脂血症 その②~検査値の見方・目標値~」
料理レシピ:「クレソンのお浸し風」
2012. 01. 09
院内広報誌「じゅんくり」第28号(1月号)を発行しました。
特集:「高脂血症について~その①:脂質の正体~」
料理レシピ:「豆乳シチューカレー風味」
2011. 10. 10
院内広報誌「じゅんくり」第27号(10月号)を発行しました。
特集:「インフルエンザ予防接種について」~2011年度
料理レシピ:「里芋とクルミの味噌和え」
2011. 09. 01
院内広報誌「じゅんくり」第26号(9月号)を発行しました。
特集:「胃炎と食事について」~胃にやさしい食事
料理レシピ:「スズキの味噌幽庵焼き」
2011. 07. 01
院内広報誌「じゅんくり」第25号(7・8月号)を発行しました。
特集:「熱中症とその対策」~湿度にもご注意を
料理レシピ:「オクラのかきあげ」
2011. 06. 01
院内広報誌「じゅんくり」第24号(6月号)を発行しました。
特集:「ピロリ菌除菌療法」のご案内
料理レシピ:「抹茶ミルク寒天」
2011. 05. 01
院内広報誌「じゅんくり」第23号(5月号)を発行しました。
特集:「骨密度検査」のご案内
料理レシピ:「アジバーグ」
2011. 04. 01
院内広報誌「じゅんくり」第22号(4月号)を発行しました。
特集:「高尿酸血症」について
料理レシピ:「菜の花とイカのごま酢味噌和え」
2011. 03. 01
院内広報誌「じゅんくり」第21号(3月号)を発行しました。
特集:「花粉症」について
料理レシピ:「しそと緑茶入りチキンロール」
2011. 02. 01
院内広報誌「じゅんくり」第20号(2月号)を発行しました。
特集:「子宮頸がん予防ワクチン」について
料理レシピ:「ほうれん草のサラダ風おひたし」
2011. 01. 04
院内広報誌「じゅんくり」第19号(1月号)を発行しました。
特集:「慢性頭痛」について
料理レシピ:「春菊とツナの炊き込み」
2010. 12. 06
院内広報誌「じゅんくり」第18号(12月号)を発行しました。
特集:「嘔吐下痢症」について
料理レシピ:「さわらの香り焼き」
2010. 11. 04
院内広報誌「じゅんくり」第17号(11月号)を発行しました。
特集:「ビタミン」について
料理レシピ:「ごま豆腐」
2010. 10. 04
院内広報誌「じゅんくり」第16号(10月号)を発行しました。
特集:①「インフルエンザ予防接種について(2010年度)」
特集:②「日本脳炎予防接種について」
料理レシピ:「秋の味覚・きのこご飯
」
2010. 9. 01
院内広報誌「じゅんくり」第15号(9月号)を発行しました。
特集:「栄養指導」始めました
料理レシピ:「
本格!!野菜スープ
」
2010. 8. 01
院内広報誌「じゅんくり」第14号(8月号)を発行しました。
特集:「熱中症」について
料理レシピ:「夏野菜の炒り鶏風」
2010. 8. 01 「お盆の日程のお知らせ」
8月14日(土)から16日(月)まで休診します。 17日(火)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2009. 12. 19 「年末年始の日程のお知らせ」
年内は、12月29日(火)まで診療、12月30日(水)から1月3日(日)まで休診します。 1月4日(月)からは通常通りです。宜しくご了承願います。
2009. 4. 15
開院しました。
・内科 ・循環器内科 ・消化器内科 ・呼吸器内科

![]()
循環器について: 循環器に関係する疾患は、高血圧、高脂血症、糖尿病、狭心症、心筋梗塞、心不全、動悸、不整脈、弁膜症など様々ですが、合併症の有無も含めて適切な検査を行い、病状を把握することが必要です。 当院では、一般的な検査に加え、心エコー、頸動脈エコー、下肢動静脈エコー、安静時心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図、血圧脈波検査(血管年齢検査)などの循環器系の詳しい検査が可能であり、心臓の状態、動脈硬化の有無、不整脈の程度、合併症の有無などを判断し、適切な治療を行います。 また、心臓や動脈硬化に関する健康診断も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
じゅんくり・いんたーねっと
2013. 01.15
広報誌の特集は「ノロウイルスへの対策(感染性胃腸炎)について」です。
院内広報誌「じゅんくり」1月号を発行しました。特集は「ノロウイルスへの対策(感染性胃腸炎)について」です。 昨年末より、ノロウイルスによる嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)の流行が全国的にみられ、広島県でも過去10年で最も広がった2006年に迫る勢いで患者数が増えています。そこで今回は、ノロウイルスへの対策について特集しました。
また、料理レシピは、「豚肉とカブの中華風巻き」です。今回は「カブ」を使ったレシピの紹介です。カブは、根と葉の栄養成分が違う食品です。根は淡色野菜でビタミンCを多く含み、でんぷん消化酵素のアミラーゼを含んでいます。葉は緑黄色野菜で、カロテン、ビタミンC、鉄、カルシウム、カリウム、食物繊維などを含んでおり、抗発がん作用、風邪の予防や疲労の回復、肌荒れなどに効果があります。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2012. 05.07
広報誌の特集は「高脂血症 その②~検査値の見方・目標値~」です。
「高脂血症」は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が必要以上に多い状態で、放っておくと血管の壁にコレステロールがたまり、動脈硬化を進行させ、脳梗塞や心筋梗塞などの怖い疾患につながります。前回は、「コレステロール・中性脂肪の役割」を説明しました。今回は、「検査値の見方・目標値」を解説します。
また、料理レシピは、「クレソンのお浸し風」です。今回はクレソンを使ったレシピの紹介です。クレソンはカルシウム・カリウム・βカロテン・ミネラル等の栄養豊富な野菜で、癌や動脈硬化や貧血の予防、美肌にも効果があります。クレソンを選ぶ時のポイントとしては、茎が太くて、節の間隔が狭く、葉は光沢があり、濃い緑色のものを選ぶと良いとされています。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2012. 01.09
広報誌の特集は「高脂血症について~その①:脂質の正体~」です。
院内広報誌「じゅんくり」1月号を発行しました。特集は「高脂血症について~その①:脂質の正体~」です。「高脂血症」は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が必要以上に多い状態で、放っておくと血管の壁にコレステロールがたまり、動脈硬化を進行させ、脳梗塞や心筋梗塞などの怖い疾患につながります。しかし、高脂血症といわれても、そもそもコレステロールや中性脂肪がどのようなものかについても良くわからないという人が多く、コレステロールが高いからといって特別な自覚症状もないため、治療の必要性を感じない方もみられます。そこで、高脂血症について、基本的な情報を数回に分けて特集します。
料理レシピは、「豆乳シチューカレー風味」です。今回は豆乳を使ったレシピの紹介です。豆乳は消化吸収がよく、良質なたんぱく質と脂質を含みます。豆乳独特の匂い消しにカレー粉を使用し、ほうれん草ロールを加えヘルシーに仕上げました。寒いこの時期に是非お試しください。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 10.10
「インフルエンザ予防接種」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」10月号を発行しました。特集は「インフルエンザ予防接種について」です。10月に入り、インフルエンザの予防接種がスタートしました。予防接種によりインフルエンザを完全に防げるわけではありませんが、発病リスクを減らし、合併症の発生する頻度が低くなるといった効果が報告されており、予防接種は有効な手段と考えております。そこで、「インフルエンザ予防接種」の情報をまとめました。
また、料理レシピは、「里芋とクルミの味噌和え」です。今月は秋から初冬が旬の里芋を使ったレシピです。
里芋はでんぷん質ですが水分が多く低カロリーで、食物繊維が豊富なのが特徴です。イモ類の中ではカリウムが比較的多く、余分な塩分を体外に排出し、むくみや高血圧の改善に効果があります。里芋独特のぬめりは水溶性食物繊維のガラクタンとムチンという成分で、ガラクタンは、脳細胞を活性化させる効果があり、免疫性も高め、がんの発生・進行を防ぎ、コレステロールの低下、風邪の予防にも役立ちます。さらに消化を促進する作用もあり、整腸と便秘の解消に大変効果的です。ムチンには肝臓を丈夫にしたり、胃腸の表面を保護し、胃潰瘍や腸炎を予防する効果があります。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 09.01
「胃炎と食事 について」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」9月号を発行しました。特集は「胃炎と食事について」です。食欲の秋となりましたが、まだまだ暑い日が続き、当院にも胃にトラブルを抱えた方が多くいらっしゃいます。薬による治療は勿論ですが、普段の食生活においても注意すべきことがあります。そこで今回は、「胃炎と食事 について」について取り上げました。
また、料理レシピは、「スズキの味噌幽庵焼き」です。今月は今が旬のスズキのレシピです。
スズキは生育年齢で呼び名が変わる出世魚(セイゴ→フッコ→スズキ)で、成長するごとに脂がのり、おいしくなる魚です。栄養的には、ビタミンA・B群、鉄が比較的多いこと。また、皮にはビタミンDが豊富です。貧血を予防する鉄も含みます。ビタミンAは、粘膜の生成や機能を助け、病気への抵抗力をつけるビタミンで、目の乾燥を防ぐ、風邪などを予防、ガン予防などに有効です。B群は体と心に活力をつけます。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 07.01
「熱中症とその対策」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」7月号を発行しました。特集は「熱中症とその対策」についてです。熱中症とは、体温を調整する仕組みがうまく働かなくなるために起こる体の異常のことです。通常、人間は体温が37℃以上になると、自律神経の働きにより、血管を拡張し血行を良くしたり、発汗を促したりして熱を外に逃がし体温を調節します。しかし、過剰に発汗して水分や塩分が失われると、うまく体温を下げることができず、体内に熱がこもってしまい脱水症状や熱けいれんが起こり、熱中症になるのです。今年は、高温多湿の日々が続くため、例年より早く熱中症で病院に運ばれる人が増えています。そこで今回は、「熱中症とその対策」について取り上げました。
また、料理レシピは、「オクラのかきあげ」です。今回は、夏野菜の「オクラ」を取り上げました。オクラの特徴であるネバネバの元は、ペクチン、ムチンですが、「ペクチン」は、血糖値の上昇を抑え、整腸作用があり、糖尿病の予防や便秘の改善に効果があります。「ムチン」は、たんぱく質の吸収を助け、コレステロールの吸収を抑えてくれます。その他にも、カルシウム、鉄、カロテン、ビタミンCを含んでいて、栄養価も高く、夏バテ解消にはもってこいの食品です。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 06.01
「ピロリ菌除菌療法について」特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」6月号を発行しました。特集は「ピロリ菌除菌療法のご案内」です。「ピロリ菌」は、胃の粘膜に生息している細菌で、この菌が潰瘍や胃がんを起しやすい下地をつくることが知られています。また、最近の研究報告では、ピロリ菌を除菌することで胃がんが発症する確率を約1/3程度に減少できることが明らかになっており、ガイドラインでも、すべてのピロリ感染症を除去することを強く奨励しています。そこで、今回は「 ピロリ菌除菌療法 」をご案内します。
また、料理レシピは、「抹茶ミルク寒天」です。今回は、「寒天」を使った料理を紹介します。 寒天に含まれている水溶性食物繊維である「アガロース」「アガロペクチン」は体内の老廃物を排出して腸内環境を整える効果があります。 さらに、コレステロールを低下させる働きもあり、動脈硬化・高血圧・糖尿病の予防など生活習慣病の予防改善にも役立つとされています。 また、寒天の食物繊維は腸の中で膨れ満腹感も得られやすくなる事から肥満解消にも効果的です。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 05.01
「骨密度検査について」特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」5月号を発行しました。特集は「骨密度検査のご案内」です。当院は、4月21日より、以前からご要望の多かった「骨密度検査」が可能となりました。骨粗しょう症の早期発見・予防に骨密度検査を受けませんか?今回は「骨密度検査」をご案内します。
また、料理レシピは、「アジバーグ」です。今が旬の「菜の花」を使った料理を紹介します。「アジ(鯵)」はビタミンB1、B2、カリウム、カルシウムや、タウリン・グリシン・アラニン・グルタミン酸といったうまみ成分、DHA、EPAなどを含む栄養満点の青魚です。タウリンはコレステロール値を下げて、高血圧や動脈硬化の予防に、EPAは血管を広げ血管壁を若々しく保ってくれます。 また、干物にすることで、ビタミンB群、カルシウム、EPAなどがさらに増え、疲労回復等に効果を発揮します。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 04.01
「高尿酸血症」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」4月号を発行しました。特集は「高尿酸血症について」です。高尿酸血症は、生活習慣病のひとつで、患者数は全国で約600万人と推定されており、当院でも多くみられます。痛風や腎臓障害、尿路結石、動脈硬化などの合併症が起こりやすく、生活習慣の改善や適切な治療が大切です。そこで、今回は「高尿酸血症」を取り上げました。
また、料理レシピは、「菜の花とイカのごま酢味噌和え」です。今が旬の「菜の花」を使った料理を紹介します。「菜の花」はアブラナ科のとても栄養価の高い緑黄色野菜です。βカロチンやビタミンB1・B2、ビタミンC、鉄、カルシウム、カリウム、食物繊維などの豊富な栄養素をバランスよく含んでいます。カロテンやビタミンCは免疫力を高め、がん予防やかぜの予防に効果が期待でき、美肌効果もあります。また体内の塩分バランスを保つカリウムも豊富で、高血圧の予防や治療中の方の食事に大変向いてます。鉄分も豊富なので、貧血気味の方には積極的に食べていただきたい食材です。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 03.01
「花粉症」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」3月号を発行しました。特集は「花粉症について」です。花粉症のシーズンがやってきました。今季は、昨年の猛暑の影響などで花粉の飛散量が多いと予測され、症状が軽い人も重症化する恐れがあります。そこで、今回は「花粉症」を取り上げました。
また、料理レシピは、「しそと緑茶入りチキンロール」です。「しそ」は、アレルギー症状を抑える働きのあるαリノレン酸、花粉症の症状を増長する原因物質を抑える作用を持つルテオリン、炎症を和らげる働きのあるロズマリン酸などを含んでおり、花粉症の予防効果が期待できます。また、「緑茶」に含まれるポリフェノールの一種のカテキンやカフェインも、過剰になったヒスタミンを抑えるため、アレルギーや花粉症予防に働きます。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 02.01
「子宮頸がん予防ワクチン」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」2月号を発行しました。特集は「子宮頸がん予防ワクチンについて」です。1月17日から、広島市内に住民票を有する中学1年生~高校1年生相当年齢の女子に対する子宮頸がん予防ワクチン接種の無料化が始まりました。それに伴い、予防接種の問い合わせや質問を多く受けるようになりました。そこで、「子宮頸がん予防ワクチン」についてとりあげました。
また、料理レシピは、「ほうれん草のサラダ風おひたし」です。ほうれん草の代表的栄養素はβカロテンと鉄分です。特にβカロテンはほうれん草100gで一日に必要な分を摂取できるほどの栄養分をもっています。また、ビタミンC、ビタミンEといった抗酸化作用を持つビタミンも豊富で活性酸素を除去しガンなどの病気予防に効果があります。鉄分も豊富なだけでなく鉄分の吸収を促進するビタミンCと造血を助ける葉酸も豊富に含まれているので貧血症の方には適した野菜です。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2011. 01.04
「慢性頭痛」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」1月号を発行しました。特集は「慢性頭痛について」です。日本人の4人に1人は頭痛持ちといわれており、当院にも頭痛を訴える方が多くおられます。頭痛は痛みの起こり方によって3つに分類されます。1つ目は「日常的に起こる頭痛」です。風邪や二日酔い、ストレスなどによるもので、原因が解消されれば自然に治ります。 2つ目は「脳の病気による頭痛」で、くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍などによって起こります。何の前ぶれもなく激しい痛みがあらわれることが多く、生命に危険がおよぶケースもあるので注意が必要です。 3つ目は痛みを繰り返す「慢性頭痛」です。いわゆる「頭痛持ち」の頭痛で、頭痛全体の約80%はこのタイプといわれています。 慢性頭痛には、片頭痛、緊張型頭痛などがあります。今回は、この「慢性頭痛」について紹介します。
また、料理レシピは、「春菊とツナの炊き込み」です。春菊はβ‐カロテン・ビタミンCが豊富に含まれ、肌荒れ、がん予防に効果があります。香りの成分は自律神経に作用し、胃腸の働きを高め、痰切りや咳を鎮める効果も持っています。体の塩分調整に役立つカリウムも非常に豊富に含まれているので、高血圧にも有効です。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 12.06
「嘔吐下痢症」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」12月号を発行しました。特集は「嘔吐下痢症について」です。今年は、嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)の流行が全国的にみられ、広島県内でも、ノロウイルスによる嘔吐下痢症の患者が急増しています。当院でも、11月中旬より、小児から高齢者まであらゆる年齢層で患者が増加しています。そこで今回は、「嘔吐下痢症」についてまとめました。
また、料理レシピは、「さわらの香り焼き」です。さわらは「EPA」や「DHA」というコレステロールを取り除く成分を豊富に含みます。また良質なたんぱく質やビタミンB2・D、ナイアシン、特にカリウムを多く含んでいて、体内の余分なナトリウムの排泄を促し、血圧上昇を抑制する働きがあるため、高血圧に効果があります。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 11 04
「ビタミン」について特集しました。
院内広報誌「じゅんくり」11月号を発行しました。特集は「ビタミンについて」です。ビタミンは五大栄養素の1つで、身体に必要な代謝(化学反応)を助ける役割(例えれば、自動車の潤滑油のような役割)があり、健康を維持する上で大切です。最近、ビタミンについての質問を多く受けることもあり、今回はビタミンについてまとめました。
また、料理レシピは、「ごま豆腐」です。「ごま豆腐」と聞くと、精進料理で手間のかかる料理と思われがちですが、それが家庭料理として簡単に作れるレシピを教えていただきましたのでご紹介します。 牛乳やコーヒー用ミルクが加わることで、とてもコクのある「ごま豆腐」ができあがり、トッピングを変えることで、先付風やデザート風にもなります。是非お試し下さい。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 10 04
「インフルエンザ予防接種・日本脳炎予防接種について」紹介しています。
院内広報誌「じゅんくり」10月号を発行しました。特集①は「インフルエンザ予防接種について」特集②は「日本脳炎予防接種について」です。
10月よりインフルエンザの予防接種が開始されました。また、日本脳炎予防接種では、2期が再開され、1期を受けていない場合の特例措置も始まりました。そこで、これらの予防接種について情報をまとめました。
また、料理レシピは、「秋の味覚・きのこご飯」 をです。
今月は秋の味覚、きのこを使った料理です。きのこは、低力ロリー食品の代表格でヘルシー食材としておなじみですが、食物繊維、ビタミンB類、ビタミンD2、ミネラルなどの栄養素を豊富に含んでいます。
是非お試し下さい。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 9 01
当院の「栄養指導について」紹介しています。
院内広報誌「じゅんくり」9月号を発行しました。特集は「栄養指導について」です。健康づくりの三本柱は、栄養、運動、休養です。中でも毎日の食生活がみなさんの健康に深く関わっています。生活習慣病をはじめとし、更年期障害、心臓病、腎臓病、貧血などの各疾患には、食生活と密接な関係を持つものが多く、医療だけではなく栄養面からの治療も大切であり、食生活の改善が健康づくりにつながります。そこで、8月より管理栄養士による栄養指導を開始しました。そこで、広報誌「じゅんくり」にて、当院での栄養指導にを詳しく紹介しました。
また、料理レシピは、「本格!!野菜スープ」 をです。今月はレシピの投稿がありましたので、紹介させていただきました。コラーゲンたっぷり、野菜たっぷりの本格的なスープで、小さなお子様からお年寄りまで幅広い世代でいただけます。是非お試し下さい。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 8 01
「熱中症」について特集しました
院内広報誌「じゅんくり」8月号を発行しました。特集は「熱中症について」です。今年は例年以上の熱さのため、熱中症で病院に運ばれる人が増えています。8月も前半を中心に全国的に気温が平年より高く、35℃以上の猛暑日となるところが多いと予想されており、熱中症に注意が必要です。そこで今回は、熱中症を取り上げました。
また、料理レシピは、「夏野菜の炒り鶏風」 を紹介しています。今回は、夏野菜の1つであるアスパラガスを使っています。アスパラガスはβカロテン、ビタミンC、E、アスパラギン酸、ルチンなどの栄養が豊富に含まれています。アスパラギン酸は新陳代謝とタンパク質の合成を助けて美肌効果や疲労回復に効果があり、穂先に含まれるルチンという成分は血管を丈夫にし、高血圧や動脈硬化の予防に役立ちます。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 6 30
「こむら返りについて」を特集しました
院内広報誌「じゅんくり」7月号を発行しました。特集は「こむら返りについて」です。睡眠中や運動中など、不意に襲ってくる「こむら返り」の痛さに思わず歯を食いしばった経験は一度や二度ではないと思います。そこで、今回は「こむら返りについて」特集しました。
また、料理レシピは、「ナスのたたき」 を紹介しています。ナスがおいしい季節になりました。ナスの紫色の成分はナスニンとポリフェノールです。ナスニンはコレステロールを下げる効果があり、ポリフェノールには血圧や血糖値を正常化する作用があります。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 5 31
「ハチ刺されについて」を特集しました
院内広報誌「じゅんくり」6月号を発行しました。特集は「ハチ刺されについて」です。毎年、初夏から秋口にかけてハチに刺されてショック症状を起こしたというニュースを耳にしますが、日本では、ハチ刺されによるアナフィラキシーショックによって、年間20~30名の人が亡くなっています。そこで、ハチ刺され事故が増える季節を前に、ハチ刺されについて特集しました。
また、料理レシピは、「レタスのポトフ」 を紹介しています。ポトフはキャベツで作るイメージが強いですが、今回は、これから旬のレタスを使ってみました。レタスは、成分の95%が水分である淡色野菜ですが、ビタミンやミネラルなど、体に必要な栄養素をバランス良く含んでいます。さらに、便通の促進に欠かせない食物繊維、貧血の予防効果がある鉄分、口内炎や肌荒れに効果がある葉緑素などが含まれています。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 5 14
「C-ペプチド検査とは」
血糖値とともにインスリンの分泌能力を検査しておくことは大切です。C-ペプチド検査とは、膵臓のベータ細胞からのインスリンの分泌能力を調べる検査です。C-ペプチドは、インスリンが合成される前段階の物質(プロインスリン)が、分解されるときに発生する副産物で、インスリンと同程度の割合で血液中に分泌され、ほとんどが分解されないまま血液中を循環し、尿とともに排出されます。そのため、血中や尿中のC-ペプチドの値が多いときはインスリンの分泌が多いことを示し、少ないときはインスリンの分泌能力が低下していることがわかります。
2010. 5 09
「糖尿病の種類について」
糖尿病は、大きく分けて次の2つのタイプ(1型、2型)に分けられます。
1型糖尿病は、インスリンを作るすい臓のランゲルハンス島細胞が破壊され、インスリンがほとんど作られなくなるものです。原因ははっきり分かっていませんが、ウイルス感染などをきっかけに起こることもあります。小児期に発病する方が多いという特徴がありますが、中年になってからこのタイプの糖尿病が起こる方もいます。このタイプの糖尿病は日本人の患者さんの5%以下です。
2型糖尿病は、インスリンの分泌量が少なくなったり、インスリンの働きが悪くなったりするもので、遺伝病と生活習慣が深くかかわりあっているタイプです。遺伝的に糖尿病になりやすい体質と、食べ過ぎや運動不足、肥満、喫煙、飲酒、ストレス等の生活習慣などの誘因原因を重ね合わせて持ってしまうことで発症します。中高年に多くみられます。日本人の患者さんの95%は、この2型糖尿病です。
この2つのタイプの糖尿病の他に、他の病気による糖尿病、薬の影響で起こる糖尿病、妊娠をきっかけに起こる糖尿病(妊娠糖尿病)などがあります。
当院では、糖尿病の診断や治療を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 5 06
「長引く咳」について特集しました
院内広報誌「じゅんくり」4月号を発行しました。特集は「長引く咳について」です。咳を伴う疾患は風邪といった軽いものから肺炎や肺がんなどの重い疾患までさまざまですが、多くは2~3週間以内に軽快する、あるいは検査などで原因が特定されます。しかし、長期(3週間以上)にわたり咳がなかなか治らず、レントゲン写真や肺機能検査でも異常を認めない、いわゆる「長引く咳」が少なくありません。そこで、今回は「長引く咳」の代表的な疾患を紹介します。
また、料理レシピは、「ひじきのサラダ」 を紹介しています。ひじきは、カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルや食物繊維を豊富に含んでいます。特にカルシウムは海藻の中では最も多く、骨粗鬆症の予防やイライラ・ストレスの改善にも効果があります。また、低カロリー、低脂肪のため肥満が気になる方にもお勧めです。
院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 4. 30
「ブドウ糖負荷試験とは?」
ブドウ糖負荷試験は、尿に糖が出ている人や、空腹時の血糖値がやや高め(血糖値100mg/dL以上) の人が、糖尿病やその予備軍かどうかの判断を行うための検査です。糖尿病の初期や予備軍の人は、空腹時の血糖値は正常か少し高いのみだが、食後の血糖値が高く、下がりにくいのが特徴で、空腹時の血糖値だけでは見逃されるケースが多くみられます。そこで、一定量(75g)のブドウ糖水溶液を飲んだ時の血糖値やインスリン濃度の推移を観察し、ブドウ糖の処理能力を調べる検査がこのブドウ糖負荷試験です。
ブドウ糖負荷試験の方法ですが、
①12時間以上絶食後(前日の夜9時以降は何も食べずに水分のみとする)、当日の朝、空腹のまま来院し、空腹時血糖とインスリン濃度を測定します。
②ブドウ糖75gを溶かした水を飲みます。(糖負荷)
③ブドウ糖の負荷後、30分、1時間、2時間後に採血し、血糖とインスリン濃度を測定します。
ブドウ糖負荷試験のときに、血糖値とインスリン濃度も測ることによって、インスリン分泌能やインスリン抵抗性を評価します。
ブドウ糖負荷試験による血糖値の評価ですが、「正常」は、空腹時血糖値が110mg/dL未満かつ2時間後血糖値140mg/dL未満です。「糖尿病型」は、空腹時血糖値が126mg/dL以上または2時間後血糖値200mg/dL以上の場合で、それ以外は「境界型」となります。
当院では、糖尿病の診断や治療を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 4. 27
「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)とは?」
糖尿病の診断や治療効果判定の検査に「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」があります。
血管内の余分なブドウ糖は体内の蛋白と結合しますが、このブドウ糖が赤血球の中に含まれる蛋白であるヘモグロビン(血色素)と結合したものが「HbA1c」です。赤血球の寿命はおよそ120日(4ヶ月)で、赤血球はこの間ずっと体内を巡って血管内のブドウ糖と少しずつ結びつくため、HbA1cは過去4ヶ月の血糖値の動きに関係しますが、HbA1cの約50%は過去1ヶ月間に作られ、約25%が過去2ヶ月、残りの25%が過去3~4ヶ月で作られます。つまり近い過去の血糖値ほどHbA1c値に大きく影響するので、HbA1cは過去1~2ヶ月の平均血糖値を反映しています。そして、高血糖状態、すなわち血管内の余分なブドウ糖が多い状態が長期間続くと、ブドウ糖と結びつくヘモグロビンが増えるため、HbA1c値も多くなります。よって、HbA1cの値が高ければ、たとえ受診した日の血糖値が正常でも、過去1~2ヶ月間の血糖コントロールは良くなかったことになります。
HbA1c値は総ヘモグロビン量に対するHbA1cの割合(%)で表され、正常値は4.3~ 5.8%です。また、HbA1cは糖尿病の合併症とも深く関係しており、6.5%以下にコントロールできていると、網膜症・動脈硬化・腎症・末梢神経障害などの合併症の進行をかなり防ぐことができます。
当院では、糖尿病の診断や治療を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 4. 24
「血糖値について」
糖尿病の診断や治療効果判定の基本となる検査に「血糖値」があります。
血糖値とは血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことで、「1dL(1デシリットル=100cc)の血液中に何mgのブドウ糖が含まれているか」という数値で表します。血糖値は食事による影響が大きく、検査のタイミングによって以下の種類があります。
①空腹時血糖値
10時間以上何も食べずに(水分は摂取可)測った血糖値です。方法としては、前日の夜9時以降は何も食べずに水分のみとし、当日の朝に血液をとり血糖値を測定します。正常値は110mg/dL未満で、126mg/dL以上が糖尿病型となります。
②食後2時間血糖値
食事を始めてから2時間後に測った血糖値です。食後の高血糖があるかどうかを簡易的にみるために用いられます。
③随時血糖値
食事の時間と関係なく測定した血糖値です。正常は140mg/dLを超えません。200mg/dL以上の場合が糖尿病型となります。
当院では、糖尿病の診断や治療を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 4. 22
「糖尿病の診断について」
糖尿病は、血液検査(血糖値、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー))や症状から診断されます。
空腹時に測定した血糖値(空腹時血糖値)が126mg/dL以上(正常値は110mg/dL未満)、ブドウ糖75gを飲んで2時間後に測定した血糖値(ブドウ糖負荷試験2時間値)が200mg/dL以上(正常値は140mg/dL未満)、食事の時間に関係なく測定した血糖値(随時血糖値)が200mg/dL以上のいずれかに当てはまる場合、これを「糖尿病型」といいます。
糖尿病と診断されるのは以下の場合です。
①再検査をしても「糖尿病型」にあてはまる場合。
②「糖尿病型」で次のいずれかにあてはまる場合。
・よくみられる糖尿病の症状(口渇、多飲、多尿など)がある。
・HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が6.5%以上ある。
・糖尿病網膜症がある。
空腹時血糖値が正常と糖尿病型との間にある場合(110~125mg/dL)は「境界型」と診断されますが、これは糖尿病になりつつあるか、あるいはもうすでに糖尿病になっている可能性もあります。それを確定するためにはブドウ糖負荷試験などの検査が必要となります。
糖尿病の検査、治療は当院で可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 4. 20
「糖尿病とは?」
糖尿病は、膵臓から分泌される糖質を調節するインスリンというホルモンが不足したり、作用が不十分なために血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が高い状態が続く病気です。自覚症状に乏しく、重篤な合併症を引き起こす特徴があります。糖尿病の患者数は約740万人、糖尿病予備軍(約880万人)と合わせると約1620万となり、増加傾向にあります。
糖尿病は元々尿に糖が出ることから付けられた病名で、尿に糖が出る病気と思われていることがありますが、尿に糖が出ることは血糖値が高いひとつの症状であり、本当に問題なのは血糖値が高いことです。
血糖値が高くても、最初のうちは、ほとんど症状を感じることはありません。しかし、血糖の高い状態が続くと、のどの渇き、疲れやすい、体がだるい、多尿・頻尿、食べてもやせるなどの症状が現れるようになり、次第に全身の血管や神経が傷ついて、全身のさまざまな臓器に影響(合併症)が起こってきます。
糖尿病の検査、治療は当院で可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 4. 17
「トランス脂肪酸」について
食品安全委員会が、心臓病との関連が指摘されているトランス脂肪酸について、健康への影響を評価するための審議を始めたことがニュースになりました。
このトランス脂肪酸ですが、水素添加した植物油を扱う過程で人工的に生成される副産物で、硬化油を使った食品(マーガリン、ショートニングを使った菓子類、業務用揚げ油など)や乳製品・食肉製品などに多く含まれます。トランス脂肪酸は善玉コレステロールを減らし、悪玉コレステロールを増やすため、それ以外の脂肪酸とのバランスを欠いて多く摂取した場合は、心臓疾患などのリスクが高まると言われており、これが「トランス脂肪酸が体に悪い」と言われる理由となっています。欧米諸国では、トランス脂肪酸の食品への表示や含有量の規制が行われているケースもあります。しかし日本では、「日本人一日当たりのトランス脂肪酸摂取量は総エネルギー摂取量の1%未満(総カロリーの0.3~0.6%)と試算しており、摂取量は少ないとされています。しかし、これらの推計は、国民健康・栄養調査の平均値を使用しているため、個人のバラツキを把握することは困難で、脂肪の多い菓子類や食品の食べ過ぎなど、偏った食事をしている場合は平均値を大きく上回る可能性はあることが問題視されていました。そのため、世代、性別ごとの食生活を調べたうえで、トランス脂肪酸の摂取状況を分析し、摂取量による健康への影響を評価します。この評価がまとまるのは来年以降の見込みです。
2010. 4. 14
「動脈硬化」が進行すると?
動脈硬化は、動脈の層が厚くなったり、硬くなったりして弾力性や柔軟性を失なった状態ですが、進行するとどうなるのでしょうか。動脈が硬くなると、その特性であるしなやかさが失われるため血液をうまく送り出せず、心臓に負担をかけてしまい、高血圧、心臓肥大、心不全などの心疾患につながります。また動脈硬化が進行すると、血管の内側がもろくなって、粥腫(じゅくしゅ)というコレステロールや脂肪などの物質が沈着したどろどろの固まり(プラーク)ができます。この粥腫(じゅくしゅ)が大きくなると、血管の中がせまくなったり、詰まったり、粥腫がはがれて血液中をただよい細い血管を詰まらせることとなり、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、下肢閉塞性動脈硬化症などを引き起こします。また、血管がもろくなり破れると、くも膜下出血など脳出血を生じます。これら動脈硬化が原因とされる疾患は近年増加傾向にあります。動脈硬化が大きな原因とされる脳血管疾患、心疾患をあわせると、それだけで日本人の死亡原因の約3割をも占めてしまいます。また、寝たきりの原因を見ると、約4割が脳血管疾患や心臓病など動脈硬化が原因とされるものです。高齢化がすすむ日本において、動脈硬化は大きな問題となっています。
このように、さまざまな症状を引き起こす動脈硬化ですが、いちばん恐ろしいのは「気づきにくい」ことです。手遅れにならないように、ふだんから血管の状態をチェックすることが大切です。当院では、頚動脈エコー検査や血圧脈波検査(血管年齢検査)などの動脈硬化の早期発見や血管のつまり具合を観察する検査が可能です。高血圧・高脂血症・糖尿病など、動脈硬化の原因となる基礎疾患をお持ちの方はもちろんですが、そうでない方も、今後の健康管理のために、これらの検査をおすすめします。
2010. 4. 12
「動脈硬化」とは?
動脈硬化とは、文字どおり「動脈がかたくなる」ことです。動脈は、内膜・内弾性板・中膜・外膜で構成され、心臓が強い力で押し出した血液が流れるので弾力性と柔軟性を持ち合わせていますが、動脈硬化は、この動脈の層が厚くなったり、硬くなったりして弾力性や柔軟性を失なった状態です。動脈が硬くなると、その特性であるしなやかさが失われるため、血液をうまく送り出せず、心臓に負担をかけてしまいます。また、血管の内側がもろくなって、粥腫(じゅくしゅ)というコレステロールや脂肪などの物質が沈着したどろどろの固まり(プラーク)ができ、血管の中がせまくなったり、詰まったり、粥腫がはがれて血液中をただよい細い血管を詰まらせたりし、様々な病気を引き起こします。
当院では、頚動脈エコー検査や血圧脈波検査(血管年齢検査)などの動脈硬化の早期発見や血管のつまり具合を観察する検査が可能です。高血圧・高脂血症・糖尿病など、動脈硬化の原因となる基礎疾患をお持ちの方はもちろんですが、そうでない方も、今後の健康管理のために、これらの検査をおすすめします。
2010. 4. 10
「頚動脈エコー検査」について
動脈硬化を調べるのに簡便で、視覚的に評価できる方法が頚動脈エコーです。頚動脈は、首の部分で大動脈からの血液を脳に流す太い血管で、 自分で触ってドクドクと脈打つのがわかるくらい浅い位置を通っているため、超音波検査(エコー検査)で観察しやすい動脈の一つです。頚動脈は超音波検査で見やすいだけでなく、動脈硬化が起こりやすい場所であり、たとえ自覚症状がなくても、検査にて動脈硬化の早期発見が可能になります。この検査は、仰向けに寝た状態で首の部分にゼリーを塗り、超音波送受信装置(プローブ)をあてて、左右の頚動脈を観察していきます。左右合わせて10分程度で終了する簡単な検査で、痛みもありません。この検査により、動脈硬化の有無、血管のつまり具合の観察、プラークの観察が可能です。
高血圧・高脂血症・糖尿病など、動脈硬化の原因となる基礎疾患をお持ちの方はもちろんですが、そうでない方も、今後の健康管理のために、この頚動脈エコー検査をおすすめします。この検査は、当院でも行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 4. 07
30、40代女性の「喫煙率」が上昇気味です。
健康志向の高まりから禁煙傾向が強まっているにもかかわらず、30~40歳代女性の喫煙率は上昇気味です。国立がんセンターがん対策情報センターの調べによると、2008年の喫煙率は男性36.8%で、1995年以降いずれの年齢階級でも減少傾向にあるのに対し、女性は9.1%で、20歳代では2005年以降減少しているが、1995年以降は30歳代と40歳代では増加しています。
女性の喫煙は妊娠、出産に悪影響を及ぼすだけでなく、お肌にもよくありません。タバコに含まれるニコチンが血管を収縮させるので皮膚の血流が悪くなり、シミやシワ、吹き出物が出やすくなります。当院は4月より「禁煙外来」を開始しました。女性の方もお気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 4. 05
院内広報誌「じゅんくり」4月号を発行しました。
特集は「禁煙外来のご案内」です。タバコには有害物質が多数含まれており、癌や心筋梗塞、脳卒中、肺気腫をはじめとする様々な病気の原因となります。当院は4月より、禁煙治療の施設基準に適合する届出医療機関となり、禁煙治療に健康保険が適用可能となりました。そこで今回は、4月からスタートした「禁煙外来」についてご紹介しました。
また、料理レシピは、「牛肉とブロッコリーの炒め物」を紹介しています。ブロッコリーは、ビタミンやミネラルをバランスよく含んだ栄養豊富な緑黄色野菜です。特にビタミンCは、レモンの約2倍と豊富に含まれています。ビタミンCは、美肌効果や風邪予防に効果がありますが、ストレスや喫煙により大量に失われるので注意が必要です。院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 4. 01
「肺年齢について」
肺年齢とは、1秒間に吐ける息の量(一秒量)から、標準に比べて自分の呼吸機能がどの程度であるかを確認する目安です。一秒量の標準値は、性、年齢、身長によって異なり、20歳前後をピークに加齢とともに低下します。肺年齢は、実際に測定した一秒量が、性、身長が同じ状態の何歳の人に相当するかを示すもので、実年齢よりも多い場合は、肺機能が年齢以上に早く低下していることを示します。肺年齢を知ることで禁煙指導、呼吸器疾患の早期発見・早期治療に活用できます。
肺年齢は、スパイロメトリー検査(肺機能検査)にて評価することができます。当院で検査可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 3. 29
「高HDLコレステロール血症について」
HDLコレステロールは、末梢組織に過剰に蓄積した過剰なコレステロールを取り去り肝臓に運び、処理する働きを持っており、このため善玉コレステロールと呼ばれています。HDLコレステロールの正常値は、40~85mg/dlですが、HDLコレステロールは低すぎる場合、動脈硬化が進行しやすくなるため、一般的には高いほうが良いとされます。しかし、HDLコレステロールが高度の増加(一般的には100mg/dl以上)を示す場合、なんらかの異常が原因となっていることがあります。その原因としては、CETP(コレステロールエステル転送タンパク)欠損症や、肝性リパーゼ(中性脂肪とリン脂質を分解する消化酵素)欠損症、原発性胆汁性肝硬変(この場合、中性脂肪高値や肝機能異常を合併することが多くみられる)や、長期の多量飲酒などがあります。また、原因不明の高HDLコレステロール血症もあり、わが国の人口の1000人中約1人はHDLコレステロールが100mg/dl以上を呈しているともいわれます。CETP欠損症の場合、HDLコレステロールが高いにもかかわらず動脈硬化を伴いやすいという報告がある一方、HDLの合成増加による高HDL-コレステロール血症では動脈硬化の発症が少ないとも見られており、CETP欠損症と動脈硬化の研究は今も行われていますが、はっきりとした結論はみられていません。また、高HDL血症のはっきりとした治療方針(ガイドライン)もありません。高HDLコレステロールでCETP欠損症を疑う場合は、心電図、頸動脈超音波検査、血管脈波検査など、動脈硬化に対する検査を定期的に施行することが望ましいと思われます。また、薬物療法に関して一定の見解はありませんが、動脈硬化を合併する場合には他の危険因子の軽減に努めることが大切です。この病気に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 3. 25
「動脈硬化と中性脂肪の関係は?」
中性脂肪は、コレステロールのように、血管壁に沈着するわけではありません。しかし、血液中の中性脂肪が多いと、「通常のLDLより小さなLDL」(超悪玉)がたくさん出現します。この小さなLDL(超悪玉)は、血管壁に沈着しやすく、動脈硬化を促します。さらに、中性脂肪が多いと、善玉と呼ばれるHDLが減少します。HDLは、血管壁にたまったコレステロールを回収する役目があるため、少なくなるとコレステロールの沈着が加速し、動脈硬化が進みます。中性脂肪が高いと、このような動脈硬化を起こしやすい状態になるのです。動脈硬化になると、血管の柔軟性や弾力性が失われ、血管は破れやすくなり、心筋梗塞や脳卒中などの深刻な病気を引き起こします。
動脈硬化の原因となる高脂血症は早期の診断・治療、合併症の検査が大切です。この病気に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 3. 23
「動脈硬化とコレステロールの関係は?」
動脈硬化に、コレステロールが大きく関係していることは、よく知られています。 コレステロールの中には、「LDL」と「HDL」があります。「LDL」は悪玉とも呼ばれ、血液中にその量が多くなりすぎると、血管壁に入り込んで、酸化され、沈着してきます。すると、白血球の一種である「マクロファージ」という細胞が、酸化したLDLを取り込んで、ドロドロした塊(粥腫(じゅくしゅ))を形成します。このため、血管壁が厚くなり、血管の内腔は狭くなります。これが、動脈硬化です。逆に、「HDL」は善玉とも呼ばれ、血管の壁などに余計に付着しているコレステロールを回収し動脈硬化を予防します。動脈硬化になると、血管の柔軟性や弾力性が失われ、血管は破れやすくなり、心筋梗塞や脳卒中などの深刻な病気を引き起こします。
動脈硬化の原因となる高脂血症は早期の診断・治療、合併症の検査が大切です。この病気に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 3. 19
「コレステロールと中性脂肪の違いは?」
コレステロールと中性脂肪はどちらも脂質の一種ですが、役割が違います。コレステロールは、細胞膜を作ることや筋肉を作るホルモンの原材料となります。 このコレステロールの中にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)という過剰になると血管にたまりやすく動脈硬化の原因となるものと、HDLコレステロール(善玉コレステロール)という全身の余ったコレステロールを抜き取って肝臓まで運んでくれる、動脈硬化を予防するコレステロールがあります。中性脂肪は、体内のエネルギーとして皮下や内臓に貯めていくための脂質です。しかし、それが度を越すと、肥満や脂肪肝になります。中性脂肪は、コレステロール以上に総エネルギーの影響が大きく、食べ過ぎで過剰なエネルギーが体内に入ってきたり、運動不足でエネルギーの消費が少ないと、中性脂肪に変えて体に貯めていきます。
血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪が多くなりすぎている状態、またはHDLコレステロール(善玉コレステロール)が少ない状態を高脂血症(脂質異常症)といいます。高脂血症(脂質異常症)は動脈硬化の原因であり、放置すると、心筋梗塞や脳卒中などの深刻な病気が引き起こされることになります。
高脂血症(脂質異常症)は早期の診断・治療、合併症の検査が大切です。この病気に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 3. 17
「今秋のインフルエンザ予防接種、季節性と新型が1種類にまとめられる見通し」
今年の秋は、インフルエンザ予防接種ワクチンが1種類にまとめられる見通しになりました。厚生労働省は15日、新型と、季節性のA香港型、B型の3タイプのウイルスを対象にすることを決め、三つを組み合わせたワクチンの製造を国内メーカーに依頼する方針を明らかにしました。今季のように季節性と新型の2種類のワクチンを打つ必要がなくなります。
来季のワクチンについては、WHOがAソ連型の代わりに新型を入れることを推奨しており、日本もこれを受け入れた形です。また、新型だけのワクチン接種を希望する人には、今シーズン使われなかったワクチンを備蓄して対応するとのことです。
2010. 3. 15
「低血圧とは?」
「低血圧」とは、血圧が正常範囲を大きく下回った状態と定義されています。血圧が低いことがそのまま病的な状態であるとはかぎらないので、低血圧にはっきりとした基準は存在しませんが、一般的には、最大血圧(収縮期血圧)が100mmHg以下の場合を低血圧としています。通常、最低血圧(拡張期血圧)は考慮にいれません。単に血圧が低いだけで、症状を伴っていない場合は治療の必要はありませんが、血圧の低下により各臓器へ送られる血液量が減少し、種々の自覚症状や臓器の機能障害が生じた場合は問題となります。
低血圧の症状としては、立ちくらみ、めまいが一番多く、朝起き不良、頭痛・頭重、倦怠感・疲労感、肩こり、動悸、胸痛・胸部圧迫感、失神発作、悪心などがあげられます。 このような低血圧症は一般に、男性より女性の方に多くみられます。(ちなみに、立ちくらみやめまいの原因としては、血液内のヘモグロビンの不足によって起きる「貧血」もあり、これは「低血圧」とはまったく別のものです。)
低血圧症の分類ですが、特別な原因疾患を伴わずに血圧が慢性的に低い本能性低血圧症と、原因が明らかな二次性低血圧症(大出血、心臓疾患、ホルモン異常などによって起きる低血圧症)があります。低血圧症の約9割を、本能性低血圧症が占めます。どんな時に起こったかによって起立性低血圧、食後性低血圧、入浴時低血圧、透析低血圧等を分けて考える事があります。
「低血圧」に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 3. 12
「はしかワクチン」13歳と18歳は今月中に接種をお願いします。
13歳(中学1年生に相当:第3期)、18歳(高校3年生に相当:第4期)全員が対象のはしか予防ワクチンの追加接種(第3期・4期)について、未接種者は費用が公費で賄われる3月中に接種を受けるようお願いします。2009年度のワクチン接種率は、昨年末時点で13歳(第3期)が全国平均で65・8%、18歳(第4期)が56・6%といずれも目標の95%に達せず低迷しています。
当院でも接種可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 3. 10
「悪玉/善玉コレステロール(LH比)とは?」
動脈硬化進展の目安になる新しい指標が注目されています。これは、悪玉コレステロール(LDL値)と善玉コレステロール(HDL値)の比率「LH比」と呼ばれるもので、LH比が高い人ほど動脈硬化が進展していると考えられます。
悪玉コレステロールは、これが増えすぎると血管壁に付着して動脈硬化の原因となりますが、善玉コレステロールも、余分なコレステロールを血管から運び出す役割があるため、少なすぎると動脈硬化の原因となります。 このため日本動脈硬化学会は2007年に、「LDL値140mg/dl以上、HDL値40mg/dl未満」を動脈硬化の危険因子の1つとして、高脂血症(脂質異常症)の診断基準値の一部としました。
ところが最近の研究で、LDL値が140未満の人でも急性心筋梗塞を起こすケースが少なくないことが明らかになり、またHDL値が高い人でもまれに動脈硬化疾患を起こすこともわかってきました。そこで、動脈硬化の新たな指標として提唱されているのが「LH比」、すなわち「悪玉コレステロール(LDL値)÷善玉コレステロール(HDL値)」で求めた数値です。 これまでの研究では、LDL値が基準値であっても心筋梗塞を発症したケースの多くは、LH比が1.5を上回っていることが報告されています。またLH比が2.0以上になると血管内のコレステロールの塊が大きくなり、1.5を下回ると小さくなるということもわかってきました。 そこで、一般的には、LH比を2.0以下にすることを目標に、ただし、糖尿病や高血圧など動脈硬化の危険因子がある人は1.5以下を目標にすることが提案されています。
当院では、高脂血症(脂質異常症)の診断・治療のみならず、動脈硬化の検査もおこなっております。ご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 3. 08
「高脂血症(脂質異常症)とはどんな病気?」
血液中にはコレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸といった4種類の脂質と呼ばれる物質が含まれており、細胞膜やホルモンの材料となったり、エネルギーの貯蔵庫になるなど、私たちの体の機能を保つために大切な働きをしています。高脂血症というのは、血液中の脂質が多過ぎる病気のことですが、血液中にある4種類の脂質のうち、多過ぎると問題なのは、コレステロールと中性脂肪です。
しかし、コレステロールの中には、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)という過剰になると血管にたまりやすく動脈硬化の原因となるものの他に、HDLコレステロール(善玉コレステロール)という全身の余ったコレステロールを抜き取って肝臓まで運んでくれる、動脈硬化を予防するコレステロールがあります。このHDLコレステロール(善玉コレステロール)は高いことが望ましく、この値が低いときも病気と診断されるようになり、病名も高脂血症から脂質異常症と呼ぶようになりました。
つまり、高脂血症(脂質異常症)は、血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪が多くなりすぎている状態、またはHDLコレステロール(善玉コレステロール)が少ない状態が続く病気です。高脂血症(脂質異常症)は動脈硬化の原因であり、放置すると、心筋梗塞や脳卒中などの深刻な病気が引き起こされることになります。
高脂血症(脂質異常症)は早期の診断・治療、合併症の検査が大切です。この病気に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 3. 06
「アルツハイマー型認知症の新薬」承認申請の動きです。
アルツハイマー型認知症治療薬について、世界的な標準治療薬である「ガランタミン」(一般名・臭化水素酸ガランタミン)と、「メマンチン」(同・塩酸メマンチン)が、厚生労働省に対し承認申請されました。いずれも審査に1年ほどはかかる見通しです。
国内のアルツハイマー型認知症患者は100万人以上とも言われますが、現在、治療薬は、「アリセプト」しか承認されていません。承認申請された「ガランタミン」はアリセプトと同じように脳内の神経に情報を流すのに必要な物質アセチルコリンの分解を抑える作用に加え、アセチルコリンの産生も促します。「メマンチン」は脳の神経細胞が壊れるのを防ぐ作用があります。2剤ともアリセプトのように認知症の進行を緩やかにする効果が期待される薬です。
2010. 3. 04
「塩分のとり過ぎと高血圧との関係は?」
塩分をとり過ぎると様々な弊害が生じますが、良く知られているのが塩分と高血圧の関係です。食塩による血圧上昇との関係(食塩感受性)には個人差があるようです。食塩をとると血圧が上がり減塩すると血圧が下がる人(食塩感受性の人)と、食塩をとっても血圧が上がらず減塩しても血圧が下がらない人(食塩非感受性の人)がいるのです。研究で、日本人の本態性高血圧の3~4割は食塩感受性高血圧であり、他は食塩の増減でも血圧の変化の少ない食塩非感受性高血圧ということが分かっています。この体質は遺伝するとされていますし、食塩感受性に関係するとされる遺伝子多型もいくつか発見されています。しかし、現在はまだ食塩感受性を測る方法が確立されておらず、一般的には高血圧を予防するためには食塩を減らしたほうがよいとされています。
現在、日本人は1日平均12gから13gとかなり食塩をとっているという統計がありますが、目標値は10g未満にしようとすすめられています。高血圧患者の場合は、日本高血圧学会の定めた目標では1日6g未満(高血圧治療ガイドライン2009年版)となっています。
高血圧に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 3. 02
「小児用肺炎球菌ワクチン(プレベナー)」について
小児向けの肺炎球菌ワクチン(PCV7)「プレベナー」が日本で接種可能となりました。この「プレベナー」ですが、約90種類の肺炎球菌の血清型のうち、小児で侵襲性肺炎球菌感染症を引き起こすことが多い7つの血清型を選んでワクチン化したもので、世界ではすでに、40の国や地域で定期接種されています。肺炎球菌は、細菌性髄膜炎原因菌の約20%を占めており、約55%を占めるインフルエンザ菌b型(Hib:ヒブ)に次いで多い細菌です。この「プレベナー」とインフルエンザ菌b型(Hib:ヒブ)に対するワクチン「アクトヒブ」合わせて接種することで、小児期の髄膜炎や菌血症にともなう肺炎を予防できます。
接種対象年齢は、生後2ヶ月以後~9歳まですが、初回接種の年齢によって接種回数が異なります(初回接種年齢2カ月~6カ月齢:1カ月おきに3回+60日後以上あけての1回=合計4回、初回接種年齢7カ月~11カ月齢:1カ月あけて2回+60日後以上あけての1回=合計3回、初回接種年齢12カ月~23カ月齢:60日以上あけて2回=合計2回、初回接種年齢24カ月齢~9歳:1回接種のみ)。
当院でもワクチン接種を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2010. 3. 01
「家庭での血圧測定のすすめ」を特集しました
院内広報誌「じゅんくり」3月号を発行しました。特集は「家庭での血圧測定のすすめ」です。最近は、血圧への関心が高く、血圧計を備えている家庭も増えてきました。血圧は、測る時間や環境、手順によって変動するため、正しく測定し、正しく評価することが大切です。そこで、「正しい家庭血圧の測り方」についてまとめてみました。
また、料理レシピは、「菜の花のそぼろあえ」 を紹介しています。初春が旬の「菜の花」を使ったレシピです。菜の花は、カルシウムや鉄などのミネラルやビタミン類を豊富に含む葉野菜で、高血圧の予防や免疫力向上などに効果があります。どうぞお試し下さい。院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 2. 26
「老人性高血圧について」
老人性高血圧とは、老化に伴う大動脈の弾力性低下が原因の高血圧です。特徴は、最高血圧(収縮期血圧)が高く最低血圧(拡張期血圧)はむしろ低めで、最高血圧と最低血圧との差(脈圧)が大きいことです。一般的に、脈圧の大きさは動脈硬化の程度を反映しています。動脈硬化により大動脈が硬くなり、伸展性、弾力性がなくなるため最高血圧が上昇し、脈圧が大きくなります。また、老人性高血圧では、動脈硬化の進行により、血圧調整が上手くいかないため血圧が変動しやすく、起立性低血圧(立ちくらみ)・食後低血圧・入浴後低血圧・夜間の血圧低下などを起こしやすい特徴があります。かつて老人性高血圧は、治療は必要ないといわれていましたが、現在ではある程度の血圧を下げる治療が必要とされています。ただし、ゆっくり少しずつ目標血圧値まで下げるなどの注意が必要です。また、高齢になると他の病気の合併や、すでに薬を複数使用している場合も多く、各個人に適した治療の選択が必要となります。
高血圧といっても色々な病態が考えられ、それに適した検査や治療があります。高血圧に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 2. 25
「高血圧の入浴に対する注意点は?」
血圧は入浴で急変動しやすく、注意が必要です。特に高齢者の突然死は、一日の時間帯の中で入浴前後が一番多く、睡眠中の10倍にもなります。入浴は熱いと危険なので、ぬるめのお湯に入り、ゆっくり上がって、着替えの部屋が寒くないようにします。適温(40℃前後)で10分程度を目安に入るとよいでしょう。また、お酒を飲んだあとにすぐにお風呂に入らないことです。飲酒をすると血液の流れが良くなっているのでこんなときに温度差が大きい入浴は、血圧を一気に上げてしまうので避けるようにします。
高血圧といっても色々な病態が考えられ、それに適した検査や治療があります。高血圧に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 2. 24
「下の血圧が高いとは?」
下の血圧のみ高い、拡張期高血圧の方が多くおられます。拡張期血圧(下の血圧)が90以上であば、収縮期血圧(上の血圧)が高くなくても高血圧です。拡張期血圧のみ高くなるのは、末しょうの血管抵抗が増加しているが、大血管の弾力性がまだ保たれている病態であり、比較的早期の高血圧にみられます。肥満、運動不足などの生活習慣が原因の場合が多く、60歳までの比較的若い人に見受けられます。ただし、二次性高血圧症(血圧上昇の原因となるはっきりとした疾患がある高血圧のこと)でも拡張期血圧の上昇が目立つ場合もあり、原因疾患の精査が必要です。
高血圧といっても色々な病態が考えられ、それに適した検査や治療があります。高血圧に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 2. 23
「麻しん・風しんのワクチンを受けましょう!」
今年4月に小学1年生になる方、現在中学1年生の方、現在高校3年生の方で、2回目の麻しん・風しんのワクチンをまだ受けていない方は追加接種を受けましょう。
接種期間(3月31日まで)を過ぎると任意の予防接種となり、全額自己負担になりますので、対象となるお子様をお持ちの保護者の方で、もしまだ予防接種を受けておられない場合は、この期間内に受けて下さい。当院でも接種可能です。
2010. 2. 22
「新型インフルエンザ、全都道府県で注意報以下に」
国立感染症研究所は19日、最新の1週間(2月8日~2月14日)に全国約5千の定点医療機関を受診したインフルエンザ患者(ほとんどが新型の豚インフルエンザとみられる)は、1医療機関あたり2.81人(前週4.26人)と発表した。3週連続で減少し、全都道府県で注意報レベルの10人を下回りました。
広島市内のインフルエンザの流行状況も、最新の1週間(2月8日~2月14日)は、1医療機関あたり1.22人と、前週からさらに減少しています。また、現在、季節性インフルエンザの流行は確認されていません。
新型インフルの流行はいったんピークを過ぎたとみられますが、引き続きの注意をお願いします。
2010. 2. 20
「今秋のインフルエンザ予防接種はどうなるの?」
今年の秋は、インフルエンザ予防接種ワクチンが1種類にまとめられる見通しになりました。これは世界保健機関(WHO)が、インフルワクチンに新型の豚インフルエンザを組み込むことを推奨すると発表したからで、今季のように季節性と新型の2種類のワクチンを打つ必要がなくなる見込みです。
今季については、季節性ワクチンはAソ連型、A香港型、B型の3タイプのウイルスが対象で、インフルエンザワクチンは1種類で最大3タイプのウイルスにしか対応できないため、新型に対しては、新たにワクチンを作る必要がありました。このため、2種類のワクチンが存在することとなり、特に1~13歳未満の子どもは季節性と新型を2回ずつ計4回も打つことになりました。
来季のワクチンについては、WHOがAソ連型の代わりに新型を入れることを推奨しており、国内では感染研が専門家の検討会議でワクチンのもとになるウイルス株を選び、厚生労働省が最終決定しますが、WHOが推奨する新型とA香港型、B型という組み合わせになるのは確実とみられます。また、ワクチンが1種類となるため、国内産でまかなえる可能性も高くなりました。
2010. 2. 19
「動脈硬化が心配です。どのような検査がありますか?」
動脈硬化を疑う状態として、血圧を測定し、収縮期血圧と拡張期血圧の差が大きければ、全身の動脈硬化の進行を疑います。動脈硬化の検査ですが、脈波伝播速度(PWV)や足関節上腕血圧比(ABI)の検査(血管年齢検査)は、全身の動脈硬化の状態を知るための検査です。首(頸部)や足(下肢)動脈の超音波検査では、特定の部位の動脈硬化(プラーク)を知ることができます。これらの検査は比較的簡便に行うことができます。また、頭部MRIやCT検査も頭頸部の血管の状態を把握するのに有用です。まず、上記のような比較的簡便な検査を行い、必要があれば、血管を直接みる検査(血流シンチグラム、カテーテルを使った血管造影や血管の観察など)を行うのが一般的です。
脈波伝播速度(PWV)と足関節上腕血圧比(ABI)の検査について、脈波伝播速度(PWV)とは、心臓から押し出された血液によって起きた拍動が手や足に届くまでの速度のことで、血管が硬いほど、その速度は速くなります。足関節上腕血圧比(ABI)とは、上腕と足首の血圧の比のことで、足に動脈硬化があるような場合にはこの値が低くなります。これら2つの検査は一度に行うことができ、健康診断などにも取り入れられています。
血管の超音波検査ですが、首(頸部)や足(下肢)の動脈を超音波検査で観察して、動脈硬化の程度をはかる検査です。頭頸部や足の血管の狭くなっている場所や程度をみることができます。
その他には、心電図や心エコー検査を行います。動脈硬化があると、心臓に負担がかかり心臓が大きくなったり、収縮するときの形に異常が生じることがありるため、心電図や超音波検査で心臓が正常に動いているかどうかを検査します。
当院では、上記の動脈硬化の検査が可能です。お気軽にご相談下さい。
2010. 2. 18
「高血圧が長く続くと?」
血管の壁は、本来弾力性があるのですが、高血圧が長く続くと、血管はいつも張りつめた状態におかれ、次第に厚くなり、そして硬くなります。これが動脈硬化の状態です。この動脈硬化は、大血管にも小血管にも起こり、脳梗塞や脳出血、心筋梗塞、大動脈瘤、眼底出血などの原因となります。また、心臓にも高い血圧に打ち勝つために負担がかかり、心臓肥大や心不全を起こします。このような合併症を起こさないためにも、血圧管理は重要になります。
高血圧の治療や合併症の検査など、高血圧に関するご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 2. 17
「高血圧の種類~本態性高血圧と二次性高血圧」についてご存知ですか?
高血圧には本態性高血圧と二次性高血圧があります。
「本態性高血圧」は、原因となる疾患がないものをいい、高血圧の90%以上がこれに当たります。本態性高血圧は遺伝的な因子や過剰な塩分摂取、肥満、精神的ストレス、タバコ、お酒など、生活習慣の関与しています。
「二次性高血圧」は、血圧上昇の原因となるはっきりとした疾患があるもので、高血圧の10%程度にみられます。原因疾患には、腎臓病に伴う腎実質性高血圧症や腎動脈の狭窄による腎血管性高血圧症が多くみられますが、原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫などの副腎疾患や、その他の内分泌疾患に伴う二次性高血圧症も存在します。これら二次性高血圧は、原因となる疾患を早めに診断し治療することで血圧の改善がみられます。そのため、高血圧の診療においては、まず、二次性高血圧症であるかどうかの診断をしっかり行う必要があります。
当院では、高血圧の治療や合併症の検査のみならず、二次性高血圧の検査が可能です。ご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 2. 16
「ヒブ(Hib)ワクチン」の任意接種について
お問い合わせが多いため、本日は、ヒブ(Hib)ワクチンについて取り上げました。ヒブワクチンは、ヘモフィルス-インフルエンザb型菌という、乳幼児の細菌性髄膜炎の原因の半分を占める細菌に対する不活化ワクチンです。細菌性髄膜炎にかかると命をなくしたり、後遺症を残す子が30%いますが、それを防ぐためのワクチンです。ちなみに、このインフルエンザ菌は細菌であって、普段多くの人がかかるインフルエンザウイルスとは全く別で関係ありません。
対象年齢は5歳未満です。この髄膜炎のおこりやすいのが2歳未満で、特に1歳未満です。接種開始時期によって接種回数が違いますが、これは年齢が大きくなると自然に免疫がついていくためです。
・2ヶ月以上7ヶ月未満 :初回免疫3回、追加免疫1回
・7ヶ月以上1歳未満 :初回免疫2回 、追加免疫1回
・1歳以上5歳未満 :1回接種
ヒブワクチンは、他のすべてのワクチンと同時接種ができます。また、ヒブワクチンは不活化ワクチンですから、次の他の種類の予防接種までの間隔は1週間以上あければ接種できます。初回免疫は4~8週間隔で接種となっていますが、DPT(3種混合)と同様に3~8週間でも接種可能です。
ヒブワクチンは、当院で接種可能ですが、需要が供給を上回っておりますので、接種希望の方は、必ずお問い合わせ下さい。
2010. 2. 15
「女性のメタボ基準」は腹囲をより厳しくするべか?
内臓脂肪の蓄積で生活習慣病の危険性が高まる「メタボリック症候群」の診断基準の妥当性について検討していた厚生労働省研究班は、現在は「90センチ以上」としている女性の腹囲を「80センチ以上」に厳しくすれば、より多くの脳卒中や心疾患を予防できるとする研究結果を示した。
研究班は、全国の40~74歳の男女約3万6千人に、腹囲と、血圧や血糖値などの関係を調べた。メタボリック症候群は、内臓脂肪蓄積に加え脂質異常、高血圧、高血糖のうち2項目以上に該当する状態だが、男性で85センチ前後、女性で80センチ前後を上回ると、そうした状態になる可能性が3倍に高まり、心筋梗塞や脳卒中が起きるリスクが大幅に上昇することが分かった。
メタボリック症候群は、日本肥満学会などが2005年に「腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上」などの診断基準をまとめ、特定健診にも採用されているが、女性の腹囲が男性より緩い点などに異論が出ており、基準の変更について検討する必要もありそうです。
2010. 2. 13
「白衣高血圧と仮面高血圧」についてご存知ですか?
高血圧が疑われる場合、注意が必要なのが白衣高血圧と仮面高血圧です。「白衣高血圧」は、家庭で血圧測定をすると正常値なのに、病院で医師など、白衣の人を見ると緊張して血圧が高くなるという人のことです。軽い高血圧の人の2~3割が白衣高血圧ともいわれています。白衣高血圧は、心血管系の大きなリスクではないことがわかっていますので治療は不要とされますが、病院での血圧だけでは判断できません。家庭血圧と病院での血圧を比較することで、正しい診断ができます。
白衣高血圧と全く逆のケースで仮面高血圧と呼ばれるものがあります。「仮面高血圧」は、病院で測定した血圧は正常値なのですが、診療時以外の家庭血圧は高血圧を示す、隠れ高血圧状態のことを指します。仮面高血圧はどうして起こるのでしょうか。普段仕事に追われてストレスを抱えている人は、診察時に仕事を離れてリラックスした状態になるため、血圧が下がる。また、ヘビースモーカーの人は、診察時は喫煙していないためニコチンの影響が少なく、血圧が下がる。このように、仮面高血圧はストレスや喫煙との関連が考えられます。仮面高血圧のため、普段の高血圧が発見されないままでいると、心臓、脳、腎臓などの大切な臓器の障害が進行します。特に仮面高血圧の中でも早朝に血圧が高くなる早朝高血圧は、心筋梗塞や脳卒中を起こしやすく危険です。仮面高血圧の診断にも、家庭血圧の測定が大切です。家庭血圧から仮面高血圧が疑われる場合は、当院に遠慮なくご相談下さい。
2010. 2. 12
「家庭血圧の正常値は?」
血圧は、病院で測る場合と、家庭で測る場合で、数値が異なります。高血圧の方に限らず一般の人でも、病院で測ると家庭よりも高い数値が出ることがわかっています。家庭ではリラックスして測定できますが、病院ではどうしても緊張したりして、血圧値が上がってしまうようです。病院で測定した血圧は「診察室血圧」または「随時血圧」と呼ばれ、家庭で測る「家庭血圧」に比べると、収縮期血圧で20~30mmHg、拡張期血圧で10mmHgも高くなる傾向にあります。日本高血圧学会では、診察室血圧については、140/90mmHg以上を高血圧としますが、家庭血圧については、135/85mmHg以上を高血圧とし、125/80mmHg未満を正常血圧の基準として採用しています。
高血圧は動脈硬化の3大危険因子(他の2つは高脂血症、喫煙)の一つで、症状がないまま脳、心臓、腎臓などの大切な臓器の障害が進行するため、家庭血圧の測定は重要です。
2010. 2. 10
「職場における健康診断推進運動」についてご存知ですか?
毎年2月1日から2月末日まで、「職場における健康診断推進運動」が実施されているのをご存知ですか。働く人々の健やかな職業生活の確保を図るため、平成元年度に第1回が開催されて以来、本年で第21回目となります。厚生労働省の平成19年労働者健康状況調査結果によると、常用者の健康診断受診率は、5,000 名以上の事業所で93.3%、100~299名の事業所で84.8%、50~99名の事業所で81.8%と、事業所規模が小さくなるにつれて受診率が低下しています。そこで、平成21年度においては、中小企業における健康診断の実施促進を重点においています。
当院では、職場検診(雇用時健康診断、定期健康診断)など、各種検診を随時行っております。お気軽にご相談下さい。
2010. 2. 09
「大豆食品で肺がんリスク低下」、たばこを吸わない男性での研究結果です。
たばこを吸わない男性では、豆腐や納豆などの大豆食品に含まれるイソフラボンの摂取量が多い人が肺がんになるリスクは、摂取量が少ない人の半分以下であることが、厚生労働省研究班の大規模追跡調査でわかった。
研究班は岩手、秋田など8県に住む45~74歳の男女約7万6千人を平均約11年間、追跡調査し、大豆などに含まれるイソフラボンの摂取量と肺がん発症との関連を調べた。
たばこを吸ったことのない男性では、イソフラボンの摂取が多い人ほど肺がんのリスクが低く、豆腐に換算して毎日3分の2丁分を摂取する人は、摂取量がその5分の1の人に比べて、リスクが43%だった。たばこを吸う人は、たばこの影響が大きく差が見られなかった。女性では肺がんの症例が少なく、有意な差はなかった。
大豆食品が肺がんを予防する可能性はあるようですが、まずは禁煙が大切です。
2010. 2. 08
「職場の禁煙義務付けへ」、職場の原則禁煙化へ、法改正の動きです。
他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」から労働者を守るため、厚生労働省は、事業者に受動喫煙を防ぐよう義務づける労働安全衛生法の改正案を、早ければ来年の通常国会にも出す方針です。 法改正が実現すれば、通常の事務所や工場では、仕事をする空間での喫煙はできなくなります。ただ、男性の喫煙率が3割を超える中で、建物をすべて禁煙にするのは非現実的だという意見も多く、当面は喫煙室の設置を認めることになりそうです。また、 飲食店や交通機関、宿泊施設など、接客する従業員が煙を吸わされる職場の扱いも問題で、従業員の受動喫煙を防ぐには客席などを全面禁煙にする必要があるが、顧客との関係で禁煙が難しい場合は、煙が含む有害物質の空気中の濃度に基準を設け、換気などの対策を徹底させる方向で規制を検討しているようです。
欧米では、公共の場での喫煙は厳しく規制される例が多く、今後の法改正への動きに注目です。
2010. 2. 06
「血圧はいつ、どのように測れば良いのですか?」
これも多い質問です。血圧は、測る時間や環境、手順によって変動します。環境をきちんと整えて、正しい手順で測定する習慣を持つことが大切です。また、血圧を毎日測定・記録し、継続的に血圧の変化を把握することが、血圧管理の重要なポイントになります。そこで本日は、正しい血圧の測り方についてまとめました。
血圧計は上腕にマンシェット(空気を送って腕を圧迫するもの)を巻いて測るタイプのものがお勧めです。通常は朝の起床後1時間以内に、排尿をすませ、朝食や薬を飲む前に測ります。可能であれば、夜の就寝前も測って下さい。毎日同じような時間に測定するように心がけて下さい。変化をつかむためには、できれば毎日、少なくとも週に3日以上、薬を変えたときや初めて治療を始めるときには少なくとも週に5日は血圧を測定するいうのが、日本高血圧学会の指針です。
血圧の測り方ですが、可能な限り座って測定します。毎回同じ姿勢で測ることが大切です。測定の少なくとも5分前には席につき、1~2分は安静にしてから測定して下さい。測る腕は利き腕の反対が原則ですが、左右の差が大きいときは、高いほうで測ります。 血圧計の操作手順ですが、まず、マンシェットを腕に巻いたときに、マンシェットが心臓の高さにくるように腕の位置を調整します。クッションやタオルなどに腕を置くとよいでしょう。反対側の手で、ひじのあたりを触りながら、脈を打っている部分(上腕動脈)を探します。次に、腕に巻くマンシェットには、長方形のゴムの袋が入っていますが、このゴム袋の中心が、上腕動脈上にくるように腕に巻きます。その時に、マンシェットは、空気を完全に抜いて、マンシェットの下端が、ひじの中心から指1本分上に来るように、指が1本はいるくらいのきつさで巻きます。最後に、血圧計のスイッチを押して測定します。測る際には、背筋を伸ばし、マンシェットと心臓を同じ高さにし、腕には力を入れないように注意してください。腕の太さにあったマンシェットを用意することも大切です。血圧計購入時に確認して下さい。
以上です。ご参考になさって下さい。なお、ご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。血圧測定方法の指導も行います。
2010. 2. 05
「家の血圧計はどのようなタイプを選べばよいのでしょうか?」
家庭用血圧計について、どのようなタイプを選べばよいか、よく相談を受けます。最近では、様々なタイプの血圧計が、比較的手頃な価格で発売されています。測定部位も、上腕(肩と肘の間)、手首、指先と様々です。正しく測定するためには、どのようなタイプを選べばよいのでしょうか。本日は、血圧の測定方式と血圧計の選び方について紹介します。
血圧の測定方式ですが、コロトコフ法(聴診法)とオシロメトリック法があります。コロトコフ法(聴診法)は、まず、カフを腕に巻いて動脈を圧迫し、血液の流れを止めます。その後空気を抜くと、血液が再度流れはじめます。この時の、血管に血液がぶつかる音(コロトコフ音)を聞いて測定する方法です。WHO(世界保健機関)では、コロトコフ法を推奨しているため、当院では通常この方法で血圧を測定しています。一方、オシロメトリック法は、途絶えた血流が流れはじめる時の動脈壁の振動を、センサーでキャッチして測定する方法で、家庭で普及しているのはほとんどこのタイプになります 。
次に、血圧計の選び方ですが、できれば上腕にマンシェット(空気を送って腕を圧迫するもの)を巻いて測るタイプのものが安定したデータが得られおすすめです。手首、指先のタイプは心臓の高さで測定するように注意する必要があり、姿勢によってはデータが不安定になります。手首、指先のタイプは、腕まくりせず測定できる簡便さがあり、全く同じ条件で測定できて、測定値そのもののより前回値との比較をしたい場合は有用です。
以上です。ご参考になさって下さい。なお、ご質問などございましたら遠慮なく当院にお尋ね下さい。
2010. 2. 04
「新たな抗インフルエンザ治療薬」、承認申請の動きです。
第一三共は1日、抗インフルエンザウイルス治療薬「CS―8958」の製造販売について、厚生労働省に承認申請手続きを行った、と発表した。A型とB型のインフルエンザに効く成人と小児向けの吸入薬です。既存のタミフルは1日2回、5日間の投与が必要だが、新薬は口から吸入するタイプで、1回の使用でタミフルを5日間使用したのと同じ治療効果があるという。2010年度中に販売できる見通しです。
2010. 2. 03
「子供の誤飲事故」、原因の1位は?
家庭で起きる子供の誤飲事故のうち、08年度に最も多かったのは「たばこ」(33・3%)で、1979年度の調査開始以来、30年連続で最多となったことが、厚生労働省の「家庭用品などにかかる健康被害病院モニター報告」で分かった。このデータは、全国7カ所の病院で扱った477件の誤飲事故を集計したもので、このうちたばこは159件に登り、全体に占める割合は前年度(33・6%)とほぼ同じあった。年齢別では生後6カ月~1歳半に集中しており、139件にのぼった。財団法人日本中毒情報センターは「たばこの誤飲事故が多いのは畳の上での生活が多い日本特有の傾向で、大人の不注意で床や低いテーブルなど乳幼児の手が届きやすい場所にたばこが置かれる」と分析している。たばこを吸う人は、乳幼児が飲み込んでしまう危険があることを十分認識し、誤飲には注意して下さい。
2010. 2. 02
「広島市内のインフルエンザの流行状況」について最新情報です。
平成22年第3週(1月18日~1月24日)は、1医療機関あたり7.32人と、前週からやや増加しました。12月は大きく減少しましたが、1月は注意報レベル(1医療機関あたり10.0人)を下回っているものの、ほぼ横ばいで推移しています。広島市衛生研究所の検査結果から、現在、季節性インフルエンザの流行は確認されていません。全国的にも、インフルエンザ患者が8週間ぶりに増加しており、引き続き、新型インフルエンザに対する注意が必要で、予防接種も対策のひとつと考えます。新型インフルエンザ予防接種に関して、広島県では、1月19日から、すべての希望される方が接種可能となりました。当院では、現在、国産ワクチンの在庫があり、予約なしでも接種可能です。接種状況やワクチンに対するご質問などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 2. 01
「花粉症」について特集しました。
2月に入り、花粉症のシーズンがやってきました。花粉症患者数は増加の一途をたどり、日本の花粉症総人口は2000万人以上、スギ花粉症だけで1500万人以上、5人に1人は花粉症ともいわれ、多くの方が花粉症に悩まされています。また、子供の花粉症も大人と同様に増えており、しかもだんだん低年齢化しています。スギ抗原の増加、大気汚染、居住空間の気密化、食生活の変化などの様々な環境因子が関係しているようです。そこで、院内広報誌「じゅんくり」第8号(2月号)では、まさに“日本の国民病”とも呼ばれている「花粉症」を特集しました。また、料理レシピは、「小松菜と豚のオイスター炒め」 を紹介しています。「小松菜」は、カルシウムがほうれん草の3倍以上も含まれており、骨粗鬆症の予防に役立ちます。また、βカロテン、ビタミンC・E、ナイアシンなども多く含まれており栄養の宝庫です。どうぞお試し下さい。院内広報誌「じゅんくり」は、院内待合にて配布しておりますのでどうぞご覧下さい。
2010. 1. 30
「生活習慣病予防週間」についてご存知ですか?
明日から2月ですが、厚生労働省では平成9年より毎年、特に脳卒中が多発する時期である寒冷期の2月1日から7日を「生活習慣病予防週間」としています。その趣旨としては、「生活習慣病を予防するためには、健康づくりのための正しい知識の普及啓発を図ることが重要であり、そのため本予防週間では、自らの生活習慣を見直し、行動変容を促すために必要な情報を提供することとしている。」(平成20年度実施要綱より一部抜粋)、とされています。
本年度のスローガンは、「自分流 楽しく続ける 健康づくり」で、公募により厚生労働省が定めたものです。本年度の予防週間では、生活習慣病予防対策全般について一層の推進を図るため、定期的な運動習慣の獲得、正しい食生活の確立、禁煙、定期的な健康診査の受診等のために必要な情報の提供を図り、その予防を強力に推進することを目指します。
生活習慣病とは、「癌」「心臓病」「脳卒中」など一般に30歳代以上の世代から発症しやすくなる病気の総称で、以前は「成人病」と呼ばれていましたが、その原因の大半が長年にわたる生活習慣にあり、子供の頃から予防に気を附けなければならないことから、「生活習慣病」と名前が改められました。皆さんもこの機会に生活習慣について一度考えてみてはいかがでしょうか。また、当院では、健康相談や生活習慣病の検査、治療が可能です。お気軽にご相談下さい。
2010. 1. 29
「肥満症を改善する医療用医薬品の開発」についてです。
武田薬品工業は肥満症を改善する医療用医薬品の開発を日米で進める。2010年度中に厚生労働省へ製造販売承認を申請し、米国では年内に最終段階の臨床試験(治験)に入る。
日本で開発している新薬候補は体内で脂肪を分解する酵素「リパーゼ」の働きを阻害し、食事で取った脂肪を吸収せずに便として排出することで脂肪の蓄積を防ぎ、体重を減らす効果が期待されている。10年度に申請すれば12年度にも発売できるとみられる。脂肪の吸収を防ぐ日本初の薬で、肥満症に対する薬物治療が可能となるため、早期の実用化が大いに期待されます。
2010. 1. 28
「日本脳炎の追加接種見送り」、未設種となった人への対応についてです。
日本脳炎の予防接種が「積極的勧奨とはしない」とされた期間中に対象年齢を迎え、未接種だった人への対応について、厚生労働省の小委員会(委員長・加藤達夫国立成育医療センター総長)は27日、ワクチンの供給量が十分ないため、追加接種を2010年度から始めるのは見送ることで合意した。
この日の会議で厚労省は、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人は10年度に4~12歳になる人で必要な接種回数は1560万回、4~7歳に絞っても817万回との試算を公表。これに対し、接種が望ましい夏までの時期に追加接種用として供給できるワクチンは約180万回分しかないと説明した。このため、積極的勧奨が再開される予定の幼児への接種状況やワクチンの供給量をみながら、追加接種の開始時期を検討することとなった。
日本脳炎は過去の病気ではありません。例えば、昨年8月に熊本市在住の7歳の男児が日本脳炎ウイルスに感染、発症しています。この男児はワクチン接種を受けていませんでした。広島県も感染のリスクが高い地域であり、日本脳炎の予防接種を受けることをお勧めします。当院でも、日本脳炎の予防接種を行っておりますので、希望される方はお気軽にお問い合わせ下さい。
2010. 1. 27
「発症前にインフルエンザウイルス検出」、唾液を使った新しい検査方法が開発、試験中です。
新型インフルエンザの感染初期に、唾液に含まれる微量のウイルスを検出する方法を鹿児島大の隅田泰生教授(生物化学)らのグループが開発、兵庫医大(兵庫県西宮市)で検査機器の試験運用を進めている。
簡易検査キットと遺伝子検査の組み合わせによる確定診断方法に比べ、100分の1から1000分の1のウイルス量で検出可能といい「発症前でも感染が確認でき、早期治療で重症化を防ぐ効果が期待できる」としている。
隅田教授によると、ウイルスがヒトの細胞の表面を覆う糖鎖にくっついて感染することに着目。患者の唾液に含まれるウイルスに、人工的に作った糖鎖をつけた微小な粒子を付着させ濃縮、検出する方法を開発した。
新型インフルエンザの感染は通常、高熱などの症状が出た後、簡易検査キットで診断されるが、一定量以上のウイルスがないと結果が「陰性」となるケースがあります。この新しい検査方法は早期診断に有用と考えられ、早期の臨床での実用化が期待されます。
2010. 1. 26
「脳卒中と心臓病で高死亡率、被ばく量多い被爆者で」、放射線影響研究所の発表です。
広島、長崎の被爆者のうち、原爆による放射線の被ばく線量が多い人ほど脳卒中や心臓病による死亡率が高いことが、放射線影響研究所(放影研、広島市・長崎市)の調査で分かり、23日付の英医学誌ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルに発表した。
がん治療で数十グレイの高線量を浴びると、脳卒中や心臓病などの循環器疾患の発症リスクが高くなることは知られているが、今回の調査で、被爆者が浴びた数グレイ以下のレベルでもリスクが高くなる可能性が示された。
放影研は被ばく線量が推定可能な被爆者約8万6600人のうち、1950~2003年に脳卒中で死亡した約9600人分と、心臓病で死亡した約8400人分のデータを統計学的に分析したところ、被ばく線量が0・5~2グレイの中程度でも、線量が増えるほど両疾病による死亡率が高くなり、1グレイでは、0グレイのときより脳卒中で9%、心臓病で14%上回っていた。(1グレイは、広島の爆心地から1・1キロ、長崎の爆心地から1・25キロ地点での推定線量。)
2010. 1. 25
「一歩あるけば医療費0.0014円節約」、厚生労働省の研究班の試算です。
ふだんたくさん歩けば生活習慣病にかかりにくくなり、医療にかかる費用も減らせそうだ。じゃあ、その効果は1歩あたりいくら? 厚生労働省の研究班がそんな試算をしたら、「0.0014円」という結果が出た。ほんのちょっとにみえるが、日本全体でみれば年間2千億円前後の効果も期待できるらしい。
歩行習慣によって糖尿病や脳卒中、心筋梗塞(こうそく)などが起きにくくなることが知られているが、研究班はこうした病気に関して「歩数がどれだけ増えれば、発症リスクがどれだけ下がるか」を検討した研究論文を集めた。それぞれの病気の治療や入院にどれくらいの費用がかかっているかを示した厚労省の統計などを使い、いまよりも歩数がどれほど増えれば、医療費がどれくらい減らせそうかを調べた。
加藤昌之・国際協力医学研究振興財団主任研究員らが中年期の千人の集団をモデルに計算したら、現状より歩数が3千歩(2キロメートル前後、約30分)増えることで今後10年間にかかる医療費が1569万円、5千歩なら2512万円減らせそうなことがわかった。死亡者が出ることも考えて1人の1歩あたりを算出すると、それぞれ0.00147円、0.0014円となった。1万歩でほぼ14円。 「それだけ?」という気もするが、20歳以上の日本人みんなが毎日、いまより3千歩多く歩いたとすれば、年間で約1600億分円になる。
試算では、糖尿病や脳卒中、心筋梗塞などにかかる年間医療費を平均5.5%減らせることもわかった。高齢者も含めたこうした医療費は年4.9兆円ほどかかっているとされるので、2700億円近く節約できる計算だ。
もちろん、生活習慣病を防ぐには、ある程度まとまった歩数が必要で、ぜんぜん歩かない人が1歩増やしても、それだけで経済効果は望めないが、普段からたくさん歩くことを心がけたいものです。
2010. 1. 23
「輸入新型インフルエンザワクチン希望は山梨県の1県のみ」
新型インフルエンザの輸入ワクチンについて、厚生労働省は22日、山梨県を除く46都道府県が入荷を希望していないことを明らかにした。輸入ワクチンをめぐっては国の方針が当初の「2回接種」から「1回接種」に変更されたことから、「余る」と指摘されてきた。使用期限が約半年と短いものもあり、厚労省は余ったワクチンを備蓄する方針だが、一部の契約解除や途上国への寄付やなども視野に入れ、在庫の有効利用を検討し始めた。
厚労省はワクチンの輸入に向け、今月から全国の都道府県に対し、必要量を調査していた。その結果、現段階で入荷を希望したのは山梨県の200人分のみ。広島県も含め、他の都道府県は入荷を希望しなかった。
新型インフルエンザワクチンについて、広島県は19日からすべての希望される方が接種可能となりました。当院は、現在、国産ワクチンの在庫がありますので、予約なしで接種可能です。また、接種の状況などのワクチンに対するお問い合わせは、電話にて承ります。(電話:082-298-7799)
2010. 1. 22
「今春の花粉飛散、2月上旬から」
日本気象協会は19日、今春のスギ・シラカバ・ヒノキ花粉の飛散量の予測の第3報を発表した。第3報では、気象庁が発表した最新の季節予報や、花芽の観測結果を反映し、スギ・ヒノキの花粉が、早いところでは2月上旬ごろから飛散し、飛散量は、「2009年に比べて少ないから非常に少ない」と予測している。
当院では、花粉症(アレルギー性鼻炎)の治療として、症状を抑えるための内服薬・頓服薬・点鼻薬・点眼薬を用いた対症療法に加えて、アレルギーに対する抵抗力をつけることを目的とした注射療法も行っておりますので、お気軽にご相談下さい 。(電話:082-298-7799)
2010. 1. 21
「あなたの動脈の硬さは?」
当院では、血管年齢検査(血圧脈波検査)が可能となりました。血圧、血管の「硬さ」と「詰まり」を測定し、血管の状態や動脈硬化の程度を見ることができます。高血圧、高脂血症、メタボリック症候群、狭心症、心筋梗塞などの動脈硬化に関係した基礎疾患をお持ちの方はもちろんのこと、基礎疾患のない方も、心臓や動脈硬化に関する健康診断として、血管年齢の把握は大切です。検査時間は10分程度と手軽に行うことができ、予約もいりません。この検査に対するご質問などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。(電話:082-298-7799)
2010. 1. 20
「日本脳炎ワクチン」の情報です。
厚生労働省は、05年から事実上中断している日本脳炎ワクチンの定期接種について、5月から再開する方針を決めた。
新ワクチンの供給量と安全性に一定のメドが立ったためで、厚労省の予防接種部会委員会で専門家の意見が一致した。日本脳炎のワクチンは3~4歳に3回、9歳に1回の計4回接種するが、同省は最初の3回について再開する。
2010. 1. 19
「広島県の新型インフルエンザワクチン関連情報」です。
1月19日から、これまでの接種対象者の方に加え、「健康な成人」への接種を開始します。これで、「すべての希望される方」が接種可能となりました。
当院では、国産ワクチンの在庫がありますので、予約なしで接種可能です。また、接種の状況などのワクチンに対するお問い合わせは、電話にて承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。(電話:082-298-7799)
2010. 1. 18
「2社の輸入インフルエンザワクチンを特例承認」、健康成人の接種開始への動きです。
厚生労働省は15日、輸入が予定されている英グラクソ・スミスクライン(GSK)社とスイスのノバルティス社の新型インフルエンザワクチンを今月20日付で「特例承認」すると発表した。2社のワクチンは来月初めにも出荷され、中旬にも優先接種の対象外だった健康成人を中心に接種できる見通しとなった。
一方、厚労省はGSKから7400万回分、ノバルティスから2500万回分の計9900万回分のワクチンを購入する契約を結んでいるが、全量を輸入すると国産と合わせた数量が全国民分を上回り、大幅に余ることが確実になった。
長妻昭厚労相は記者会見で、都道府県を通じて輸入ワクチンの必要量を把握した上で、メーカー側と購入量などについてあらためて交渉する考えを示した。
また同省は、輸入ワクチンの承認により、希望するすべての人への新型ワクチン接種が可能になったとして、健康成人への国産ワクチン接種も2月中旬ごろから認める方針を示した。
2010. 1. 16
「日本脳炎予防接種、勧奨再開へ」05年以来5年ぶりです。
日本脳炎の定期予防接種について、厚生労働省の小委員会(委員長・加藤達夫国立成育医療センター総長)は15日、2010年度から、主に3、4歳児を想定した幼児期の3回接種を「積極的に勧奨」とすることで合意した。
接種後に急性散在性脳脊髄炎(ADEM)を発症した事例を受け、厚労省は05年5月、積極的に勧奨しないとの見解を発表していたが、勧奨を再開する。上部の部会などでの議論を経て、2月にも正式決定する。
積極的勧奨の差し控えによって、定期接種は事実上中断し、昨年、副作用が少ないと期待される新ワクチンによる接種が再開されたが、積極的勧奨は再開していなかった。
この間の接種率は極めて低く、未接種の子どもが増えて感染リスクが高まることが懸念されており、今後はこうした子どもへの接種をどう進めるかを検討する。
この日の小委員会で、新ワクチンはこれから10年度にかけて約700万本の出荷が見込まれ、幼児期の接種には十分な量が確保でき、勧奨再開をするべきだとの意見で合意した。
2010. 1. 15
「慢性疲労」を数値で診断、血液中のたんぱく質発見というニュースです。
原因不明の激しい疲労が半年以上も続く「慢性疲労症候群(CFS)」を診断できる血液中のたんぱく質を、大阪市立大の木山博資教授(解剖学)らが発見した。
CFSには自覚症状を中心に判定する診断基準はあるが、血液の検査値など客観的な指標(マーカー)はなく、今回の発見は健康診断などに活用できそうだ。
木山教授らは、5日連続の運動で極度に疲労させたラットの脳下垂体の中葉と呼ばれる部分を分析。「α―MSH」というたんぱく質が異常に分泌され、血液中のα―MSHの量も上昇していくことを突き止めた。α―MSHの分泌は神経伝達物質ドーパミンが抑制しているが、ラットでは疲労がたまるにつれドーパミン産生能力が低下していた。
一方、CFSと診断された患者57人と、健康な30人の血液を使い、α―MSHの量も測定した。その結果、発症後5年未満の37人の平均値は健康な人に比べ、約50%も高かった。一晩徹夜した人の血液を調べてもα―MSHの量に変化はないことから、短期間の疲労とは関係がないこともわかった。CFS患者は潜在する人も含め、国内に200万人以上いるとされる。
2010. 1. 14
「欧州で新型インフルエンザワクチンが大量に余る見通しです。」
新型インフルエンザのワクチンの需要が当初の見込みを大きく下回り、ワクチンが余る見通しとなったドイツやフランスでは、製薬会社に発注したワクチンの購入を一部取りやめ、さらに余ったワクチンを発展途上国などに売却することを検討しています。
ヨーロッパでは、当初2回必要とみられていたワクチンの接種が1回で十分な効果が得られることがわかったことに加え、副作用に対する懸念などから、ワクチンの接種を希望する人たちが当初の見込みを大幅に下回り、ワクチンが大量に余る見通しとなっています。
このうちドイツは12日、すでに発注したワクチン5000万回分のうちの30%を取りやめることで製薬会社と合意し、さらに余っているワクチンをウクライナやトルコなど必要としている国々に売却することを検討しています。
また、フランスでも発注した9400万回分の半分を取りやめたうえ、さらに余ったワクチンを中東などに売却する方針で、今後、ワクチンが余っているほかのヨーロッパの国々でも同様の動きが出てくるものとみられます。
新型インフルエンザのワクチンをめぐっては流行に備えて需要が急増したため、一時は世界的にワクチンが不足するおそれが出ていましたが、一転して余ったワクチンをどうするかが各国の課題となっています。
2010. 1. 13
「新型インフル 検査キット開発」というニュースです。
国立国際医療センター(東京・新宿区)などの研究グループは、季節性インフルエンザの簡易検査の診断法を応用し、新型インフルエンザに感染しているかどうかを15分で判定できる簡易検査の診断キットを開発しました。
患者の鼻の中に入れた綿棒を試薬に浸し、その溶液を専用のプレートにたらすと、陽性の場合、15分程度で赤紫色の線が現れます。これまでの簡易検査では、季節性と新型のインフルエンザを区別することができず、診断するには数時間かけてウイルスの遺伝子を調べる必要がありましたが、新しいキットでは新型かどうかその場でわかるということです。
診断キットを開発した国立国際医療センター研究所の秋山徹室長は「できるだけ早く厚生労働省に医薬品としての承認申請を行い、医療現場で使えるようにしたい。キットを使えば、重症化のおそれのある患者に対して、早い段階から適切な治療が行えるようになる」と話しています。
2010. 1. 12
「60代以上の多くに新型インフルエンザに免疫か?」
現在の新型インフルエンザと過去に流行したスペイン風邪など、同じ「H1N1型」のインフルエンザウイルスの遺伝子分析から、60代以上の人の多くが新型への免疫を持っている可能性があるとの研究結果を科学技術振興機構の西浦博さきがけ研究者(理論疫学)と米国の研究者らのグループがまとめ、英科学誌に8日発表した。
グループは、11の国と地域で新型感染者の年齢分布を検討。75%以上が30歳未満に集中し、10~19歳がピークで、65歳以上は3%未満と少ないことを確認した。
これを踏まえ、1918年以降に流行したH1N1型のウイルスについて、人の免疫反応にかかわるウイルス表面のタンパク「ヘマグルチニン」の遺伝子配列を分析。18年以降40年代までに流行したウイルスと新型との間に、タンパクに付いている「糖鎖」と呼ばれる構造が一部脱落している共通点があることを突き止めた。77年以降に流行したウイルスにはこの特徴がなかった。
グループは、この流行時期によるウイルスの違いが、年齢による免疫の差が生じた理由とみており、60代以上には新型への免疫があるが、77年以降に生まれた人には免疫がないと考えた。
2010. 1. 09
輸入新型インフルエンザワクチンの国内臨床試験の結果が発表されました。
厚生労働省の欧州の2社から輸入する予定の新型インフルエンザワクチンの国内臨床試験の結果によると、健健康な成人に対して1回接種で十分な効果が確認されたが、国産ワクチンに比べ注射部位の痛みを訴える割合が高かった。
同省薬事・食品衛生審議会の部会は両ワクチンを「承認して差し支えない」との意見をまとめている。同省は資料をホームページで公開し、1月11日まで意見を募集、最終的に承認するかどうか決める。
英グラクソ・スミスクライン社のワクチンを用いた臨床試験は20~64歳の成人100人に実施、1回接種3週間後に95%の人が十分な免疫物質(抗体)を持ったことが分かった。1回接種後に98%の人が痛みを訴えた。スイス・ノバルティス社のワクチンは、20~60歳に投与された。約100人に半量を注射したところ、1回接種後に81%、2回接種後に96%の人に抗体が確認された。
2010. 1. 08
広島県の「新型インフルエンザ予防接種」に関する情報です。
広島県は、1月14日から、これまでの接種対象者の方に加え、「中学生」、「高校生」及び「65歳以上の高齢者」の接種を開始する予定となりました。
当院では、予約を開始しましたので接種を希望される方はお申し出下さい。(電話:082-298-7799)
当院は、新型インフルエンザの予防接種ができる医療機関です。県の決定した予防接種スケジュールに従い、予約や接種を行っておりますのでよろしくお願いします。
2010. 1. 07
今日は「七草の日」です。
一年の無病息災を願って1月7日に春の七草を使って作る七草粥。これは古くに中国から伝わった風習で、七草がゆに入れる七草は「春の七草」と呼ばれ、お正月に食べ過ぎた胃腸を休めると言われています。七草と呼ばれるのは、「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の7種類の野菜です。本日はこの七草の効能を紹介します。
「せり」=鉄分が多く含まれているので増血作用があり貧血の改善が期待できる他、便秘防止や風邪予防にも効果的と言われています。
「なずな」=ぺんぺん草のことで解熱や尿の出をよくする作用が期待できます。
「ごぎょう」=ハハコグサのことで痰切りに良く、気管支炎・扁桃炎・風邪の予防にも効果的といわれてます。
「はこべら」=タンパク質が比較的多く含まれミネラルその他の栄養に富んでいるため、古くから薬草として親しまれています。胃炎・胃弱に効果的といわれてます。
「ほとけのざ」=抗酸化物質が含まれており筋肉痛・打撲症などに効果的といわれてます。
「すずな」=かぶのこと。ジアスターゼが豊富に含まれているので消化を促進してくれますし、食物繊維が多いので腸の働きも良くする作用があります。
「すずしろ」=大根のこと。根にはジアスターゼが多く含まれており消化促進作用があります。その他にも辛味成分で抗酸化物質のメチルメルカプタンやイソチオシアネートが含まれているので、ガン予防にも効果的といわれています。葉にはカロテン・ビタミンC・ビタミンE・カルシウムなどが豊富に含まれています。
2010. 1. 06
5日に発表のあった、「広島市内のインフルエンザの流行状況」です。
第52週(12月21日~12月27日)には、1医療機関あたり11.03人と4週連続で減少していますが、まだ注意報レベル(1医療機関あたり10人)を超えており、多い状態が続いています。
現在発生しているインフルエンザのほとんどが新型インフルエンザ(A/H1N1)だと考えられますが、今後、季節性インフルエンザについても発生・増加が予想されることから、再度、流行が拡大する可能性があるため、注意が必要です。
2010. 1. 05
「水痘・ヒブワクチン・肺炎球菌の定期接種化を検討」
厚生労働省は、水痘(水ぼうそう)など3種類のワクチンを全額公費負担の「定期接種」にする検討を始めた。接種費用が無料のワクチンが少なく、「ワクチン後進国」と呼ばれる現状を打開するのがねらい。新型の豚インフルエンザの流行で、ワクチンの重要性が浮き彫りになったことが背景にある。
厚労省が新たに定期接種化を検討するのは、「水痘ワクチン」、乳幼児の重い細菌性髄膜炎を防ぐ「Hib(ヒブ)ワクチン」、細菌性髄膜炎や肺炎などを防ぐ「乳幼児向け肺炎球菌ワクチン」。定期接種のワクチンになれば、国の副作用被害救済制度の対象にもなる。
水痘ワクチンはすでに接種が実施されているが自己負担分がある任意接種で、接種率は約3割にとどまっている。ヒブワクチンも昨年末に使用が始まったが、乳幼児向けの肺炎球菌ワクチンは9月末に承認されたばかり。
厚労省は今後、各ワクチンの接種状況を踏まえ、効果を見極めたうえで定期接種化に必要な予防接種法の改正を目指すとみられる。ただし、ワクチンについては、副作用を懸念する意見も根強く、議論は曲折も予想される。
ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンは世界保健機関(WHO)が「定期接種にすべきだ」と勧告している。しかし、WHOが全地域に勧告しているワクチン8種類のうち、日本は4種類がまだ定期接種化していない。水痘も含め国内でも定期接種化を求める声が強く、昨秋の臨時国会でも新型ワクチンとともに議論された。
2010. 1. 04
「あたらないカキでブランド化を。」
冬の味覚を代表するカキに含まれているとされるノロウイルスを減らそうと、岡山県水産試験場(同県瀬戸内市)が研究を重ね、シソ科植物の香草オレガノに効果があることを突き止めた。
同試験場は香辛料やハーブ類に殺菌効果があることに注目。2007年、下水処理場の排水口近くで約2カ月かけてカキにノロウイルスを取り込ませ、ニンニクやオレガノなど10種類以上を食べさせる実験を開始した。
カキのエサである植物プランクトンに似せた直径約0・1ミリの球形カプセルに各成分を含ませて与えたところ、オレガノの場合だけ効果が表れ、ノロウイルスの検出が10~20%程度に激減した。
同試験場によると、必要なオレガノはカキ1個につき約10円で、実用化に向けて与えるオレガノの最適量を模索中だ。水揚げしたカキは出荷前にサンプル検査が必要で、検査費は県全体で1シーズン約500万円にもなる。岡山県漁連は「完全に抑制できることが確認できれば、検査コストを抑えることも期待できる」と注目している。
本年最初の「じゅんくり・いんたーねっと」です。今年も色々な話題を提供していきたいと思いますので、宜しくお願いします。
2009. 12. 29
「ビール大瓶毎日1本以上、乳がんリスク1.75倍に」
週にビール大瓶7本に相当する量を超える酒を飲む女性が乳がんになるリスクは、全く飲んだことがない女性の1・75倍との調査結果を、厚生労働省研究班(主任研究者・津金昌一郎国立がんセンター予防研究部長)が25日、発表した。
欧米で報告されていた飲酒と乳がんのリスクの関係を、日本人でも裏付ける結果。担当した岩崎基・国立がんセンター予防研究部室長は「飲みすぎないよう注意することが、一つの予防手段になることが示された」と話している。
研究班は、岩手、秋田など9府県の40~69歳の女性約5万人を平均13年間追跡。喫煙や閉経年齢など飲酒以外の要因を除き、飲酒量と乳がん発生率の関係を調べた。毎日ビール大瓶1本を飲んだ場合の1週間のエタノール量(150グラム)を目安にした。
その結果、150グラム超飲む人のリスクは飲んだことがない人の1・75倍だった。それ以下の量では、差はほとんどなかった。
今年の「じゅんくり・いんたーねっと」は終了です。来年も色々な話題を提供していきたいと思いますので、宜しくお願いします。
2009. 12. 28
「輸入新型インフルエンザワクチン承認へ」
輸入予定の海外メーカー2社の新型インフルエンザワクチンについて、国内販売承認の可否を検討する厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会は26日、条件付きで「承認して差し支えない」との結論をまとめた。
メーカーが行う臨床試験の結果を随時、速やかに報告することや、副作用に関する情報提供の徹底などが条件。吉田茂昭部会長は「これらの点について適切な対応がされれば、健康危機管理上の観点から承認して差し支えない」と述べた。
輸入ワクチンは、含まれる物質や接種方法が国産と異なるため、筋肉痛や関節痛などの副作用の発生頻度が国産よりも高めだという。
厚労省は部会の審議結果について、28日から1月11日まで一般からの意見募集(パブリックコメント)を実施。上部組織の薬事分科会での議論を経て、承認の可否を最終判断する。承認に当たっては、審査手続きを簡略化した「特例承認」を初めて適用する方針。順調に進めば、2月上旬にも主に健康な成人を対象に輸入ワクチンを使える見込みとなった。
2009. 12. 26
「献血対象年齢」の拡大の話題です。
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の血液事業部会は24日、400ミリリットルの全血献血対象を、現行の18歳以上から、17歳男性にも広げることを了承した。白血病などの治療に必要な血小板の成分献血の上限年齢も54歳から69歳に引き上げを認めた。
厚生労働省では、年明けに意見公募した後、同部会の最終承認を経て、年度内に省令を改正する見通しで、実際の運用は来年度以後になる。
日本赤十字社の試算では、年齢の拡大によって、約7万人の献血者が増えるという。
献血には、血液中のすべての成分を採る全血献血と、血小板などの成分だけを採る成分献血がある。現在、全血献血の年齢の下限は16歳。18歳以上は400ミリリットルだが、16、17歳は、体への負担を考慮して200ミリリットルの提供に限られていた。上限は原則69歳だが、血小板の成分献血に限り、54歳だった。
しかし、少子化などで若い世代からの提供が伸び悩んでいる。医療現場から効率よく使える400ミリの需要も高い。治療の進歩で成分輸血の求めも増えた。このため、安全性を検討し、対象拡大を認めた。
2009. 12. 25
季節性インフルエンザのワクチンを打っていると、新型インフルエンザのワクチンの効果が高まるという動物実験の結果を、オランダとイタリアの研究チームが23日付の米医学誌サイエンス・トランスレーショナル・メディシンで発表した。
研究チームは、感染の仕方が人間と似ているイタチの仲間フェレットを使ってワクチンの効果を検証した。新型ワクチン接種の1か月前に季節性のワクチンを接種すると、新型だけを接種した場合より、新型ウイルスに対する免疫の反応が高まった。
季節性ワクチンは新型ウイルスには効果がないとされ、当初、新型ワクチンは2回の接種が必要と予想されていた。しかし、各国の臨床実験の結果、健康な成人では1回で効果があることが分かった。詳しい仕組みは不明だが、過去に接種した季節性ワクチンが新型ワクチンの効果を増強する働きをしていると見られる。
2009. 12. 24
「鼻炎の子ども増加、文科省調査 アレルギー・花粉症広がる?」
鼻炎など鼻に疾患がある児童生徒の割合が小学校で12.6%、高校で9.6%などと過去最高にのぼったことが、文部科学省が17日に公表した2009年度学校保健統計調査速報でわかった。同省は「子供にアレルギーや花粉症が広がっていることが一因にあるのでは」としている。
鼻・副鼻腔(びくう)疾患の割合は1995年から上昇が続いている。ぜんそくの割合も増えており、今年度は小学校4.0%、高校1.9%で過去最高を更新した。
2009. 12. 22
「12歳児の虫歯、25年前の3分の1 過去最低1.4本」、学校保健統計調査(速報値)からです。
文部科学省が17日発表した2009年度学校保健統計調査(速報値)によると、12歳児の永久歯の虫歯は1人あたり1.40本で過去最低に。データがある25年前の4.75本の3分の1にまで減った。同省は「学校や家庭での歯磨き指導が効果を上げてきたのではないか」とみている。
速報によると、虫歯がある子どもは幼稚園が47%、小学校62%、中学校53%、高校62%で、それぞれ前年度より2~4ポイント下がった。いずれの学校種別でも30年前は89~96%の子どもに虫歯があり、80年代以降は低下傾向にあります。
2009. 12. 21
「第3のインフルエンザ治療薬ペラミビル、来月承認へ」
厚生労働省は18日、新型インフルエンザ対策として、タミフル、リレンザに続く第3のインフルエンザ治療薬「ペラミビル」(商品名・ラピアクタ)を1月にも承認する方針を決めた。タミフル耐性の新型インフルエンザウイルスが出現しており、医療現場での治療薬選択の幅を広げるのが狙い。
ペラミビルは点滴注射薬。経口や吸入で服用するタミフルなどと異なり、人工呼吸器で管理されたり、意識不明の状態に陥ったりした重症患者に使いやすいとされる。
2009. 12. 19
「小学生の視力低下止まらず、0・3未満が過去最多」
視力が0・3に満たない小学生の割合が、2008年度より0・2ポイント増えて7・3%に上り、過去最多となったことが17日、文部科学省が公表した09年度学校保健統計調査速報で分かった。調査項目に加わった1979年度の2・7倍。視力低下が止まらない現状が浮かんだ。
背景には、幼児期からのテレビゲーム、パソコンの影響があるとみられ、文科省は「目を酷使する機会が増えたのでは」と分析。
速報によると、「0・3未満」の児童の割合は、6年が14・9%(昨年度比0・9ポイント増)、4年が8・4%(同0・5ポイント増)。1年は1・0%、2年は2・7%で昨年度と同じ割合。
中学生は0・4ポイント減り22・0%。高校生も0・7ポイント減の27・7%だったが、「1・0未満」の割合は1・4ポイント増加し59・4%を占めた。
2009. 12. 18
「新型インフルエンザワクチン、中高生も1回接種に」
厚生労働省は16日、国産の新型インフルエンザワクチンの接種回数について、13歳以上の中高生も従来の「当面2回」から1回接種に変更すると発表した。この日開かれた専門家会合で、1回接種への見直しで意見が一致したことを受けた措置。
今回の変更により国産ワクチンの供給に余裕ができるため、輸入ワクチンの使用も予定していた65歳以上の高齢者約2100万人全員に国産を使うことが可能になった。また、優先接種対象外の健康な成人(高卒相当の18歳~64歳)の一部にも国産を使える見通しとなった。
厚労省は、1月後半に設定していた高校生の接種開始時期を1月初めに、2月としていた高齢者についても1月後半に早めた新たな接種スケジュールを公表した。
広島県の接種予定スケジュールにも、前倒しなどの変更があると思われます。
2009. 12. 17
広島県の新型インフルエンザワクチン接種についての最新情報です。
12月21日から、前回からの接種対象者である「妊婦」、「基礎疾患を有する方」、「1歳~小学校3年生」に加え、新たに、「1歳未満の小児の保護者」、「小学校4~6年生」の接種が開始となります。
また、「中学生」は1月14日からの接種になりそうですが、詳細はまだ未定です。
以上が最新情報です。当院では本日から、「1歳未満の小児の保護者」、「小学校4~6年生」の予約を開始しますので、当院での接種を希望される方はお申し出下さい。また、現在、「妊婦」、「基礎疾患を有する方」、「1歳~小学校3年生」の予防接種を行っておりますのでお問い合わせ下さい。(電話:082-298-7799)
2009. 12. 16
「新型インフルエンザワクチン、健康成人も接種、全国民対象へ」
政府の新型インフルエンザ対策本部は15日、基礎疾患(持病)のある人や妊婦などの優先対象者に接種を進めている新型ワクチンを、これまで対象外だった健康な成人にも接種することを決めた。
新たに対象となるのは19~64歳の健康な人。高校生以下を除いて接種回数が2回から原則1回に見直され、ワクチン供給に見通しがついたという。住民税の非課税世帯など低所得者に対する負担軽減措置も、優先対象者と同様に講じる。
政府は本年度内に国産ワクチンを5400万回分確保、海外メーカー2社から9900万回分を購入する方針。輸入が順調に進めば全国民分のワクチンが確保できる。健康成人の大部分には輸入品が使われる見込み。
ただ、輸入予定のワクチンについてはカナダでの副作用問題などを受けて承認手続きが遅れており、実際に使えるようになるのは1月以降になる見通しです。
2009. 12. 15
フクダ電子が「医療機器AED」のマンション向け販売に乗り出します。
フクダ電子は自動体外式除細動器(AED)を住宅向けに売り込む。このほど、首都圏のマンション管理大手数社に営業活動を始めた。AEDは心臓が突然けいれんして意識を失った患者に電気ショックを与えて心拍を回復させる医療機器。公共施設や企業向けの販売が景気低迷で伸び悩んでいるため、販売対象を広げた。
居住者向けにAEDの必要性を訴えるパンフレットを10万部作成した。マンション管理会社に居住者への配布を委託し、管理組合に購入かレンタルでの設置を促す。レンタル料金は5年契約の場合、月8000円前後を検討している。
2009. 12. 14
「新型インフルエンザ患者、乳児・成年増える」、感染患者の年代に変化がみられます。
新型インフルエンザ患者のなかで、大半を占めていた5~19歳の割合が減る一方、0~4歳の乳幼児、20~30代中心の成年層の割合が増えていることが11日、国立感染症研究所の発表で分かった。
9月には最大で患者全体の8割を占めた5~19歳は、11月23~29日の1週間で62%(前週70%)に減少。逆に、割合が増えているのは、0~4歳12.6%(11.6%)、20~29歳9.5%(6.9%)、30~39歳7.9%(5.8%)など。
同研究所は、特に5~14歳は、すでに相当数が感染していると推定。「今後、大きな増加はなく、むしろ短期間のうちに減少してくる可能性がある」と予測している。
2009. 12. 12
「新型インフルエンザ感染者の18%が無症状」、大阪の関西大倉高で行われた抗体検査の結果です。
大阪府は11日、新型インフルエンザの集団感染が5月に起きた関西大倉高校(同府茨木市)で、生徒や教職員ら647人にウイルス感染の有無を調べる抗体検査をした結果、感染したとみられる人のうち18・4%が、発熱やせきなどの症状が出ない「不顕性感染」だったと発表した。
不顕性感染とみられるのは18人で、高校生が17人、教職員が1人だった。
抗体検査は8月下旬、府立公衆衛生研究所が生徒550人、教職員95人、生徒の家族2人に協力を得て採血し実施。102人の血中から、過去にウイルスに感染した際にできたとみられる抗体が高い濃度で見つかった。
これほど大規模な新型インフルエンザ抗体検査の実施例は国内になく、新型でも不顕性感染が起きていることを具体的なデータで確認したのは初めてです。
2009. 12. 11
「インフルエンザ患者報告数が大幅減」、厚生労働省の集計結果です。
全国約5千の定点医療機関から6日までの1週間に報告されたインフルエンザ患者数が、前週の1機関当たり39・63人から約31人へと大幅に減少したことが厚生労働省などの10日までの集計で分かった。患者の大半は新型とみられる。
これまでも大型連休や祝日の影響で1機関当たり1人未満の小幅な減少があったが、今回はこうした要因が見当たらず、減少幅も大きい。厚労省は「流行がピークを越えたかどうか、各地の状況を見ながら分析している」としている。
集計によると、1週間に報告された患者数は約15万人。前週は約19万人だった。
報告数は、8月に流行入りの指標となる1機関当たり1人を上回り、10月上旬に注意報レベルの10人を突破。11月初めには警報レベルとなる30人を上回った。その後もペースは衰えたものの増加は続いていた。
今回の減少について押谷仁東北大教授(微生物学)は「症状が現れない『不顕性感染』も含めると、5歳から14歳までの年齢層では既に多くの人が感染したと考えられる」と分析している。
2009. 12. 10
「新型ワクチンの副反応は0.07%」との厚生労働省のまとめです。
新型インフルエンザワクチンについて、医療機関から都道府県を経由して報告があった接種者数に基づく10月16-31日の推定接種者92万2000人のうち、副反応が0.07%、重篤例が0.004%の割合であることが12月9日、厚生労働省のまとめで分かった。これまでに厚労省が発表した副反応の報告頻度は、医療機関へのワクチンの納入量を基に推計しており、接種者数の報告から推計した副反応の報告頻度の発表は初めてです。一方、納入量を基に推計した12月7日接種分までの副反応の報告頻度は0.02%、重篤例は0.002%です。
2009. 12. 09
「来春の花粉予測(ウェザーニューズ社)」を紹介します。
気象情報会社「ウェザーニューズ」は8日、来春のスギ花粉の飛散予想を発表した。今年の夏が全国的に日照不足だった影響で、2005年以降では最も少ない飛散量になるとみている。
同社によると、花粉の量は前年の夏の日照時間や最高気温、降水量と関係が深く、同社は過去のデータから独自に予想しており、各地から届く花芽の成長を撮影した写真も参考にしている。
予想によると、飛散が始まるのは西日本は2月上旬、関東周辺は2月中旬、東北が3月上旬。飛散量は関東や東北南部は前年の1割程度、北陸や甲信北部で2割程度、東北北部は5割程度と少ない。北海道は前年より1.4倍程度多い見込み。
2009. 12. 08
本日は、北里大を中心とするグループで行われた「生活習慣やストレス度などのアンケートによる調査結果」を紹介します。
北里大は、企業のメンタルヘルスを助言する日本ヴィクシーと共同で、東京都内の情報通信企業に勤務する20~40代の社員1500人を対象に、生活習慣やストレス度、意欲などをアンケート。〈1〉朝の目覚め〈2〉仕事中の眠気〈3〉休日の寝だめの3項目から睡眠の充足度を「高い」「普通」「低い」の3段階に分け、ストレスとの関係を調べた。
その結果、充足度の低い群は、高い群に比べてストレスを訴える割合が高く、「会社に行くのがつらい」「ぼーっとする」「集中力が低下する」と答えた人が、それぞれ11.7、11.4、6.6倍も多かった。
さらに、朝の目覚めの良さには、何が一番影響しているか詳しく分析したところ、20代では「上司との関係」、30代は「仕事の満足度」、40代は「リラックスできる時間」と、年代によってストレスの原因が違っていることがわかった。
2009. 12. 07
新型インフル患者が、これまで流行の中心となっていた小中高生以外で増加しています。
厚生労働省によると、これまで新型インフルエンザの推計患者は、小中高校生に当たる5-19歳が7割近くを占めていたが、11月23-29日は62.4%にまで低下。0-4歳、20歳代、30歳代など他の年代の患者が増加しています。
厚労省によると、インフルエンザ定点医療機関からの報告を基に推計した全国の医療機関を受診した患者数は、23-29日は約189万人で、前週より16万人増えた。しかし、5-9歳は2万人減、10-14歳は1万人減、15-19歳は前週と変わらず、5-19歳の合計は3万人減の118万人でした。その他の年代ではいずれも増えており、0-4歳が4万人増え24万人、20歳代が6万人増え18万人、30歳代が5万人増え15万人となっており、他の年代に流行が広がっています。
2009. 12. 05
新型インフルエンザについて「流行の中心が小中学生から成人など、ほかの年代にどう広がるかが見えず、今後の患者数の伸びは予測できない」との見方を、厚生労働省が示しました。
国立感染症研究所のまとめでは、11月29日までの1週間に医療機関を受診したインフルエンザの推計患者数は約189万人で3週連続の増加。その大半は新型インフルエンザとみられます。
厚労省によると、年齢別では0~4歳が24万人で前週の20万人から大幅に増える一方、5~9歳は55万人から53万人に、10~14歳は42万人から41万人にそれぞれ減少。20代以上では1~6万人の増加が見られた。
都道府県別では、これまで患者数が多かった北海道が目立って減少。関東地方の多くの都県や愛知県などでも減少か横ばいとなっています。
引続きの、手洗いうがいなどの感染対策をお願いします。
2009. 12. 04
日本でロタウイルス向けワクチンの承認申請の動きです。
英系製薬会社グラクソ・スミスクラインは11月30日、幼児の胃腸炎を引き起こすロタウイルス向けワクチン「ロタリックス」の承認を申請したと発表した。実用化されれば同ウイルス向けでは日本初のワクチンとなる。承認が得られれば、ベルギーの工場で製造して日本に輸入する。
ロタリックスは弱毒化したヒトロタウイルスの経口型ワクチン。ロタウイルス感染による胃腸炎を予防する。乳幼児を対象に凍結乾燥製剤や液剤(日本では液剤の承認を申請)として世界116カ国で承認を得ています。
2009. 12. 03
「麻しん(はしか)風しんの予防接種(第3期、第4期)」について。
平成20年度から5年間、中学1年生と高校3年生に相当する年齢の方が、麻しん風しん(第3期、第4期)の予防接種の対象となっています。
広島市では毎年、その年の麻しん風しん第3・4期の対象者に予防接種票を送付しており、今年度末の平成22年3月31日までは、接種にかかる費用は無料となります。ただし、平成22年4月1日以降に予防接種をうける場合は、予防接種の費用が全額個人負担となります。また、予防接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合の補償についても、予防接種法に基づく補償が受けられなくなります。
まだ接種を受けていない方は、健康状態の良い時に、予防接種を受けるようお願いします。
まだ予防接種を受けていない方で、予防接種票をお持ちでない方は、お住まいの区の保健センター(南区の方は南保健センター:082-250-4108・保健予防係)にお問い合わせください。
2009. 12. 02
広島県の新型インフルエンザワクチン接種についての最新情報です。
12月7日から、前回からの接種対象者である「妊婦」、「基礎疾患を有する方(最優先)」に加え、新たに「基礎疾患を有する方(その他)」、「幼児(1歳~就学前)」、「小学校1~3年生の方(予定の前倒し)」が接種開始となります。
ただし今回は、基礎疾患を有する方(最優先)のうち小学校4年生以上の方、基礎疾患を有する方(その他)、幼児(1歳~就学前)、小学校1~3年生の方のワクチンは、医療機関からの接種希望数に対して約20%しか配分されません。接種希望者に対して、ワクチンが不足しており、お待ちいただく状況にあります。
1歳未満の小児の保護者、小学校4~6年生は12月21日からの接種になりそうですが、詳細はまだ未定です。
以上が最新情報です。ワクチンが不足しており、ご希望に添えない状況になっておりますが、ご理解とご協力を宜しくお願いします。
2009. 12. 01
「若年インフルエンザ患者の異常行動」についての報告です。
飛び降りなどインフルエンザ患者による異常行動が、9月下旬から11月中旬までに全国から151件報告されたことが、厚生労働省研究班のまとめで11月30日に分かった。患者は1~17歳で、ほとんどが新型インフルエンザとみられる。異常はタミフルなどの治療薬服用の有無にかかわらず、8割近くが発熱から2日以内に発生していた。
異常行動の内容は、飛び降り、突然走りだす、うわ言など、例年の季節性インフルと同様です。厚労省は、新型インフルエンザの流行が10代以下の若年層に集中していることや、新型患者に対する関心の高まりで報告数が増加していると分析。「薬の服用にかかわらず、発熱から少なくとも2日間は患者から目を離さないように」お願いします。
2009. 11. 30
本日は先週紹介した「成人用肺炎球菌ワクチン」に続き、今年10月、「小児向けの肺炎球菌ワクチン」が承認された話題を紹介します。このワクチンですが、来春には発売される見込みです。
小児向けの7価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV7)「プレベナー」の接種により、肺炎球菌感染症、特に、細菌性髄膜炎や菌血症の予防が期待されますが、世界ではすでに、40の国や地域で定期接種されています。
「プレベナー」の接種は、生後2~7カ月未満の乳幼児では初回免疫として3回、追加免疫として12~15カ月の間に1回接種する、というスケジュールです。
国内での販売価格はまだ未定ですが、任意接種での導入となるため、1回につき1万円前後の自己負担となる可能性が高く、接種費用が課題となりそうです。
「肺炎球菌ワクチン」について、院内広報誌「じゅんくり」第6号(12月号)で特集しましたので、ご参照下さい。
2009. 11. 28
最近、お問い合わせの多い「成人用肺炎球菌ワクチン」について、認められていなかった再接種が可能となったことを紹介します。
厚生労働省は、肺炎の重症化を予防する肺炎球菌ワクチンについて、1回目の接種から5年程度経ていれば再接種を認めることを決め、今年10月より改定を行った。
新型インフルエンザに感染した65歳以上の高齢者が重篤な肺炎を併発することを防ぐ効果も期待されます。
同ワクチンの効果は5年以上たつと低下するが、従来は再接種すると強い副作用が出るとして、接種は一生に1度とされていた。海外などで4年以上の間隔を置けば、再接種は問題ないとの報告が出され、現在では欧米の多くの国で再接種が認められている。日本でもようやく再接種が可能となりました。
肺炎球菌ワクチンは当院でも接種可能です。ご質問などございましたらお問い合わせ下さい。
2009. 11. 27
「成人7割が運動不足感じる」内閣府調査の調査を紹介します。
成人の4人に3人は日ごろ運動不足を感じていることが、内閣府が21日に結果を発表した「体力・スポーツに関する世論調査」で分かった。
ただ、頻繁に運動する人はむしろ増えており、内閣府では「健康への意識が高まり、結果的に運動不足を感じるようになっているのではないか」と見ている。
調査は9月24日~10月4日に、全国の20歳以上の男女3000人を対象に面接方式で実施した。1925人が回答し、回収率は64・2%だった。
運動不足を感じると答えた人は「大いに」と「ある程度」をあわせて73・9%で、2006年の前回調査から6・3ポイント増え、同様の質問を始めた1991年以降で最も多くなった。年代別では40歳代が最も割合が高く、86・6%に達した。
この1年間に何らかの運動やスポーツをした人は全体の77・7%で、これらの人に運動の頻度を聞くと、「週3日以上」が30・2%で最も多かった。前回より1・1ポイント増え、17・1%だった88年の2倍近い割合となった。「週1~2日」が28・1%、「月に1~3日」が23・4%で、半数以上の人は週に1回以上の頻度だった。
種目(複数回答)はウオーキング(48・2%)がトップで、体操(26・2%)、ボウリング(15・7%)が続いた。
2009. 11. 26
今年7月以降にインフルエンザに感染した推計患者数(902万人)の8割を、20歳未満が占めたことが国立感染症研究所のまとめでわかった。
感染研は全国の小児科と内科約5000医療機関から報告されるインフルエンザ患者数を基に、国内の推計患者数を1週間ごとに計算している。今回は、患者数が増加し始めた7月6日から11月15日までの累計数を、20歳未満は5歳ごとに、20歳以上は10歳ごとに分析した。
その結果、20歳未満が716万人で79%を占めた。最多は10~14歳で267万人、ついで5~9歳が230万人、15~19歳が144万人、0~4歳が75万人の順だった。男女比をみると、全体では男性が女性をわずかに上回る一方、30代と40代では女性が多く、子どもの看病で感染した母親が多いとみられる。
2009. 11. 25
シャボン玉石けんと広島大学が共同開発した、「新型インフルエンザ対策せっけん」が発売されることになりました。
合成添加物を含まないせっけんを製造販売している「シャボン玉石けん」(北九州市)は24日、広島大医歯薬学総合研究科の坂口剛正教授(ウイルス学)と共同で開発した、新型インフルエンザウイルスに効果がある無添加の手洗いせっけん「バブルガード」を12月に発売すると発表した。
同社によると、新型インフルのウイルスの数を千分の1以下に減少させる効果があり、無添加のため手の細胞への影響も通常のハンドソープと比べ30分の1以下という。感染性胃腸炎などを起こすノロウイルスなどへの効果も確認されている。
当初は通信販売で、来年2月から全国のスーパーやドラッグストアなどで販売する。300ミリリットル入りのボトルが1本630円、250ミリリットルの詰め替え用は441円です。
2009. 11. 24
厚生労働省の専門家検討会による「現在使用中の国内産新型インフルエンザワクチンの安全性についての評価」が行われ、「現時点では重大な懸念は示されていない」と発表された。
医療従事者約2万2000人を対象とした臨床試験では、副作用症例が423件報告された。そのうち、意識レベルの低下など6件(0・03%)が重い副作用事例だった。また、一般の医療機関からは、19日までに推定約450万人の接種者のうち、877件の副作用報告があった。うち重い副作用報告は死亡13件を含む68件(0・002%)だった。
また、ワクチン接種後の死亡例が20日までに21例報告されているが、持病の悪化が原因とみられ、死亡との関連は今のところ認められないとした。
ちなみに、昨年の季節性のワクチンでは4740万人に接種して、重い副作用報告は121件(0・0003%)だった。
一方、輸入ワクチンの安全性について、気になるニュースが入ってきました。英大手製薬会社「グラクソ・スミスクライン」(GSK)がカナダで製造している新型インフルエンザのワクチンの一部について、接種後にアレルギー反応が強く出るなど、想定以上の副作用が複数報告され、同社がカナダの複数の州政府に使用中止を要請していることがわかった。日本政府は同社が同じ工場で作った製品を早ければ12月下旬にも輸入する予定だったが、状況によっては、GSK社からは輸入がストップする可能性もある。
輸入ワクチンは、1月以降、主に高齢者に使われる見込み。国はGSK社とノバルティス社の欧州2社と契約し、計4950万人分(2回接種)を輸入する予定だが、このうち3700万人分がGSK社製です。因果関係は不明だが、今回の同社ワクチンは免疫補助剤が入り、筋肉に打つなど、国内産と違う製造方法や打ち方がされている。
今後の日本政府の対応が注目されます。
2009. 11. 21
新型インフルエンザワクチンの重篤な副反応についての研究結果です。
厚生労働省は11月20日、新型インフルエンザワクチンの重篤な副反応が2万人中6例だったとする研究結果を発表した。国立病院機構の67施設で実施されたもので、重篤例は動悸や嘔吐、意識レベルの低下などだが、後遺障害に至るものはなかった。
新型インフルエンザの国産ワクチン接種を最優先で受けた医療従事者約2万2千人を対象に国立病院機構が実施した安全性調査で、接種後14日目までに認められた副反応を取りまとめた。
それによると、副反応の報告基準に該当する有害事例は90例で、このうち入院に相当する重篤例は6例だった。重篤例の内訳は、「吐き気・嘔吐」が2例、「動悸」「両下肢筋肉痛」「発熱・意識レベルの低下・嘔吐」「末梢性めまい」が各1例。重篤例以外は、「39度以上の発熱」39例、「じんましん」28例などだった。
局所反応は、2cm以上の発赤が53.7%、2cm以上の腫脹が31.0%、痛み止めを用いる程度の疼痛が3.4%に見られた。発赤、腫脹の96%が接種当日か翌日に始まり、73%は4日以内に消失した。
全身反応は、倦怠感19.0%、頭痛14.1%、鼻水10.4%、37.5度以上の発熱3.1%などだった。発熱の34%は接種当日か翌日だった。
厚労省は、このデータなどを基に11月21日に副反応に関する検討委員会を開き、接種の安全性などについて評価する予定です。
2009. 11. 20
メタボ診断の1項目である腹囲(ウエストサイズ)の基準値が変わるかも知れません。
肥満症やメタボリック症候群の診断基準の1項目、腹囲(ウエストサイズ)について「男性85センチ以上、女性90センチ以上」という現在の基準値が妥当かどうか、日本肥満学会が専門委員会を設置し本格的な検討に入っていることが18日、分かった。大規模なデータ解析などを進めており、来年をめどに結果を公表する。専門家の間にはさまざまな意見があるという。
腹囲は、生活習慣病の原因となる内臓脂肪の蓄積量の目安とされるが、日本の基準値は海外に比べて、男性はかなり厳しい一方、女性の基準値が男性より緩いのは珍しく、異論も出ていた。昨年から腹囲測定は特定健診(いわゆるメタボ健診)にも取り入れられており、基準値が変更されれば保健指導にも影響を与えそうだ。
現在の基準値は、肥満学会が肥満症の診断基準として2000年に策定。関係学会が合同で05年に作ったメタボリック症候群の診断基準にも盛り込まれ、厚生労働省は学会の定めた基準値をメタボ健診に採用した。
だが策定の基になったデータは、著しい肥満を含む肥満者が中心で、女性の数が少ないなどの問題があったという。
ちなみに、米国では男性102センチ以上、女性88センチ以上であり、国や地域により腹囲の基準値は様々です。
2009. 11. 19
新型インフルエンザの流行で売り上げを伸ばしているマスクで、15商品のうち少なくとも11商品が「ウイルスカット99%」「N95規格クリア」などと過大な表現で販売されていることが18日、国民生活センターの調査で分かった。
マスクを販売する際の公的な表示基準はないが、消費者庁は同日、科学的根拠が薄く消費者が誤解する恐れがあるとして、業界団体「日本衛生材料工業連合会」を所管する厚生労働省に対応を取るよう通知、景品表示法に基づき業者に行政指導することを決めた。
国民生活センターによると、15商品のうち、ウイルスの捕集効率95%以上は3商品だけだった。6商品は80~95%、2商品が60~80%で、50%以下も4商品あった。
13商品が、捕集効率が「99%」や95%以上の医療用「N95規格」を満たすなどと、パッケージやインターネット上で数値を示して販売。表示を満たしているのは2商品だった。
2009. 11. 18
「新型インフルエンザワクチン接種、小学校高学年は年内に日程繰り上げの方針」
新型インフルエンザの国内産ワクチンについて、厚生労働省は17日、優先接種対象者(5400万人)の新たな予防接種スケジュールの目安を公表した。妊婦や高齢者も含む成人の接種回数を原則2回から1回に変更したのを受けた変更だ。
今回のスケジュールで、小学校高学年(4~6年)の接種開始時期を従来の来年1月後半から今年12月下旬に繰り上げた。ほかに、1歳未満の小児らの保護者を1月前半から12月下旬に、中学生を1月後半から同月前半に、それぞれ早めた。この対象は合計で約900万人になる。
また、従来は輸入ワクチンを使う予定だった高校生と高齢者の一部にも国内産ワクチンを打つことにした。
ただ、詳細な接種時期は都道府県ごとに決めるため、広島県の対応に注目したい。
2009. 11. 17
本日は、「楽天家の男性は脳卒中リスク低め」という厚生労働省研究班が実施した追跡調査結果を紹介します。厚生労働省研究班が実施した約9万人規模の調査で「楽天的な男性ほど脳卒中や狭心症、心筋梗塞(こうそく)などを起こすリスクや死亡率が低い」という結果が明らかになった。ストレスやいらいらが健康に影響を与えるといった報告はあるが、こうした前向きな意識との関係についての研究は少ないという。
琉球大の白井こころ准教授と大阪大の磯博康教授が岩手、秋田、長野、沖縄など8県に住む40~69歳の男女8万8175人を調べた。「自身の生活を楽しんでいるか」というアンケートを実施し、意識の高さを「高・中・低」の3グループに分け、約12年間にわたり循環器病との関係について調べた。期間中に循環器病を発症したのは3523人で、うち脳卒中が2786人、狭心症と心筋梗塞が686人だった。
男性で楽しんでいる意識が「低い」グループは、「高い」グループに比べ、脳卒中の発症リスクが1.28倍、狭心症や心筋梗塞の発症は1.22倍と高くなった。死亡者1860人に関しても、脳卒中のリスクが1.75倍、狭心症や心筋梗塞が1.91倍だった。女性は関連がみられなかった。
楽しんでいる意識が高いグループでは、週1回以上の運動習慣がある人が多く、喫煙者も少なく、健康的な生活をしている傾向が強いことが関係していると考えられる。
2009. 11. 16
新型インフルエンザ用ワクチンを2回接種するよりも、1人1回で2倍の人口に接種した方が流行を抑えられることが、科学技術振興機構(JST)と神戸大の試算で分かった。欧州の感染症対策専門誌「ユーロサーベイランス」(電子版)に12日掲載された。
1回接種に2回接種の4割以上の効き目があれば、1回接種で対象人数を増やした方が地域の発症者を減らせるという結果が出た。
新型ワクチンを多くの人が早めに接種できるような対応が望まれます。
2009. 11. 14
「新型インフルエンザワクチン接種、19歳も原則1回」
新型インフルエンザワクチンの接種について、厚生労働省は12日、健康な19歳の接種回数を1回にすると発表した。国内の臨床試験の結果や海外の情報などから、成人と同じ扱いで構わないと判断した。高校卒業後でまだ18歳の健康な人も1回にするという。
厚労省は11日、20歳以上の接種回数を原則1回とし、中高生は12月中旬に出る別の臨床試験の結果をみて判断すると発表した。ところが、どちらにも属さない19歳などについては決めていなかった。このため長妻昭厚労相も記者会見で答えられず、急きょ検討した結果、接種回数を1回にすることとなった。
2009. 11. 13
新型インフルエンザに関して、「インフルエンザに罹りましたが、新型ワクチンの接種は必要ですか?」という質問を多く受けます。
一般的に、新型インフルエンザに感染して発症した方は、免疫を持っていると考えられるため、新型の予防接種をする必要はないと考えられます。
そこで、罹ったインフルエンザが新型かどうかが問題になるのですが、厳密に言うと、確実に新型インフルエンザに感染したと言えるのは、PCR検査やウイルス分離等で新型インフルエンザウイルスあるいはその遺伝子が検出された方のみであり、この検査は一般的には行われていないため、新型かどうかわからないというのが答えになります。しかし、厚生労働省が行っているサーベイランスによると、現在国民が罹患しているインフルエンザの大部分は新型インフルエンザによるものであり、このため、平成21年の夏以降、現在までにA型インフルエンザと診断された方については、新型インフルエンザに感染した可能性が高いと考えられ、新型インフルワクチンを接種する必要はないと考えられます。もちろん、厳密には新型かどうか証明されていませんので、希望すれば新型ワクチンを接種することは可能です。
ただし、上記は、あくまでも季節性インフルエンザのほとんどない時期に通じる考え方です。これからは季節性インフルエンザもみられる時期になりますので、インフルエンザに罹ったからといって必ずしも新型とは限らなくなります。
2009. 11. 12
「新型インフルワクチン接種回数」に関する最新情報です。
厚生労働省は11日、新型インフルエンザワクチンの接種回数について、これまで1回接種としていた「健康な成人」だけでなく、「妊婦」や「基礎疾患を有する人」、「高齢者」を含め、成人は原則1回接種にすると発表した。中高生については、12月中に判明する1回接種の臨床試験の結果を踏まえて判断する。これまで厚労省が提示していた接種人数やスケジュールは、妊婦などの2回接種が前提で、今回の見直しを受けての新しいスケジュールなどは、週明けにも示すという。
政府は来春までに2回接種を前提に、7700万人分のワクチンを確保する方針で、このうち国内産は2700万人分。1回接種の対象者が広がれば、ワクチンが節約できて、小児などの接種時期の前倒しもしやすくなる。
接種回数についてまとめると、「妊婦」や「基礎疾患を有する人」、「高齢者」を含め、成人は原則1回接種。「13歳未満の子ども」は2回接種とし、「持病のある人のうち抗がん剤治療を受けているなど免疫機能が極端に低下している患者」については医師の判断で2回も可能とした。また、「中学、高校生」は当面2回を前提とし、12月中に臨床試験結果がまとまるのを待って1回で済むかどうか判断する。
2009. 11. 11
喫煙率の調査で、「男性の喫煙率が調査開始以降で過去最低」となりました。
厚生労働省が9日に公表した08年の国民健康・栄養調査で、喫煙率が21.8%で5年前の03年から5.9ポイント減っており、長期的にみた喫煙人口の減少がはっきりした。男女別では、男性の喫煙率が10.0ポイント減の36.8%と調査開始の86年以降で、過去最低になったことが明らかになった。女性は9.1%で01年以来7年ぶりに10%を下回った。厚労省生は「健康への悪影響などの知識が深まり、たばこに対する意識が変化している」と分析している。
調査は全国約8149人の男女が対象。86年当時の喫煙率は男性は59.7%、女性は8.6%だった。
5年前の03年と比較すると、男性は46.8%から10ポイントの大幅な減少。女性は11.3%から2.2ポイント減った。世代別で最も減少幅が大きかったのは男性の20歳代で、55.8%が41.2%に下がっていた。その他、男性の30歳代、50歳代、70歳以上での減少が目立った。
一方、禁煙を試みたことがある人の割合は男性52・1%、女性57・0%だったが、「たばこをやめたい」と考えている人は、男性で28・5%、女性で37・4%にとどまった。
2009. 11. 10
「新型インフル低年齢で増加傾向」
国立感染症研究所が全国の定点医療機関から報告されるインフルエンザ患者の年齢を分析したところ、9歳以下が増加していることが9日分かった。患者の大半は新型とみられる。
感染研によると、夏休みが終わった後は、5~19歳の患者の割合が増加して流行の中心になり、その中でも10代前半の患者割合が最も多かった。
しかし、最近になって10代の割合が低下し、9歳以下が増加。今月1日までの1週間でみると、5~9歳が36・7%を占め、前週まで最も多かった10~14歳と入れ替わった。
重症化や脳炎を防ぐためにも、疑わしい症状がみられた場合は、早目の受診をお願いします。
2009. 11. 09
タバコ税の増税も検討されている「たばこ」ですが、本日は、「がんと喫煙の関係について」少しお話をしましょう。がん発症の要因となる喫煙ですが、肺がんだけでなく口腔(こうくう)や咽頭、食道、胃、膵臓(すいぞう)、肝臓などさまざまながんで、発がん性が認められています。日本人の非喫煙者に対する喫煙者のがん死亡のリスクは男性が2倍、女性で1.6倍程度です。日本人のがん死亡の約20~27%は喫煙が原因といわれています。また、たばこを吸わない人も要注意です。厚生労働省の調査では、非喫煙女性でも夫からの受動喫煙がある場合、肺がんのリスクは受動喫煙がない場合と比べ、1.3倍に高まります。喫煙歴が長いと手遅れと考えがちです。確かに何十年もたばこを吸えば、禁煙後肺がきれいになるのに10~20年かかるけれど、やめないで吸い続けるのと比べればリスクは確実に下がるため、禁煙は重要です。
2009. 11. 07
子どもの新型インフルエンザの予防接種の日程が前倒しになる可能性が出てきました。
厚生労働省は6日、新型インフルエンザのワクチンについて、健康な小児への接種時期を前倒しするよう検討を求める通知を都道府県あてに出した、と発表した。1~6歳の幼児や小学1~3年の児童に対して、「12月前半」や「12月中旬から」としていた接種開始を「11月中旬から」に早めるよう求めた。
また、12月前半を予定していた基礎疾患(持病)のある9~15歳の子どもの接種も、同様に11月中旬への前倒しの検討を求めた。
足立信也政務官が同日夜、記者会見で明らかにした。前倒しを求める理由について、14歳以下の重症患者の発生率が他の世代より高い点や、6日に3回目のワクチン出荷が始まったことをあげた。
ただ、持病のある人や妊婦らの接種回数は「当面2回」とされ、1回か2回かの正式決定は臨床試験の結果が出る11月中旬~12月下旬の見込み。仮に接種が1回になれば、ワクチンの量に余裕も出てくるが、そうしたことがないまま都道府県が小児への前倒しを決められるかは不透明だ。足立政務官は「ワクチンの流通・在庫状況を把握した上で可能であれば対応をお願いしたい」と求めた。
今後の動きに注目です。
2009. 11. 06
広島県全域にインフルエンザ警報
広島県は4日、新型インフルエンザの本格的な流行を受け、県内全域にインフルエンザ警報を発令した。制度を始めた1999年以降、時期は最も早い。県は「流行は拡大傾向にある」と予防策の徹底を呼び掛けている。
県や広島市など保健所設置市の定点観測で、10月26日~11月1日の1週間、1医療機関当たりのインフルエンザ患者数が、県西部東保健所(東広島市、竹原市、大崎上島町)管内で48・40人、広島市保健所管内で34・64人となり、警報発令基準の30人を超えた。
県内7保健所管内の平均は24・93人。前週(10月19~25日)の15・63人から1・6倍に増えた。呉市9・15人▽福山市11・44人▽県西部26・50人▽県東部13・67人▽県北部26・17人だった。
県健康福祉総務課によると、インフルエンザ警報はこれまで1月上旬から2月にかけて発令。例年、1~3週間後に流行のピークを迎えるという。
そこで、大切になってくるのがインフルエンザの予防対策です。日常生活ではまず、体調を整えて抵抗力をつけ、ウイルスに接触しないことが大切です。手洗い、うがいも重要で、手洗いは接触による感染を、うがいはのどの乾燥を防ぎます。また、インフルエンザウイルスは湿度に非常に弱いので、室内を加湿器などを使って適度な湿度に保つことは有効な予防方法です。
これからは、新型インフルエンザに加え、季節性インフルエンザのシーズンも始まります。ワクチン接種など予防対策をお願いします。
2009. 11. 05
「高齢者も新型インフルエンザワクチン1回接種で十分な免疫が得られた」というベルギーで実施したワクチンの臨床試験の結果が発表されました。
日本が輸入する新型インフルエンザワクチンの製造元、英国のグラクソ・スミスクライン(GSK)社は4日、ベルギーで実施したワクチンの臨床試験で、18~60歳だけでなく高齢者も1回の接種で強い免疫応答が得られたと発表した。
臨床試験は18~85歳の240人が対象。1回目の接種から3週間後の2回目接種前の時点で、18~60歳のほとんどは免疫が期待できる抗体価の上昇が確認され、高齢者も61~70歳は88%、71歳以上は87%で上昇していた。
厚生労働省はGSKから3700万人分購入する契約を結んでおり、国内販売の承認後、65歳以上の高齢者と高校生に使われる見通し。臨床試験に使われたワクチンと日本が輸入するものは、製造工程の一部が異なるが、ウイルスの培養方法や免疫増強剤が入っている点は同じ。
この臨床試験の結果が、日本でのワクチン接種回数の決定に影響を与えるかもしれません。
2009. 11. 04
「健康な成人と同様、妊婦も新型インフルエンザワクチン1回接種で十分な免疫が得られた」という米国での治験結果が発表されました。
米国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)は2日、妊婦に対する新型インフルエンザワクチンの初期の臨床試験(治験)結果を発表した。「健康な成人と同様、1回接種で十分な免疫が得られた」としている。
治験は、仏サノフィ・パスツール製のワクチンを使い、18~39歳で、妊娠14~34週の女性50人の協力で行われた。25人ずつ、1回分接種のグループと2回分接種のグループに分けて接種から21日後に血液を調べた結果、それぞれ92%、96%の女性で十分な免疫が得られており、1回接種でも十分な免疫が得られた。
厚生労働省は、13歳未満の接種回数は2回と決定しているが、13歳以上の持病のある人と妊婦の接種回数は当面2回が前提だが、今後の臨床研究結果などを踏まえて1回でよいかどうか最終判断するとしています。 この米国での治験結果が接種回数に影響を与えるかもしれません。
2009. 11. 02
本日は「飼い犬25%が日本脳炎に感染」という調査結果の紹介です。
全国の飼い犬の4匹に1匹が日本脳炎に感染しているとの調査結果を、山口大の前田健教授らがまとめた。豚から人や犬にウイルスを広げる蚊が、養豚場周辺から市街地まで飛んでいるためのようだ。犬から人には感染しないが、媒介する蚊が身の回りにいて、人への感染拡大の危険性を示すものとして、専門家は注意を呼びかけている。
西日本に多い日本脳炎は体内でウイルスが増える豚の血を吸った蚊を介して、人などに感染する。犬や人からは蚊を介しても人に感染しない。感染者の発病率は1%以下だが、重症化すると高熱、意識障害を起こす。脳症になると2~4割が死亡する。感染した犬が発症した例は報告されていない。
前田教授(獣医微生物学)らは06~07年に47都道府県の動物病院にかかった犬652匹の血液をとり、日本脳炎ウイルスの抗体ができているか調べた。その結果、25%に抗体があり、感染していた。
地域別では、四国が61%で最も多く、次いで九州が47%だった。ほかは中国26%、近畿23%、関東17%。市街地で24%、住宅地で21%の犬が感染、室外犬は45%、室内犬も8%が感染していた。
ウイルスを運ぶコガタアカイエカは30キロ移動するため、豚の血を吸った蚊が都市部まで飛んでいるようだ。
ワクチンの集団接種により60年代に感染者は激減し、最近の感染者は年間数人しかいない。ワクチンの副反応による重症者が出たことで、05年に厚労省は接種を積極的に勧めることをやめ、現在は受けていない子供も多い。
感染で重症化すれば、効く抗ウイルス薬がないため、解熱剤で熱を抑え、炎症を抑える薬を使う。ワクチンは今年から、副反応が出にくいとされる新しいタイプも使えるようになている。
今後、ワクチンを打っていない子どもを中心に日本脳炎の感染が広まる可能性もあり、注意が必要です。
2009. 10. 31
「新型インフルエンザが全国で本格的な流行状態となりました。」
新型インフルエンザについて、厚生労働省は30日、全国で本格的な流行状態となったと発表した。累計患者の7割超が14歳以下だったことも判明した。季節性インフルより子どもが重症になりがちで、日本小児科学会(会長=横田俊平横浜市立大教授)は、健康な子どもに早くワクチン接種するよう求める要望書を厚労省に出した。
国立感染症研究所によると、定点医療機関(5千カ所)で1医療機関あたりのインフル患者数は24.62人(前週17.65人)になった。ほとんどが新型と見られ、来週の集計では30人の「警報レベル」を超えそうな勢いだ。
7月6日~10月18日の患者累計でも、73%は14歳以下。なかでも、5~14歳で6割を占め、学校などで感染していると見られる。季節性も学校から広がる傾向があり、従来は3学期が始まる1月以降、一気に患者が増える。今季は、夏休み明けの2学期に「前倒し」となった形だ。同省は「明らかに全国規模の本格的な流行。今後も患者は増える」とみている。
厚労省の計画では、子どものワクチン接種は12月からだが、こうした状況から、前倒しすべきだという声が専門家から強まっている。日本小児科学会は重症児の3分の2は持病がないことから対策強化を求めている。日本産科婦人科学会内には「妊婦は予想外に重症例が少ない。むしろ小児の接種を優先した方がいい」という意見もある。
日本政府は現時点では医療従事者以外は「2回接種」としているが、東京大医科学研究所の河岡義裕教授は「小児の接種が早められるかどうかは、(11月に始まる妊婦や持病のある成人が)1回接種でよいかどうか、ということとも密接に関係する」と指摘しており、政府の方針が注目されます。
2009. 10. 30
「新型インフルワクチン、子どもの臨床試験実施」という動きです。
新型インフルエンザワクチンを子どもに接種し効果を確かめる臨床試験が30日から実施される。インフルエンザワクチンをめぐっては、現行の乳幼児への接種用量では効果が低いとの指摘があるため、厚生労働省は試験結果を受けて将来的に用量の見直しも検討する。
臨床試験は、独立行政法人国立病院機構の全国8医療機関で、国内ワクチンメーカー4社が製造した新型と季節性のワクチンを使って行われます。
対象は6カ月以上13歳未満の男女360人。新型のみを接種する人、両方を接種する人などにグループ分けし、それぞれについて世界保健機関(WHO)が推奨している用量で、免疫の指標である抗体価が十分に上昇するかどうかを確認する。
国内では従来、季節性インフルエンザワクチンを6歳から13歳未満は0・3ミリリットル、1歳から6歳未満は0・2ミリリットル、1歳未満は0・1ミリリットルをそれぞれ2回接種している。新型ワクチンについても接種の対象外である1歳未満を除き、季節性と同じ用量、回数を接種することになっています。
しかし、現行の用量では乳幼児に対する効果が低いとの指摘や、用量を増やせば効果が上がるとの研究結果もあり、適切な用量を見極める必要性が出てきたため、臨床試験を行う運びとなった。
2009. 10. 29
最近、「妊娠していますが、インフルエンザの予防接種を受けてもよいですか?」という問い合わせが多くみられますので、妊婦とインフルエンザ予防接種についてお話します。
日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会が作った「産婦人科診療ガイドライン産科編2008」(日本産科婦人科学会発行)には、妊婦がインフルエンザワクチンの接種を希望する場合は接種してよいという公式見解が、明記されています。
また、国立成育医療センター(東京)で行われた妊娠15~39週の女性125人(25~41歳)を対象に実施された研究で、妊娠中に季節性インフルエンザワクチンを接種した女性には、感染や重症化予防に必要な抗体が90%の確率で生成され、胎児にも十分な免疫力が備わることが発表されています。
実際、厚生労働省も、季節性と新型のインフルエンザワクチンについて「妊婦へは原則接種しない」としていた添付文書の「接種上の注意」の記載を削除することを決めました。新型ワクチンの一般国民への接種が11月から始まるのを前に、安全性を改めて評価し、妊婦特有のリスクはないと判断した結果です。
インフルエンザは妊婦がかかると重症化しやすいとされており、赤ちゃんの器官ができあがった13~16週以降の方なら、妊娠中のワクチン接種もインフルエンザ予防対策の選択肢のひとつになると考えます。念のため、産婦人科の先生に、予防接種を受けてもよいか確認しておくとよいでしょう。
2009. 10. 28
「新型インフルエンザのインフルエンザ脳症について」
新型インフルエンザに感染し、インフルエンザ脳症を発症した患者が7月からの3か月間に計50人に上ったことが、国立感染症研究所の調査でわかった。最も多かった年齢は7歳。5歳以下に多い季節性インフルエンザに比べて年齢が高く、感染研は注意を促している。
インフルエンザ脳症の原因は、ウイルスに対する免疫反応がが激しすぎて、免疫成分が血管外にもれて脳細胞が傷害されて脳が腫れることで起きます。ほとんどは発熱1日以内に起こっていて、けいれん、意識障害、幻覚、意味不明の発語や異常行動で発症しています。残念ながら確実な脳症の予防法がなく、重要なのは、脳症が起こったら早期受診して、早期に治療を開始することです。また、インフルエンザの発熱に対して、アセトアミノフェン(アンヒバ、カロナールなど)以外の解熱剤は、脳症を誘発し易いので使用しないようにお願いします。
2009. 10. 27
「新型インフルエンザの大学入試に関する対応について」のニュースです。
国立大学協会は26日、新型インフルエンザにかかり来年度の入学試験で2次試験を受験できなかった受験生について、本試験の1週間後の追試験や大学入試センター試験を参考にした合否判定など、各大学が救済策をとることで合意した。
文部科学省によると、国立大学2次試験の追試などの救済策は、平成7年の阪神大震災や、20年の大雪の際にも一部大学で実施したが、全国のほぼすべての国立大が足並みをそろえて実施するのは初めて。
大学入試の新型インフルエンザ対策をめぐっては、大学入試センターがセンター試験の追試の日程を1週間ずらし、1月30、31日に変更するなどの特例措置を決めている。
国大協によると、この救済策は22年度入試に限った特例措置で、追試験を受ける場合は、本試験1週間前から当日までに、追試験受験申請書や診断書を提出させる。
2009. 10. 26
本日は、「血圧が高いと物忘れしやすい傾向あり」というお話です。血圧が高い中高年は、脳に何らかの損傷を受けて物忘れしやすい傾向にあることが米アラバマ大バーミングハム校の研究でわかった。高血圧は脳卒中や心臓病などの危険を増すことが知られているが、認知症予備群も生み出していることになる。研究チームは、脳卒中を起こしたことがない45歳以上の米国人約2万人の血圧データと、「今日は何日ですか?」といった認知機能テストの結果を分析。高血圧は「最高血圧140mmHg以上か最低血圧90mmHg以上、あるいは高血圧の薬を服用している」と定義されるが、最低血圧が10mmHg上がるたびに、認知機能に障害が出る危険が7%ずつ上がることがわかった。 過去の実験研究では、最低血圧が高いと脳の細動脈が弱くなって神経細胞が損傷を受けることがわかっている。チームは「高血圧を治療することで、認知機能障害を防げる可能性がある」としている。 今回の研究では、最高血圧と認知機能の間には関連は見られなかった。 高齢者には高血圧と認知症が多くみられることから、関連があると考えられてきたが、これまで明確な結論は出ていなかった。
2009. 10. 24
「小中学生が流行の中心」新型インフルエンザ流行についてです。
18日までの1週間に新型インフルエンザとみられる症状で新たに医療機関を受診した患者が推計で約83万人(前週約64万人)に上ったことについて、厚生労働省は23日、「小中学生から20歳までが流行の中心」との見方を示した。
同省によると、83万人のうち0~4歳は7万人、5~9歳は21万人、10~14歳は28万人、15~19歳は12万人、20~29歳は6万人、30~39歳は4万人、40~49歳は3万人、50~59歳は1万人。
中でも5~9歳は前週の16万人、10~14歳は23万人からそれぞれ大きく増えた。入院も小中学生が突出しているという。
都道府県別では、北海道が昨シーズンの季節性インフルエンザによるピーク時の1定点医療機関当たり報告数を既に超えたほか、全国的に増加が進んでおり、広島県全域にもインフルエンザ注意報がでています。
2009. 10. 23
本日は、「睡眠時無呼吸症候群」についての京大の調査結果を紹介します。男性サラリーマンの5人に1人が治療が必要な睡眠時無呼吸症候群だったことが、京都大学の陳和夫教授(呼吸管理睡眠制御学)らの調査でわかった。中でもメタボリック症候群の人ほどより重症な睡眠時無呼吸症候群だった。25日、大阪市で開かれる日本睡眠学会で発表する。
研究チームは、関西の企業に勤める事務職の男性275人(平均年齢44歳)を対象に、体重や腹囲、血圧、睡眠時に呼吸がとまる回数などを調べた。その結果、58人が無呼吸、もしくは低呼吸が1時間あたり15回以上で、米学会の基準で治療が必要とされる睡眠時無呼吸症候群と判定された。このうち23人が、国の基準でメタボリック症候群に分類された。
メタボリック症候群の17%が、無呼吸と低呼吸が合わせて30回以上の重症患者で、メタボリック症候群でない人(3%)より、かなり高率だった。軽症と中等症の患者の割合は、メタボリック症候群とそうでない人で、大きな違いがなかった。
メタボリック症候群の人に重症患者が多いことについて、陳教授らは、内臓脂肪が腹部にたまることで呼吸が浅くなり、睡眠時無呼吸の症状を悪化させているのではないかとみている。
睡眠時無呼吸症候群の人は狭心症や心筋梗塞(こうそく)などの循環器疾患や、脳梗塞などの脳血管障害を起こしやすいことが指摘されており、適切な治療を受ける必要があります。
当院でも睡眠時無呼吸症候群の検査治療を行っています。お気軽にお問い合わせ下さい。
2009. 10. 22
「広島県全域にインフルエンザ注意報」
広島市は21日、インフルエンザの流行が注意報レベルを超えた、と発表した。市内36カ所の定点医療機関を12~18日に受診したインフルエンザ患者は1医療機関平均で11・17人に達し、基準の10人を超えました。
これに伴い、広島県は県内全域にインフルエンザ注意報を発令した。定点医療機関での調査を始めた1999年以降、10月の発令は初めて。県全体では平均患者数は7・60人。地域別では福山市5・11人▽北部(三次、庄原市)5・50人▽呉市5・08人などとなっています。
そこで、大切になってくるのがインフルエンザの予防対策です。日常生活ではまず、体調を整えて抵抗力をつけ、 ウイルスに接触しないことが大切です。手洗い、うがいも重要で、手洗いは接触による感染を、うがいはのどの乾燥を防ぎます。また、インフルエンザウイルスは湿度に非常に弱いので、室内を加湿器などを使って適度な湿度に保つことは有効な予防方法です。
これからは、新型インフルエンザに加え、季節性インフルエンザのシーズンも始まります。ワクチン接種など予防対策をお願いします。
2009. 10. 21
本日は、「新型インフルエンザワクチン接種回数」に関する新しい情報です。厚生労働省の足立信也政務官は20日、新型インフルエンザの国産ワクチンの接種回数について、最優先グループのうち20代から50代の健康な医療従事者は1回とし、妊婦、基礎疾患(持病)のある人、1歳未満の乳児の保護者らは当面2回接種とする方針を発表した。1歳から13歳未満の子どもについては2回接種が確定した。
医療従事者を1回にした点について、「持病のある人や妊婦に可能な限り早く接種することが望まれるため」と説明した。
妊婦や中高生は当面2回接種を前提とし、1回目に合わせて数十人規模の臨床試験を実施。12月までに出る試験結果をもとに、2回目を接種するか決める。1~13歳未満の子どもは2回接種とする。
持病のある人は1回目を接種後、11月中旬にまとまる健康な大人を対象にした別の臨床試験の2回目の接種結果を踏まえ、原則1回にするかどうか決める。1回接種という結論が出た場合であっても、医師と相談したうえで2回接種しても差し支えないと判断した。白血病など免疫力が著しく低い患者が含まれているためだ。
医療従事者の接種は今週始まった。妊婦や持病のある人は11月、幼児や小学校低学年の子は12月、1歳未満の子の保護者と小学校高学年の子、中高生は1月に、それぞれ接種が始まる予定。
厚労省の専門家による意見交換会は16日、健康な大人について「原則1回接種」との方針で合意。ところが同時に、中高生や妊婦、持病のある人についても、「原則1回」でまとまったことを足立氏が問題視。改めて開いた意見交換会では、健康な大人以外を原則1回とすることに慎重な意見が多かったため、長妻昭厚労相ら政務三役が協議し、結論を出した。
◆接種回数について現在の方針をまとめると、
・1回 :新型インフル患者の診療にあたる医療従事者
・2回 :1歳~13歳未満の子ども
・当面2回(1回に減らすかは今後判断): 妊婦、基礎疾患(持病)のある人、1歳未満の乳児らの保護者、中高生、65歳以上の高齢者
2009. 10. 20
新型インフルエンザの国産ワクチンによる副作用の発生頻度を調べるため、厚生労働省は19日、最優先で接種が始まった医療従事者を対象に安全性調査に着手した。同日と20日の2日間、国立病院機構が運営する全国67病院で医師や看護師ら計約2万2千人が接種を受け、副作用症状の報告に協力する。
今後、基礎疾患(持病)のある人や妊婦などに接種が広がるのを前に、副作用の傾向を早急に把握するのが狙い。神経障害や呼吸器障害などの重い副作用に加え、軽い発熱や接種部位の腫れなども報告を受け、季節性のワクチンとも比較。11月中旬までに結果をまとめて公表する。
調査に参加した都内の病院では19日午後、マスク姿の医師や看護師らが接種会場へ。受付で腫れの大きさを自分で測るための定規や体温計を受け取った後、次々に接種を受けた。
国立病院機構の伊藤澄信研究課長は「今のところ200人の臨床研究のデータしかないので、2万人に広げることで、一般の人がより安心して接種を受けられるようにしたい」と話した。
2009. 10. 19
すでに報道によりご存知かもしれませんが、厚生労働省の意見交換会で、「新型インフルエンザ国内産ワクチンを13歳未満の子どもを除いて原則1回接種する方針で合意」というニュースです。
これまで2回の接種が必要とされていた新型インフルエンザの国産ワクチンについて、厚生労働省の意見交換会に出席した専門家らは16日、1回で効果が出たとする臨床研究の中間報告を受け、13歳以上については妊婦、基礎疾患(持病)のある人など高リスク者も含め、基本的に1回接種とすることで合意した。
これを踏まえ厚労省が接種回数を決定するが、回数が減れば、より多くの人にワクチンが行き渡ることになり、優先対象者以外も接種を受けられる可能性が高くなった。また、19日から始まる医療従事者への接種を皮切りに、妊婦や持病のある人、1歳から小学校低学年の子どもなど最優先グループに対して順次進められる接種のスケジュールも、当初の予定より早まる可能性が出てきた。料金は2回接種の場合は6150円、1回なら3600円になります。
会議に出席した政府の新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会委員長の尾身茂自治医大教授は「今回の国産ワクチンは、健康な人では1回接種で十分な免疫反応を起こす効果が非常に強い。優先順位に入っていない人にも接種できる可能性があり、国民全体にとって朗報だ」と話した。
臨床研究は健康な成人200人が対象。通常量の0・5ミリリットルを接種した場合、1回で78・1%の人が免疫を期待できる抗体を持つなど、国際的な評価基準を満たす結果が得られた。
意見交換会では、13歳以上には何らかの基礎的な免疫があるため、1回の接種で免疫の指標である抗体価が上昇したとの見方が示された。さらに妊婦や持病のある人でも同様の効果が期待できると結論づけた。1~12歳は従来通り2回接種とし、持病のある人の中でも免疫不全など著しく免疫が低下している人は2回接種が必要とした。
現在、厚労省が示している接種開始時期の目安は、医療従事者の後、妊婦と持病のある人が11月初めから、1歳から小学校低学年の子どもが12月後半から、1歳未満の乳児の保護者らが年明けからとされていますが、接種スケジュールも変更があるかもしれません。
2009. 10. 17
本日は、以前紹介した子宮頸がんワクチンに関する最新情報で、「子宮頸がん予防ワクチンの製造販売を厚労省が承認した」というニュースです。
厚生労働省は16日、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染予防を目的としたワクチン「サーバリックス」の製造販売を承認した。そして、希望者が自己負担で受ける任意接種が12月にも始まる見通となった。
子宮頸がんの主な原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)のうち、7割を占める2種類のウイルス感染を防ぐことができると期待されている。ただ、ワクチンは3回の接種が必要で、費用は全額負担となれば、4万~6万円程度かかる見込み。
日本産科婦人科学会と日本小児科学会、日本婦人科腫瘍学会は同日、連名で見解を発表。ウイルスは性交渉で感染するため若いうちに接種するのが望ましいとして、11~14歳を中心に45歳までの女性に接種を推奨するとともに、数万円かかる接種費用への公的支援を訴えた。
子宮頸がんは、年間1万人以上が新たに発症し、約3500人が死亡しています。特に近年、20~30歳代の女性で発症者が増加しています。ワクチン接種は女性にとって朗報ですが、接種開始年齢や費用など解決すべき課題もあり、今後の動向が注目されます。
2009. 10. 16
本日は、「チョコレートなどの甘い菓子を毎日食べる子供は、成人してから暴力的になりやすい」という英国での研究結果の紹介です。
英カーディフ大学の研究者らによると、10歳の時にこうした菓子類を毎日与えられた子供は、34歳までに暴力行為で有罪となる可能性がより高かった。すぐに満足感を得られることが衝動的な行動を助長するためと考えられる。
同医学会によると、小児期の食生活が成人後の暴力性に与える影響の調査結果は初めてという。他の研究には、食品添加物と小児の過活動の関連性を解明したものがある。
研究は、2つの集団を比較する方法で、約1万7500人が今回の研究に参加した。1970年以降、数回のデータが集計され、対象者の健康状態、教育、社会的・経済的状況と甘い物の摂取について、5、10、26、30、34、42歳の各時点で追跡調査され、そのデータが解析された。
今回の研究の中心となったサイモン・ムーア氏は、電話インタビューで「子供に菓子を持続的に与えると、衝動的になり、欲しい物を攻撃的手段で入手しようとする傾向を生む可能性がある」と説明した。
2009. 10. 15
本日は、「大酒飲みの女性は乳がんリスク高くなる」という調査結果を紹介します。酒を多く飲む女性ほど乳がんになりやすい傾向にあることを、愛知県がんセンター研究所疫学・予防部の川瀬孝和主任研究員らが確かめた。閉経後の女性では、1週間に日本酒換算で7合以上飲んでいると、発症率は全く飲まない人の1.74倍だった。乳がんは女性で最も多いがんで最近急増しています。研究グループは、愛知県がんセンター病院で乳がんと診断された1754人と、乳がんと診断されなかった女性3508人を分析。全般に酒量が増えるにつれて、乳がんの発症率が高くなっていた。この傾向は50歳前後の閉経の後で著しく、閉経前の女性では、はっきりしなかった。研究結果から、乳がんを予防するには大酒を控えた方がよいと考えられます。
2009. 10. 14
本日は、「帯状疱疹患者が10年で2割ほど増加」という宮崎県皮膚科医会が2006年までの10年間に県内の病院・診療所計46施設を受診した帯状疱疹の患者計4万8388人を対象に実施した調査結果の紹介です。
子どものころに感染した水ぼうそうのウイルスが原因で起こる「帯状疱疹(ほうしん)」の患者が10年間で2割強増えていることが、皮膚科を対象にした大規模調査で分かった。50代以降で発症する患者が多く、発症率は女性の方が男性より2割以上高いことも判明した。
「帯状疱疹」とは、水ぼうそう(水痘)にかかったあと、同じウイルスがまた再発しておきる感染症です。このウイルスは、脊髄(せきずい)などの神経節にひっそりと残っていて、あるとき、また活発に活動しだすことがあります。今度は神経にそって皮膚にブツブツが出てくるため、胸や背中では「帯状」にまとまっています。また、ピリピリと痛いのも特徴です。大人にうつすことはまずありませんが、水ぼうそうにかかったことのない子供にはうつることがあり、うつされた人は水ぼうそうになるので注意が必要です。
帯状疱疹は、もとをただせば水ぼうそう(水痘)です。水ぼうそうの予防にはワクチンがあります。子どものころに受けておくと、水ぼうそうにかからないか、かかっても軽くすみます。その結果、帯状疱疹になることを防いでくれるのではないかと言われています。また、帯状疱疹になりやすい高齢者に対してこのワクチンを接種すると、水ぼうそうウイルスを抑える免疫が活発になり、帯状疱疹の罹患率が50%以下に減り、また罹患した際の重症度が劇的に低下することも分かってきました。水ぼうそうワクチンはどの年齢の方も任意接種になりますが、接種していない方は検討してみては如何でしょうか。
2009. 10. 13
本日は、「子どもの体力、10年前より向上」という文科省の調査結果を紹介します。
小学校高学年以上の10代の体力や運動能力は、99年度からの10年間で緩やかに向上していることが文部科学省の08年度体力・運動能力調査で分かった。07年度に中学生以上に現れた向上傾向が小学校高学年まで広がった。子供の体力水準が高かった1985年ごろと比較すると依然低いものの、同省は「多くの種目で向上の兆しがみられる」としている。調査は08年5~10月、全国の6~79歳の約7万人を対象に実施し、回収率は94%であった。年齢層に応じ6~8種目を測定した。
6~19歳が行った50メートル走、立ち幅とびなど8種目の合計点(80点満点)を99年度と比較すると、11歳女子は58・58点から61・37点、13歳男子は39・99点から43・00点、16歳男子は49・80点から54・04点に増加するなど小学校高学年以上は最近10年間で向上した。種目別で見ると、走る能力(50メートル走、持久走)、投げる能力(ソフトボール投げ、ハンドボール投げ)は横ばいか向上の兆しを示した。その一方、跳ぶ能力(立ち幅とび)は小学生、高校生の男子がともに低下傾向を示した。
ただし、体力水準が高かったピーク時の85年度と比べると、11歳女子の50メートル走は9・00秒だったのが9・23秒、11歳男子のソフトボール投げは33・98メートルだったのが30・37メートルにとどまるなど、比較可能な小中学生計8種目中7種目で依然、劣っていた。
また、20~64歳の最近10年間の推移をみると、20~30代の女性は低下傾向が見られるが、40歳以降では男女とも緩やかな向上傾向が見られた。
調査を分析した順天堂大の内藤久士スポーツ健康科学部教授は「子供の運動不足、体力低下への危機感から体育、スポーツ関係者が行ってきた地道な努力、取り組みが効き始めたのだと思う」と話した。
2009. 10. 10
本日、10月10日は何の日かご存知でしょうか?以前は「体育の日」と答える方が多かったもしれません。10月10日を記念日にしているものはたくさんありますが、そのひとつが「目の愛護デー」です。10月10日の「10・10」を横に倒すと眉と目の形に見えることからこの日に制定されました。歴史は意外と古く、中央盲人福祉協会が昭和6年に「視力保存デー」として制定し、戦後、厚生省(現厚生労働省)が「目の愛護デー」と改称し現在に至っています。本日は「目の愛護デー」にちなみ、最近多くみられる「パソコンに代表されるOA機器による眼精疲労」についてお話します。
長時間、パソコンの画面をみたりデスクワークを行うと、目がチカチカしたり焦点が合わせにくくなったりします。目の充血や頭痛・肩こり、吐き気といった症状もあります。これらは「眼精疲労」や「VDT症候群」と呼ばれ、OA機器が普及するにつれて多くの方に症状が現れるようになりました。また、通常は1分間に約10回のまばたきをして涙の膜を作り、目は保護されていますが、画面に集中するとまばたきは1分間に2~3回に減ります。すると目の乾燥も起こり、涙不足の「ドライアイ」になります。
では、どのような対策があるでしょうか。パソコンの環境として、ディスプレイは目線の下に来るようにします。そうすると、まぶたが眼球にかぶさり乾燥を軽減できますし、目の緊張も少しはほぐれます。また、部屋の明るさにあわせてまぶしくないように画面の明るさも調節して下さい。また、疲れ目を回復するために、長時間に及ぶ作業をする人は、必ず1時間に5~10分は休憩を取り、肩や首をほぐすような軽い体操をして下さい。また、目の周りにはたくさんのつぼがあるため、眉毛の上に沿って、鼻の付け根、目の下の骨、こめかみを順に指の腹で心地よい強さで押し、マッサージを行うのもよいでしょう。蒸しタオルを、5分間程度目の上に乗せるのも効果的です。
みなさんも「目の愛護デー」をきっかけに目を大切にすることについて考えてみては如何でしょうか。
2009. 10. 09
発がん性物質に変わる可能性が指摘される不純物を含んでいるとして出荷・販売を停止している「エコナ」関連10製品について、販売元の花王が8日「特定保健用食品(特保)」の表示許可の失効届を消費者庁に提出し、同日付で受理されことがニュースになりました。そこで本日は、この「特定保健用食品(特保)」について簡単に説明します。
「特定保健用食品(特保)」は、「コレステロール値を下げる」「虫歯になりにくい」などの効能や用途を表示できる食品であり、身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含んでいます。「いわゆる健康食品」とは異なり、その保健効果が当該食品を用いたヒト試験で科学的に検討され、適切な摂取量も設定されています。また、その有効性・安全性は個別商品ごとに国によって審査されています。1991年に導入されました。動物実験や臨床試験などの科学的データに基づき、国が許可します。厚生労働省の所管だったが、今年9月に許可権限が消費者庁に移管されました。形態は飲料、菓子などさまざまで、今年8月末時点で892品目に上ります。
2009. 10. 08
新型インフルエンザワクチンの輸入が正式決定しました。厚生労働省は6日、新型インフルエンザの輸入ワクチンについて、英国のグラクソ・スミスクライン(GSK)とスイスのノバルティスの製薬2社と購入契約を結んだと発表しました。GSKから3700万人分、ノバルティスから1250万人分の計4950万人分を購入します。
厚労省などによると、GSKのワクチンは9月末に欧州で承認され、欧州連合(EU)加盟の27カ国で販売が認められています。国産と同じく鶏卵で原料のウイルスを培養するが、国産にはない「アジュバント」と呼ばれる免疫増強剤が添加されています。近く健康な成人100人を対象に日本国内での臨床試験を始める予定です。
また、ノバルティスのワクチンは、犬の腎臓由来の細胞でウイルスを培養。まだ海外での承認はなく、欧州4カ国で行った臨床試験結果を分析中で、日本国内での臨床試験が進んでいます。
厚労省は輸入に当たって、ほかの先進国での承認を条件に国内での正式な治験を省略する「特例承認」を適用する方針だが、使用するかどうかは国内での臨床試験の結果を踏まえて判断するとしており、実際に接種に使えるのは年明け以降の見込みです。厚生労働省が2日発表した、「新型インフルエンザワクチンの詳細な接種スケジュール」によると、輸入ワクチン接種対象者は高校生、高齢者となっています。
2009. 10. 07
日本より一足早く、5日米国で新型インフルワクチンの接種が開始しました。日本のワクチン接種は注射式ですが、この日接種した米国のワクチンは、なんと鼻の粘膜から吸収させるスプレー式です。この鼻粘膜に噴霧するだけで、インフルエンザの感染を予防できる経鼻インフルエンザワクチンですが、日本でも、2007年6月、国立感染症研究所が開発したことがニュースになりました。当時の記事には「動物実験では、皮下に注射する現在のワクチンより効果が高いことが確認され、新型インフルエンザの予防にも威力を発揮することが期待される。感染研は、3年以内に国内初の臨床試験開始を目指している。」と書いてあります。
経鼻ワクチンと注射型ワクチンとの違いですが、注射型は、皮下に注射し血液中の抗体を増やす仕組みで、発症や重症化は防げるが感染は完全には防げません。これに対し開発中の経鼻ワクチンは、鼻やのどをはじめとする全身の粘膜で、従来ワクチンとは違う種類の「IgA」と呼ばれる抗体を分泌させ、感染自体を予防できるという特徴があります。
実際、強毒型のウイルス(H5N1型)の経鼻ワクチンと注射型ワクチンをマウスに接種し、ウイルスを感染させたところ、注射型に比べ、経鼻ワクチンを接種したマウスの生存率は平均して約2倍高く効果的でした。さらに、経鼻ワクチンは、注射型と異なり、様々なウイルス株に効果があるという報告もあります。
経鼻ワクチンの有効性については、引き続きの検証が必要ですが、接種のしやすさを考慮すると、日本でも早く経鼻ワクチンが使用可能になればと思います。
2009. 10. 06
本日は、「緑茶好きの女性、少ない肺炎死」という東北大での調査結果を紹介します。ふだん緑茶をよく飲む女性は、肺炎によって亡くなるリスクが半分ほどにまで下がるという調査結果を東北大公衆衛生学のグループがまとめ、米の臨床栄養学の専門誌で報告した。男性では差がなかった。緑茶に含まれるカテキンという成分が肺炎を起こすウイルスや細菌の働きを抑えている可能性がある。
94年に緑茶を飲む習慣や健康状態などについて聞いた宮城県在住の男女約4万人(40~79歳)について、06年まで追跡した。この間に男性275人、女性131人が肺炎で亡くなっていた。
女性では、緑茶を飲むのが「1日あたり1杯未満」だった4877人のうち、肺炎で死亡したのは43人。一方、「1~2杯」の4458人では死亡は24人、「5杯以上」の7208人で38人。
年齢や体力、結核感染の有無など、肺炎死亡と関係しそうな要因を考慮して比べると、緑茶を飲むのが「1日あたり1杯未満の人たち」に比べて、「1~2杯飲む人たち」は41%、「5杯以上」では47%、肺炎で死亡するリスクが低かった。
ただし、男性では飲む量とリスクは関係がなかった。解析を担当した大学院生の渡辺生恵さんは「男性の8割以上は、肺炎と関連が指摘される喫煙歴があり、緑茶の効果が及ばなかったのかもしれない」という。
グループは今秋から、静岡県掛川市民の協力を得て、緑茶がインフルエンザを抑える効果があるかどうかを調べる予定で調査結果に注目です。
2009. 10. 05
「新型インフルエンザワクチンの詳細な接種スケジュール」の最新情報です。厚生労働省は2日、都道府県の担当者会議で、来年3月までの新型インフルワクチン接種をめぐる詳しい計画を発表した。今月19日の週から医療従事者への接種が始まるが、当面は出荷ペースが遅く、優先接種の対象となる幼児の接種が始まるのは12月後半にずれ込みそうです。 優先対象者の接種時期の目安は、ぜんそくや重い腎臓病などの持病がある人や妊婦が「11月前半」、その他の持病のある人が「12月前半」、1~6歳の幼児や小学1~3年生が「12月後半」、1歳未満の乳児の保護者などが「1月」、続いて小学4年生から中学生となり、いずれも国内産ワクチンを接種する。高校生、高齢者は順次、輸入ワクチンを打つ予定。持病のある人はかかりつけ医で打つことになる。 計画は対象者全員が接種することが前提だが、接種するかどうかは個人が決める任意のものだ。接種する人が少なくワクチンが余れば、各都道府県が予定を前倒しするかを判断する。ただ、実施中の臨床試験などで1回の接種で効果があるとわかれば、計画している国内産ワクチンの接種対象は増えることになる。 接種は、本人の意思確認が必要で、厚労省は16歳未満は原則、保護者同伴にするとしている。
2009. 10. 03
本日は、「新型インフルエンザワクチンの詳細な接種スケジュール発表、初回出荷は59万人分」というニュースを紹介します。厚生労働省は2日、新型インフルエンザワクチンの詳細な接種スケジュールや供給計画を明らかにした。今月9日に最初の59万人分(1人2回接種)が出荷され、19日の週から11月前半までに、優先順位が最も高い医療従事者約100万人が1回目の接種を受ける。計画では、20日に67万人分の出荷が続き、11月から始まる基礎疾患(持病)のある人と妊婦の接種にも使われる。妊婦向けには、あらかじめ注射器にワクチンが詰められているため防腐剤を含まず、安全面での懸念が少ないタイプも11月前半から出荷される見込み。これに先立ち、都道府県は今月7日までに接種を行う医療機関を取りまとめ、厚労省はそのリストを、医療従事者以外の接種対象者向けに10月中に公表する。接種を希望する対象者は、リストに載った医療機関に個別に予約して接種を受ける。当初の出荷量は限られるが、11月には465万人分、12月には760万人分などと増加が見込めるため、厚労省の担当者は「効率的に接種できる態勢を整えておいてほしい」と呼び掛けた。また、スケジュールは対象者が全員接種を受けることを想定しているため、対象者の接種率によっては日程の前倒しもあり得るとした。10月中旬にまとまる国産ワクチンの臨床研究の結果次第では、1人2回必要な接種が1回で十分とされる可能性があり、その場合はさらに短期間に多くの人が接種を受けられる。
2009. 10. 02
本日は、「新型インフルエンザ予防接種、今月中旬から開始。費用は1人6150円 。」というニュースです。政府は1日、新型インフルエンザ対策本部会合を開き、医療従事者や基礎疾患(持病)のある人などを最優先とするワクチンの接種順位や、約5千万人分のワクチン輸入などを盛り込んだ接種の基本方針を正式決定した。
方針によると、接種は国と委託契約を結んだ医療機関で実施。今月19日の週から医療従事者を皮切りに、優先順位に従って希望者に国産ワクチンの接種を始める。
最優先の接種対象者は(1)インフルエンザ患者を診る医療従事者(約100万人)(2)持病のある人と妊婦(約1千万人)(3)1歳から小学校低学年の子ども(約1千万人)(4)1歳未満の乳児の保護者と優先対象だがアレルギーなどで接種を受けられない人の保護者ら(約200万人)。このほかに小学校高学年と中高校生(約1千万人)、持病のない高齢者(約2100万人)も優先される。
接種は、母子健康手帳や健康保険証で優先対象であることを確認しながら原則予約制で行う。医療従事者以外の接種開始時期の目安は、持病のある人と妊婦が11月初め、1歳から小学校低学年の子どもは12月、乳児の保護者は年明け、小学校高学年と中高校生、高齢者は1月前半。接種費用は原則として全国一律で、必要な2回の接種のうち1回目を3600円、2回目は2550円、合計6150円と設定。国と地方自治体で分担し、生活保護世帯の接種費用を無料とするなどの負担軽減策を取る。新型インフルエンザ予防接種の時期を考慮し、早めの季節性インフルエンザワクチン接種をお願いします。
2009. 10. 01
本日は、昨日紹介した「子宮頸がんとワクチン」についてもう少し説明します。子宮頸がんは世界で年間約50万人が発症し、約27万人が死亡している。女性のがんとしては乳がんに次いで2番目に多い。国内でも年間1万人以上が発症し、約3500人が死亡していると推計されます。子宮頸がんの原因の約7割はヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因です。30代後半から40代に多いが、最近は感染原因である性交渉の低年齢化などが影響し、20~30代の若い患者が増えています。ワクチンによる予防手段があるため「予防できる唯一のがん」と言われ、ワクチン接種による有効性は10~20年継続するといわれています。自治医大さいたま医療センター産婦人科の今野良教授によると、12歳の女児全員が接種すれば、子宮頸がんにかかる人を73・1%減らせる。死亡者も73・2%減ると推計されます。ワクチンは、2006年6月に米国で初めて承認されて以降、欧米や豪州、カナダなど世界100カ国以上で使われています。多くの国では12歳を中心に9~14歳で接種が開始され、学校や医療機関で接種が行われています。我が国では、希望者が自己負担で接種する任意接種となる見通しで、全額自己負担だと3万~4万円かかり、普及には費用の問題が深くかかわってくると考えられるが、欧州や豪州、カナダなど26カ国では全額公費負担または補助が行われており、接種率が9割に上る国もあります。外国のこのような方法に対して、我が国がどのような形で予防接種を行うのか注目されます。
2009. 9. 30
本日は、「子宮頸がんワクチン承認」というニュースです。厚生労働省の薬事・食品衛生審議会薬事分科会は29日、子宮頸(けい)がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染予防を目的としたワクチンの承認を決めた。10月中に厚労省の正式承認を経て早ければ年内にも発売される。承認されたワクチンは英系製薬会社、グラクソ・スミスクラインの「サーバリックス」で、すでに世界98カ国で承認されている。HPVは性交渉により感染。ワクチンは頸がんの原因の約7割を占める2種類のHPV感染を予防する効果が期待される。10歳以上の女性を接種対象として検討しており、希望者が自己負担で接種する任意接種となる見通し。6カ月間で3回の接種が必要で全額自己負担だと3万~4万円かかるという。女性にとっては朗報であると同時に、接種開始年齢や費用など解決すべき課題もみられる。
2009. 9. 29
本日は、「新型インフルエンザ、80歳未満の国民の大半は抗体なし」というニュースです。新型インフルエンザウイルスに関し、80歳未満の国民の大半は抗体を持っておらず、免疫がないことが、国立感染症研究所の調査でわかった。国立感染症研究所は、過去30年にわたり約15万人分の血清を集めた「国内血清銀行」から931の検体を使い、新型ウイルスに対する抗体の有無を調査した。その結果、スペイン風邪が猛威を振るった1918~1919年よりも前の1917年以前に生まれた92歳以上の高齢者の50~60%が、新型インフルエンザに対する抗体を持っていることがわかった。しかし、1920年代生まれはおよそ20%程度、1930年代以降に生まれた80歳未満の国民はほとんどが抗体を持たず、免疫がないことが確認された。このことから、新型インフルエンザ対策として、ワクチンの接種が重要な選択肢になると考えられます。
2009. 9. 28
本日は、「新型インフルエンザの国産ワクチン、2700万人分に増産」というニュースです。厚生労働省は、新型インフルエンザのワクチンについて、従来約1800万人分としてきた来年3月までの国内産ワクチンの生産量を約2700万人分に上方修正した。ワクチンのもとになるウイルス株の増え方が想定よりよかったことなどが理由だという。これを受け、子どもでは1歳から就学前までと予定している優先接種の対象を小学校1~3年にも拡大する検討を始めた。同日の専門家による意見交換会で明らかにした。優先接種の意見公募で要望の多かった受験生や保育士への対象拡大は見送る考えという。また、厚労省は、遺伝子検査で新型の感染が確認された患者への今シーズン中の接種は「必要性に乏しい」との考えを示した。57年から大流行したアジア風邪で、再感染した患者が少なかった点などを参考にしたという。
2009. 9. 26
本日も、「新型インフルエンザに関するアンケート結果」を紹介します。マーケティングリサーチ会社のインテージが特定非営利活動法人疾患啓発推進センターと共同で実施。全国の15-79歳の男女を対象に8月26日-31日、新型インフルエンザに関する意識や対策などをインターネット上で尋ね、10万6178人から回答を得た結果です。
「新型インフルエンザワクチンの予防接種を受けたいと思うか」の問いでは、「是非受けたい」と「できるだけ受けたい」を合わせると、52.3%でほぼ半数が「受けたい」と回答。職業別では「医療・ヘルスケア関係」69.6%、「医薬品・医療機器関係製造業」62.1%、「教職員・保育士」57.3%、「専業主婦・主夫」55.9%などが高かった。一方、「自由業」40.3%、「情報処理・IT関係・市場調査」46.5%、「小売・卸売業」47.4%などは低く、5割に届かなかった。
また「あまり受けたいと思わない」「受けたくない」と答えた2万1841人に理由を尋ねたところ(複数回答)、最も多かったのは「予防接種を受けたとしても、かからないとは限らない」45.3%で、「弱毒性で、かかってもそれほど重くならないと思う」33.1%、「ワクチンの予防接種は副作用がある」28.6%、「自分はこれまでかかったことがない」24.9%、「マスク、うがい、消毒などで十分」23.8%などが続いた。
アンケートの結果は以上です。
2009. 9. 25
本日は、「新型インフルエンザに関するアンケート結果」を紹介します。マーケティングリサーチ会社のインテージが特定非営利活動法人疾患啓発推進センターと共同で実施。全国の15-79歳の男女を対象に8月26日-31日、新型インフルエンザに関する意識や対策などをインターネット上で尋ね、10万6178人から回答を得た結果です。
「新型インフルエンザをどの程度怖い病気だと思うか」では、「とても怖い病気」が18.8%、「やや怖い病気」が49.0%だった。一方、「あまり怖くない病気」は11.0%、「全く怖くない病気」は1.4%であった。
「新型インフルエンザにかかる可能性はあると思うか」では、「ある」32.8%、「少しはある」37.4%で、「あまりない」と「ない」は、それぞれ8.4%、1.9%だった。「ある」と「少しはある」を合わせた「罹患の可能性がある」の回答率を職業別にみると、高い方から「医薬品・医療機器関係製造業」80.4%、「医療・ヘルスケア関係」80.1%、「教職員・保育士」78.9%、「公務員」78.5%の順だった。一方、低かったのは「無職」63.8%、「農林水産業」66.4%、「自由業(作家、タレント、プロスポーツ選手など)」66.9%などであった。
明日も引き続きアンケート結果を紹介します。
2009. 9. 24
本日は、「妊婦への季節性インフルエンザワクチン接種が90%の効果あり」という研究結果を紹介します。妊娠中に季節性インフルエンザワクチンを接種した女性には、感染や重症化予防に必要な抗体が90%の確率で生成され、胎児にも十分な免疫力が備わることが19日、国立成育医療センター(東京)の研究で分かった。一般の人に比べ、安全面に慎重な配慮が必要で研究対象になりにくい妊婦や胎児について、インフルエンザワクチンの有効性を免疫学的に立証した報告は海外にも例がないといい、研究を主導した同センター母性内科の山口晃史医師は「副作用も認められなかった。新型インフルエンザ用ワクチンも製造法は基本的に同じなので、同様の効果が期待できる」としている。研究は一昨年から昨年にかけ、同センターに来院した妊娠15~39週の女性125人(25~41歳)を対象に実施。病原性を除去したA型2種、B型1種のウイルス株を含む不活化ワクチンを使い、接種前と接種1カ月後の血中の抗体価(免疫力を示す指標)を調べた。その結果、45人は接種以前に3種すべてのウイルスに免疫があり反応は鈍かったが、残り80人の90%に当たる72人は、ワクチンに明確に反応。免疫のないウイルスに対する抗体が急増し、十分な免疫力の目安とされる「抗体価40倍」を超えた。日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会が作った「産婦人科診療ガイドライン産科編2008」(日本産科婦人科学会発行)には、妊婦がインフルエンザワクチンの接種を希望する場合は接種してよいという公式見解が、明記されています。インフルエンザは妊婦がかかると重症化しやすいとされており、赤ちゃんの器官ができあがった16週以降の方なら、妊娠中のワクチン接種もインフルエンザ予防対策の選択肢のひとつになると考えます。
2009. 9. 19
本日は、「心筋再生の臨床試験開始へ」というニュースを紹介します。京都府立医大は、重い心不全を起こした患者自らの心臓幹細胞を使い、心筋を再生させて機能回復を図る臨床試験が、厚生労働省に許可されたと発表した。年内にも同医大病院と国立循環器病センター(大阪府吹田市)で、重い慢性虚血性心疾患の6人に実施する予定。循環器内科の松原弘明教授は「心臓移植のドナー(提供者)不足は深刻で、移植に代わる医療となることを希望している。10年後の実用化を目指したい」としている。計画では患者の心臓組織の一部から高い分化能力を持つ幹細胞を15~20ミリグラム採取。患者本人の血清を用いて約4週間かけて培養し、増殖した約5千万個を心筋が弱った場所の近くに注射する。松原教授はブタを使った実験で有効性と安全性を確認。厚労省に許可申請していた。
2009. 9. 18
本日は、「食事と一緒にビールを飲むと血中エタノール消減速度が速くなる」という調査結果を紹介します。アサヒビールは日本医科大学と共同で、ビール摂取後の血中エタノールの消滅時間についての調査結果をまとめた。ビールだけを摂取した場合に比べると、食事と一緒にビールを摂取した場合の血中エタノールの消滅時間は約10%強短い2.9時間。エタノールは人を“酔い”の状態にさせる成分で、食事と一緒にビールを飲んだほうが、酔いがさめるのが早いことが明かになった。 アサヒと日本医科大によると、食事と一緒にビールを摂取したほうが、酔いざめが早いのは、食べ物に含まれるアミノ酸の働きが加わるため。アミノ酸が体内の代謝を促進させるピルビン酸を供給、酔いの要因となるエタノールの分解を促進する効果があり、早い酔いざめを期待する場合は、ビールと一緒に食事を摂取することが望ましいと説明している。
2009. 9. 17
開発中のインフルエンザ治療薬(点滴薬)「ペラミビル」の情報です。開発中の「ペラミビル」が、1回の投与で、タミフルを5日間服用したのと同等の効果があることが、米サンフランシスコで開かれた米国微生物学会で報告され、AP通信が報じた。ペラミビルは、米国の製薬会社バイオクリスト社が開発し、2010年秋にも塩野義製薬が日本国内での販売を計画している新しい抗インフルエンザ薬。長崎大の河野茂教授(先進感染制御学)によると、08年にアジアで季節性インフルエンザの患者約1100人にタミフルかペラミビルを投与して効果を比較した結果、ペラミビルの注射1回で、タミフルを1日2回、5日間服用した場合とほぼ同じ時間で症状が回復した。ペラミビルは、現在インフルエンザ治療薬として使われているタミフルやリレンザと同じ「ノイラミニダーゼ阻害薬」と呼ばれるタイプの薬で、新型インフルエンザにも効果があるとみられている。内服薬のタミフル、吸入薬のリレンザに対し、点滴薬である点が特徴で、薬を飲めない重症者や感染から時間が経過した患者に効果が期待されている。
2009. 9. 16
本日は、「はしかの予防接種率」の話題です。はしか(麻疹)予防のため、13歳(中学1年)と18歳(高校3年)を対象にした追加予防接種の接種率が、流行予防の目安となる95%に届かなかったことが、明らかになった。厚労省は12年度までにはしかを国内からなくす目標を掲げており、今年度以降も追加接種を呼びかける。 労省の専門家会議で報告された。3月末現在で13歳は85%、18歳は77%だった。都道府県別にみると、13歳では福井が最も高く95%。富山と茨城が続いた。最低は福岡の75%。18歳では95%を超える都道府県はなく、最高は山形の91%。最低は東京都の60%で、大阪や神奈川など大都市圏で低い傾向がみられた。 はしかワクチンは接種によって95%の人が免疫を得ると言われ、高い効果が期待できる。追加接種でさらに効果が高まるとされる。厚労省は接種率が目標に及ばなかったことについて「PR不足もあったかも知れない。今年度は目標に届くよう努力したい」としている。 当院でも接種可能ですのでまだの人は宜しくお願いします。
2009. 9. 15
今日は老人福祉法で「老人の日」と定められています。そこで「100歳以上の高齢者、4万人突破」の話題をとりあげます。厚生労働省は11日、全国の100歳以上の高齢者が今月15日(本日)時点で4万399人になる、と発表した。前年の3万6276人から約1割増え、初めて4万人台になった。全体の86.5%が女性。今年度中に100歳になる人は、初めて2万人を超えた。老人福祉法で「老人の日」と定められた15日を前に、厚労省が毎年公表している。同法が制定された63年は153人だったが、81年には1千人を超えた。初めて1万人を上回ったのは98年で、わずか11年で約4倍になった。国内最高齢者は、沖縄県の114歳の女性。人口10万人当たりで比べると、都道府県別で最も多いのが沖縄県の67.44人で、37年続けて1位。次いで、島根県(66.21人)、高知県(61.45人)が多い。上位10県のうち九州が5県、中四国が5県を占めた。最も少ないのが埼玉県の15.90人で、20年連続の最下位。次いで愛知県(18.45人)、千葉県(21.45人)、神奈川県(21.98人)です。
2009. 9. 14
「国産新型インフルワクチンも効果、安全性を確認のため治験」という情報です。 厚生労働省は、国産の新型インフルエンザワクチンについて、国立病院機構で成人200人を対象に臨床試験(治験)を行う。国産ワクチンは、従来の季節性インフル用と同じ方法で作るため、法令上は新たな治験は必要ない。しかし、効き目が弱い恐れがあるため、通常の2倍量の接種なども試み、有効性と安全性の確認を急ぐ。インフルエンザに対する基礎的な免疫は、毎年、ウイルスの体内侵入を受けることで、少しずつ高まる面がある。このため、季節性インフルのワクチンは成人には1回の接種で効くが、大半の人が免疫を持たない新型インフルは、ワクチンの効果が低い可能性があり、2回接種を予定している。治験では、3週の間隔で2回接種し、各段階で免疫をどのくらい獲得できたかを調べる。また、半数の100人には通常の2倍量を接種する。効果とともに、発熱や腫れなどの副反応が従来のワクチンと大差ないかどうかを確認する。成人とワクチンの接種量が異なる12歳以下の小児についても、治験の実施を検討している。
2009. 9. 12
「輸入新型インフルワクチンにめど、輸入で5000万人分」という情報です。新型インフルエンザ対策ワクチンの緊急輸入で、厚生労働省が欧州メーカー2社との交渉で約5千万人分を確保したことがわかった。国産の約1800万人分を合わせて、7千万人分近くになる。厚労省は高齢者や持病のある人ら接種の必要性が高い人を5300万人と見込んでいた。輸入のめどがたったのは、グラクソ・スミスクライン(英国、GSK)からの3500万人分余りと、ノバルティス(スイス)からの1200万人分余り。上積み分があるといい、合計で5千万人分を確保したとされる。1人分は2千円程度で契約する見込みで、合計額は1千億円前後。厚労省は承認手続きを簡略化する特例承認を検討しており、その場合には、接種は12月下旬からになる見込みだ。 季節性インフルエンザの接種と同じ扱いで、原則として希望者の負担で接種する。2回の接種で計7千円程度とされるが、低所得者のための補助制度を設けるとのことです。
2009. 9. 11
「輸入新型インフルワクチン、日本で来週治験開始」という情報です。 スイスの製薬大手ノバルティスの日本法人は、新型インフルエンザワクチンの日本での臨床試験(治験)を来週から始めると明らかにした。国内の病院で、成人200人、小児120人の計320人の協力を得てワクチンを接種し、有効性と安全性を確かめ、厚生労働省の承認を受けるためのデータにする。結果が判明するのは12月ごろになる見込み。 新型インフルワクチンに関しては国産分だけでは供給量が不十分なため、厚労省は輸入を検討中。同社などの輸入ワクチンは国産ワクチンと成分が違い、効果を高める免疫補助剤を使うなどしているため、国内で安全性などの確認が必要とされている。
2009. 9. 10
本日は、厚生労働省が8日に発表した「新型インフルエンザワクチンについて接種開始時期や接種方法などの実施案」を紹介します。費用は全国一律とし、接種者や保護者が原則、実費で負担する方向。低所得者に対する負担の免除や軽減については検討中という。 接種回数は3~4週間の間隔で2回、費用は不確定だが同省内には「8千円程度」との見通しもある。10月下旬以降、最優先予定のグループから始める。(1)医療従事者(2)妊婦、重症化リスクとなる持病がある人(3)1歳~小学校入学前の小児(4)1歳未満の小児の両親、の順を想定。ワクチンの供給状況をみながら、健康な小学生、次いで健康な中高生や高齢者に広げる。 接種場所は、国の委託を受けた医療機関になるが、地域の医師会と市町村が決め、10月中旬に厚労省のウェブサイトなどで公表する予定。持病がある人や入院している人は現在、かかっている医療機関で受けることになる。 一方、季節性インフル用のワクチン接種も例年通りする方針。予防接種法で国が接種を勧めている65歳以上と60歳以上の持病がある人を対象に、供給を優先するよう医療現場に求める方針を示した。今季は新型用の生産のため、昨季の8割分にあたる2220万人分しかなく、季節性インフルが重症化しやすい高齢者での接種を確保するための措置だという。
2009. 9. 09
「新型インフルワクチン接種できる医療機関を限定へ」というニュースです。厚生労働省は、新型インフルエンザワクチンの接種を、国と委託契約を結んだ医療機関に限って行う方針を固めた。対象の医療機関は市町村や地域の医師会が選ぶ。供給量に限りがある国産ワクチンを、最優先接種者から順に、適切に接種していく必要があるため、当面は医療機関を限定する必要があると判断した。最優先の接種対象者は、医療従事者、糖尿病やぜんそくなどの持病のある人や妊婦、1歳~就学前の小児、1歳未満の乳児の両親を合わせた1900万人。ワクチン輸入も計画されているが、供給は12月下旬以降の見通し。国産は早ければ10月下旬から出荷されるが、年内の生産量は最大1700万人分しかない。持病がある人のかかりつけが対象外となった場合、主治医から「優先接種対象者証明書」を発行してもらい、国と委託契約した医療機関で接種を受ける。方針案は都道府県担当課長会議に提示される。
2009. 9. 08
安心・安全は冷蔵庫に-。本日は「救急医療情報キット」について紹介します。持病や服用薬などの医療情報を容器に入れて冷蔵庫に保管する「救急医療情報キット」の導入が、東京都港区や北海道夕張市など全国に広がっている。自宅で倒れるなど万一の際、迅速な救命活動に役立ててもらうのが狙い。約20万人が暮らす港区は昨年5月から「救急医療情報キット」を、希望する区民(高齢者と障害者)に無料で配布している。キットは持病や服用薬、かかりつけ医、緊急連絡先を記入する用紙とプラスチック容器がセット。必要事項を書き込んだ用紙のほか、本人確認ができる写真や健康保険証の写しを容器に入れ、冷蔵庫に保管する。同高輪地区総合支所の神田市郎区民課長は「都会では隣近所とのつきあいが少なく、万一のときに不安を抱える高齢者も少なくない。病状を説明できないような一刻を争う事態に、救急隊が患者情報をいち早く把握することで適切な救命活動につなげてもらえれば」と、導入の狙いを話す。医療情報を冷蔵庫に保管するユニークなシステムは、米国・ポートランド市が実施する高齢者の救急対応を参考に、港区が考案した。「冷蔵庫ならどこの家庭にもあるし、すぐ目につく。外部に事前に個人情報を知らせる必要もないので、プライバシーを守れる極めて都会型のシステム」と神田課長。高齢化が進む地域住民の命を守る取り組みとして注目です。
2009. 9. 07
本日は、手に広げやすい「泡タイプのイソジン」販売のニュースです。明治製菓は7日、殺菌・消毒効果のある手洗い剤「イソジン泡ハンドウォッシュ」を発売する。同社のうがい薬に使っている有効成分「ポビドンヨード」を1ミリリットル中、75ミリグラム配合。新型インフルエンザや食中毒を予防したい主婦らに売り込む。ポンプから泡状の洗剤が直接出るタイプで、手の隅々まで洗剤を広げて洗いやすい。従来のイソジンブランドの手洗い剤は液状タイプだけだった。250ミリリットル入りで、希望小売価格は1029円。全国のドラッグストアや薬局などで販売する。
2009. 9. 05
「新型インフルエンザ用ワクチンの優先接種順位」についてのニュースです。厚生労働省は4日、新型インフルエンザ用ワクチンの優先接種順位をインフルエンザ患者を診る医療従事者を最優先とする同省案を発表した。第2位以下は「妊婦と基礎疾患(持病)のある人」「1歳から就学前の幼児」「1歳未満の乳児の両親」の順。対象者は計約1900万人。国民の意見(パブリックコメント)を今月6日から13日まで募り、月内に最終決定する。厚労省案によると、ワクチン接種は「死亡者や重症者の発生をできる限り減らす」のが目的。対象者には、10月下旬にも出荷が始まる国産ワクチンを優先的に使う。最優先とされた医療従事者は約100万人で、患者を搬送する救急隊員も含めた。新型インフルエンザに感染するリスクが高く、感染すれば医療全般に支障が出ることが理由。次に「国内外で入院数や重症化率、死亡率が高い」として妊婦(約100万人)と持病のある人(約900万人)を挙げ、持病のある幼児は特に優先するとした。さらに、海外で乳児の入院率が高く、国内でインフルエンザ脳症による幼児の重症例が出ていることなどから、就学前の幼児(約600万人)も対象に。1歳未満の乳児は接種しても十分な免疫が得られないため、両親(約200万人)に接種して感染を防ぐ。これ以外に、接種が望ましいとされる小中高校生と持病のない65歳以上の高齢者計約3500万人には原則として輸入ワクチンを使う方針。輸入については現在、海外メーカー2社と詰めの交渉中で、治験を必要としない薬事法上の「特例承認」を適用して行う方向だが、国産とは製法が異なるため国内で小規模な臨床試験を実施する。早ければ12月下旬から接種できる見通しという。厚労省は「医療従事者から順番に接種を始めるが、一つのグループが終わらなければ次のグループに接種しないわけではなく、出荷状況に応じて進める」としている。
2009. 9. 04
インフルエンザ予防策がネットで動画配信されます。新型インフルエンザの予防法や対策を国民に広く知ってもらおうと、政府インターネットテレビ(http://nettv.gov-online.go.jp/)は3日から「予防編」「受診と療養編」の動画を配信する。各7分半。正しい手洗い法やせきをする際のエチケット、医療機関の受診方法、自宅療養時の注意点などを、国立感染症研究所の専門家による解説も交えて説明する。厚生労働省も小学生に新型インフルを知ってもらうためのネット動画を作成中で、今月中旬までに公開予定です。
2009. 9. 03
「広島大で折りたたみ式の橋開発」という話題を紹介します。広島大は、災害現場でもコンパクトに折りたたんで運べる応急橋「モバイルブリッジ」を開発し、試作品を報道各社に公開した。アルミ合金製で幅0・5メートル。パンタグラフのように長さ0・5~6メートルに伸縮可能で、歩行用板を敷けば、大人3人(体重計約215キロ)が同時に渡れる強度を持つ。組み立て時間は約3分。総重量83キロで軽トラックでも運べる。開発に当たった有尾一郎助教(構造解析学)は、平成16年の新潟県中越地震の被災地を調査。従来の仮設橋は部材ごとに大型トレーラーで運び、設置に4~7日かかるため、緊急性を要する災害現場により適したタイプの研究を重ねてきた。「災害復旧作業や被災者の迅速な救助に有効だ」と期待。今後は乗用車も通行できる応用型(幅2メートル、最長20メートル)の開発も進め、自治体への配備を目指すという。
2009. 9. 02
本日は、昨日紹介した「植物工場」について簡単に説明します。植物工場とは、閉鎖的または半閉鎖的な空間内において、主として植物を計画的に生産するシステムです。施設内で、植物の生育に必要な環境を、LED照明や空調、養液供給等により人工的に制御し、季節を問わず連続的に生産できるシステムです。
以下のような魅力があります。
・1年中安定的に生産できます。
・工業団地・商店街の空き店舗等農地以外でも設置できます。
・多段化で土地を効率的に利用できます。
・自動化や多毛作で高い生産性を実現します。
・形や大きさ、品質が揃うので、加工が容易です。
・栄養素の含有量を高めることが可能です。
・無農薬で安全・安心。無洗浄で食べられます。
ただし、以下のような普及に向けた課題もあり今後の取組が必要です。
・コストダウン。(施設整備、エネルギー)
・栽培技術の確立(先進地域オランダの半分以下に留まる生産性の向上)と人材育成。
・専用品種の開発や対象作物の拡大。
2009. 9. 01
「植物工場の野菜に対する意識調査」の話題です。日本政策金融公庫は、工場で栽培した野菜に関する調査結果を発表した。それによると、約6割の消費者が通常の野菜より安ければ工場で育てた野菜を買うと答えた。工場で育てた野菜を買ったことのある消費者は9.2%にとどまった。工場の野菜は通常と比べ生産費用がかかりやすいため、「費用削減と付加価値をつけることが課題」(同公庫)としている。価格について、通常の野菜と比べ「多少安ければ購入する」人が37.6%、「かなり安ければ購入する」人が21.3%と、合計58.9%にのぼった。工場の野菜を知っている割合は、60代は81.7%だったものの、20代は53.0%だった。
2009. 8. 31
「がん患者のための冊子、国立がんセンターが試作」という話題です。がんと診断された患者にまず知ってほしい病気の基礎知識や心構え、療養生活のポイントなどをまとめた冊子を国立がんセンターが試作し、がん対策情報センターのホームページ(HP)上で公開した。秋以降、一部の病院で患者に配布。実際に使ってもらい、どの程度役立つかなどを検証し、「将来はすべての患者に配られる“必携”の冊子にしたい」と意気込んでいる。冊子は「がんになったら手にとるガイド」「わたしの療養手帳」「地域の療養情報」の3種類。厚生労働省のがん対策推進協議会で、患者・家族の支援活動をしている委員が提案した。試作版の作成には患者や家族もかかわり、実体験が反映されたほか、患者本人の手記も掲載している。「がんになったら手にとるガイド」はA4判で254ページ。がんの治療法のほか、療養生活の過ごし方、診断されたときの受け止め方などが具体的に書かれている。例えば、治療の副作用で吐き気があるときの食事については、「あっさりしたもの、口当たりのよいもの、飲み込みやすいものが食べやすいようです」などとしている。
2009. 8. 29
「食品に対する意識」についての話題です。「日本政策金融公庫」が全国の20~60歳代の男女2000人を対象に7月に実施した消費者動向調査によると、食品に対する意識は「安全」より「価格」を重視する人が増えていることがわかった。食品に対する意識で、「安全」を重視する人は08年5月の41.3%から19.8%に低下、「経済性」を重視する人は27.2%から35.1%に増えた。国産品か輸入品かを気にかけない消費者も増えており、輸入食品の安全性へのイメージは改善している。日本政策金融公庫は、08年1月の中国製冷凍ギョーザによる食中毒事件をきっかけに高まった食に対する不安が、食品メーカーや流通業者などの取り組みで沈静化したことに加え、08年9月の世界的な金融危機により低価格志向へ一転したと分析している。
2009. 8. 28
「あなたが食べるものは、一緒に食べる人に依存するのかもしれない。」という海外の研究を紹介します。マクマスター大学のヤング氏は、3つの総合大学のバイキング式カフェテリアでの観察で、男性の友人と一緒に食べる女性は女性同士で食べる女性よりも有意に低カロリーの食事を選んでいたことを発見した。そのうえ、男女混合グループで食べる女性の選んだ食べ物はカロリースケールの下端で、そのグループに男性が多かった場合のカロリーはより減少したことも発見した。しかし、女性だけのグループの場合、カロリーは有意に高まったと報告した。皆さんにも思い当たる節はありますか。
2009. 8. 27
「新型インフルエンザ」の情報です。国立感染症研究所感染症情報センターによると、今年第28週(7月6-12日)から第33週(8月10-16日)の間に、全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザ患者の1万8438人のうち約85%に当たる1万5768人が20歳代以下だった。現在、国内で検出されているインフルエンザウイルスのほとんどが新型であるため、患者の大半が新型に感染していると考えられる。同センターの調べでは、患者の年代別の割合は0-4歳10.6%、5-9歳20.3%、10-14歳21.0%、15-19歳17.9%、20-29歳15.7%だった。同センターでは、10歳未満の患者が多い季節性インフルエンザと違い、今回の新型では「10歳代の人が多い」と分析。特に5-19歳が患者発生の中心とみている。ただし、今後はほかの年代にも感染が広がる可能性もあります。
2009. 8. 26
喫煙と肺がんに関するニュースです。ニュージーランドのオークランド大学はこのほど、喫煙者の口内粘膜をぬぐって採取した検体の遺伝子を調べ、将来肺がんにかかるリスクを予測するテストを開発した。肺がんの多い家系かどうかや年齢などの要素も考慮し、危険度を3段階で判定する。簡単な検査でリスクが分かるため、がんの早期発見につながると期待されている。テストは元喫煙者にも有効。同大によると「平均的喫煙者」が肺がんになる危険度は非喫煙者の20~30倍。テストの結果、最高リスクと判定された場合、危険度は平均的喫煙者の10倍と見なされる。研究チームは「リスクが低かった場合も、安心して喫煙を続けるのでは意味がない」とくぎを刺している。師のサインがあれば、検査キットを入手できる。当初はニュージーランド国内に限られるが、年内に他国でも入手が可能になる見通しという。
2009. 8. 25
「日焼けベッドで発がんの恐れ」という記事を紹介します。世界保健機関(WHO)の専門機関である国際がん研究機関(IARC、本部フランス・リヨン)は、人工的に肌を日焼けさせる「日焼け用ベッド」の発がんリスクを5段階の危険度で上から2番目の「高い可能性がある」から「人間に対する発がん性がある」との最高レベルに引き上げると発表した。20以上の疫学研究機関の分析によると、人工的に紫外線を放射する「日焼け用ベッド」の使用を30歳になる前に始めた場合、皮膚がんなどを引き起こす黒色腫が形成されるリスクが75%高まることが分かった。IARCの発がんリスク分類で最高レベルにランクされるのは、ほかにアスベスト(石綿)やカドミウム、喫煙など100種類超。「日焼け用ベッド」はファッションとして広く利用されており、安全性をめぐる論議を呼びそうです。
2009. 8. 24
「広島特産のカキや日本酒でがん予防?」という広島大学での研究の話題を紹介します。 貝類や日本酒に含まれるうま味成分の一種、コハク酸にがん細胞の増殖を抑える効果があるとの研究結果を、広島大学の加藤範久教授(分子栄養学)らが15日までにまとめた。コハク酸はカキや酒かすに含まれるが、機能性についてはあまり注目されていなかった。加藤教授は「貝汁に含まれる程度の濃度でも抑制効果が期待できる。コハク酸を日常の食事で取ることで、がんが予防できるかもしれない」と話している。加藤教授は、コハク酸がある環境で大腸がんや胃がん細胞を培養すると、増殖が半分程度に抑えられるのを確認。ラット実験で、がんの増殖を促すとされる血管新生が起きにくくなることも確かめた。今後、さらなる研究が期待されます。
2009. 8. 22
昨日に引き続き、新型インフルエンザについての情報をQ&A方式で紹介します。
・Q)感染を予防するワクチンの供給体制はどうなっているの?
・A)国内のワクチンメーカー4社が現在、製造にあたっていますが、これまで年内に1400万~1700万人分としていたワクチンの国内製造見通しを、1300万~1700万人分と下方修正しています。メーカーの製造開始時期のばらつきなどが原因で、今後の生産状況によってはさらに減る恐れもあるとしています。現在、新型インフルエンザ用ワクチンの接種の優先順位について、厚生労働省の意見交換会が行われている状況です。
・Q)新型インフルエンザに対する予防策は?
・A)手洗い、うがいの徹底が大切です。ウイルス感染の可能性があるドアノブやつり革などを触った後も手洗いをする習慣を家族ぐるみで身につけることが重要です。また、部屋が乾燥している場合は湿度を50~60%ぐらいに加湿すると感染しにくくなります。人ごみの中ではマスクが効果的です。少しでも咳(せき)が出る人はマスクを着用し、咳エチケットを心がけましょう。
新型インフルエンザについては、これからも情報を紹介していきたいと思います。
2009. 8. 21
全国で患者が急増している新型インフルエンザについてです。通常のインフルエンザは1~2月に流行のピークを迎え、夏には患者が少なくなります。ところが、新型についてはほとんどの人が免疫を持っていない上、感染力が強く、真夏に入ってからも感染が止まらず、夏休みが終わり、子供たちが学校の集団生活に戻る9月以降に感染が急激に拡大する恐れがあります。そこで、新型インフルエンザについての情報をQ&A方式で紹介したいと思います。
・Q)新型の流行は今後どうなるの?
・A)9月に学校が再開されてから、流行のピークを迎えることが考えられます。通常、インフルエンザウイルスは湿度や高温に弱いとされるが、新型は夏にも感染が拡大しており、流行規模がどの程度にまで達するのかはよくわからないというのが現状です。
・Q)感染した場合、どのような人が重症化するリスクが高いの?
・A)糖尿病、ぜんそく、人工透析を受けている患者など持病のある人や、妊婦、乳幼児については新型に感染すると重症化の恐れがあります。持病があると重症化しやすいのは、病気を防ぐ免疫力が落ちるためです。また、6歳以下の乳幼児はインフルエンザ脳症の合併症を発症することがあるため注意が必要です。
明日も引き続き、新型インフルエンザについての情報を紹介します。
2009. 8. 20
「はしか予防ワクチン、2回目接種率が初の90%超え」という話題を紹介します。はしかを確実に予防するため、6歳児を中心に行われている2回目のワクチン接種率が2008年度は91.8%となり、2回接種が始まった06年度(79.9%)以降、初めて90%を超えたことが、厚生労働省の調査で分かった。 前年度比では3.9ポイント増え、流行阻止に必要とされる接種率95%に向け着実に増加。一方、07年の10~20代のはしか流行を教訓に08年度から始まった13歳、18歳への追加接種は85.1%、77.3%にとどまった。 厚労省結核感染症課は「都道府県で接種率に高低差があるので、調査結果を分析して施策に生かしたい」と話した。 2回目接種率が高かった都道府県は秋田(97.3%)がトップで、次いで佐賀(96.3%)、福井(96.0%)の順であった。はしかの予防接種は当院でも可能ですので、まだの人は接種をお願いします。
2009. 8. 19
「たばこ喫煙率、初の25%割れ」というニュースを紹介します。日本たばこ産業(JT)が14日発表した全国たばこ喫煙者率調査によると、2009年の喫煙者率は前年から0.8ポイント低下し24.9%だった。たばこの喫煙率は、14年連続で低下し、1965年に調査を開始して以来初めて25%を下回った。男女別に見ると、男性が0.6ポイント低下して38.9%、女性が1.0ポイント低下して11.9%だった。全国推計の喫煙人口は2601万人で、前年に比べ79万人減った。たばこ自動販売機用成人識別カード「タスポ」の導入や喫煙所の減少、健康志向の高まりなどが要因として考えられるという。
2009. 8. 18
いま、大変人気の電動自転車の話題です。三洋電機は折り畳み式の電動アシスト自転車「エネループ バイク CY-SPJ220」を9月21日に発売する。タイヤの直径は20インチ(約50センチメートル)で、全長は1メートル55センチ。折り畳むとほぼ半分になる。「マンションの玄関や室内に自転車を置きたい」という消費者の声に応えた。重さは18.5キログラムで、このクラスの電動自転車としては軽めという。前輪のモーターで駆動力を発生させる方式で、下り坂やブレーキをかけた時には発電に切り替える「回生充電」機能を備える。家庭用の電源につないだ充電器を使って約2時間15分でフル充電でき、最大で46キロメートル程度走れる。白、赤、黒の3色を用意した。価格はオープンだが、店頭では10万~11万円前後と想定している。月1000台を生産する計画とのことです。
2009. 8. 17
胸骨圧迫を中心とした心肺蘇生(そせい)法を広める大阪の特定非営利活動法人(NPO法人)が、子供でも扱えるコンパクトな訓練キット「あっぱくん」をこのほど作製した。学校でも取り入れやすいよう、従来のキットより安価に設定し、全国に販売する。 あっぱくんは、「大阪ライフサポート協会」(大阪市)と京都大などが作製。縦約25センチ、横約35センチの箱型で、開くとスポンジでかたどった人の胸部になる。心臓部分を正しい力で押すたびに、「ピッ」と音が鳴る仕組み。自動体外式除細動器(AED)の疑似装置も付いており、胸骨圧迫の後にAEDを使用する一連の流れが体験できる。いざという時に救命活動ができるためには、子供のころから心肺蘇生法やAEDについて学び、繰り返し訓練することが大切です。
2009. 8. 12
食中毒についての情報です。近年増加している「カンピロバクター食中毒」。鶏肉や牛肉の生食が原因とされ、発生件数はノロウイルスや病原性大腸菌O(オー)157を超えており、これからの時期は特に注意が必要です。厚生労働省調省によると、カンピロバクター食中毒の全国患者数は、2007年2396人、08年3071人と近年増加の傾向で、大阪や東京などの都市部の方が目立っており、生食肉を出す飲食店や利用客の多さに加え、調理器具を介した集団感染が起きやすいことが理由だという。カンピロバクター菌は鶏や牛の腸管に存在しており、家畜からの汚染食品(鶏肉や牛乳など)の摂取後2-7日(平均2-3日)で下痢、腹痛、発熱などの症状がみられます。 予防は十分な加熱と調理器具の消毒です。食中毒については、院内広報誌「じゅんくり」9月号で取り上げる予定にしております。
2009. 8. 11
減少するミナミマグロの養殖についての話題です。近畿大水産研究所(和歌山県白浜町)は、人工ふ化させたミナミマグロを、稚魚サイズまで育てる「種苗生産」に成功した。近畿大によると世界初で、減少するマグロ資源の回復につながると研究者たちは大きな期待を寄せている。ミナミマグロはインドマグロとも呼ばれ、クロマグロ(本マグロ)に次ぐ高級魚。オーストラリアの水産養殖会社、クリーン・シーズ・ツナが施設内での人工ふ化には成功していたが、稚魚サイズの成長にまでは至らなかった。稚魚がさらに成長して産卵すれば完全養殖の実現となる。近畿大は平成14年、クロマグロの完全養殖に成功しており、同社との共同研究でそのノウハウが応用された。同研究所の村田修所長(69)は「人工ふ化や養殖の技術など、互いの良いところを存分にぶつけ合えたのが結果につながった」と語った。
2009. 8. 10
お薬のお話です。エーザイは、主力のアルツハイマー型認知症治療薬「アリセプト」について、ゼリー剤の承認を厚生労働省から取得したと発表した。これまでアルツハイマー薬には錠剤や細粒剤などがあったが、ゼリー剤は世界初。認知症患者は飲み込む力が落ちた高齢者が多いことから、服用しやすいゼリー剤の開発を進めていた。今秋以降に売り出す。 適度な甘さがある「はちみつレモン風味」の味付けにして、ゼリー状でも違和感がないようにした。スプーンですくって患者に飲ませることができるため、介護担当者にとっても扱いやすくなります。
2009. 8. 08
自動車運転中の携帯電話操作の危険性に関する記事を紹介します。米バージニア工科大交通研究所は、トラックを運転中に携帯電話のメールを読み書きすると衝突事故の危険率が23倍になるとの調査結果を発表した。米メディアによると、チームは乗用車やトラックに設置された監視カメラの記録を運転者約100人分について分析。調査期間は約1年半で、走行距離は総計約1千万キロに及んだ。 その結果、運転手が携帯電話でダイヤルすると衝突事故や衝突しそうになる危険率が5.9倍になった。とりわけ危険なのはメールの読み書きで事故の危険率は23.2倍となり、このとき運転者は約5秒間、道路から目を離していた。時速約90キロで走行しているとすると、100メートル以上は前を見ずに走っていることになる。 ただ、シミュレーターを使った過去の研究結果とは違い、会話するだけでは事故の危険率はほとんど変わらないこともわかり、チームは「危険なのは、運転者が道路から目を離すこと」と結論づけた。ハンズフリー装置を使っていても、ダイヤル時に携帯電話を見つめたりするのは危険としている。
2009. 8. 07
がん患者の約半数は診断時、既に体重減少がみられるといわれていますが、体重減少が大きくなればなるほど、平均の生存期間も短くなります。医療の進歩でがん患者の生存期間が長くなる中、がんの初期から適切な栄養管理を行うことで、QOL(生活の質)を保つことが可能なことが分かってきました。では、体重減少を食い止めるにはどうしたらよいのでしょうか。がん患者の栄養管理に詳しいせんぽ東京高輪病院(東京都港区)栄養管理室の足立香代子室長は「普段の食事に加え、ウナギやサンマなど脂の多い魚2、3匹と、ビタミンCやβ-カロテンなど抗酸化ビタミンを含む緑黄色野菜5、6皿分をさらに食べる」ことを勧めている。また、そうした量の栄養をバランス良く効率的に補給できる栄養機能食品を、製薬会社「アボットジャパン」(東京都港区)が発売した。医薬品ではなく紙パック飲料なので、普段の食事に加えて一日2パック飲めば、タンパク質32グラム、エネルギーも600キロカロリー分が補給できます。治療や日常生活に耐えられる体力を維持するためにも、栄養管理は重要です。
2009. 8. 06
高齢の運転者が表示する「もみじマーク」の見直しについての話題です。「もみじマーク」のデザイン変更を検討している警察庁は、代替案を9月にも公募する方針を決めた。応募作品から代替案を選び、現行マークとどちらが適切かを改めて意見募集する。同マークは当初からデザインなどに不満が強く、表示義務に罰則を付けた法改正の撤回を余儀なくされた経緯があることから、丁寧な意見集約が欠かせないと判断した。警察庁のアンケート調査では、もみじマークの印象を「もみじではなく枯れ葉」と考える人が42.1%と最多だったことも判明。50~74歳は「気に入っていない」との回答が過半数を占めている。
2009. 8. 05
昨日は「緑黄色野菜の大腸がん発生の抑制効果」に関するニュースを掲載しましたが、「緑黄色野菜とは何?」という質問が多くございましたので、本日は「緑黄色野菜」について簡単に説明します。緑黄色野菜とは、100g 中に 600マイクログラム以上のβ-カロテンを含む野菜のことで、決して野菜の色による分類ではありません。カロテンが600マイクログラム以下でも1回に食べる量や使用回数の多い野菜(トマト、さやいんげん、ピーマン等)も緑黄色野菜に含まれます。β-カロテンは、ビタミンAの作用をするという働きのほかに、有害な活性酸素から体を守る抗酸化作用や、免疫を増強する働きがあることがわかってきています。緑黄色野菜は現在56種あり、「しそ・モロヘイヤ・パセリ・にんじん・唐辛子・ほうれん草・小松菜・かぼちゃ」などがこれに含まれます。緑黄色野菜と淡色野菜のもっとも単純な見分け方は「中まで色がついているかどうか」です。緑黄色野菜は淡色野菜よりもカロテン、ビタミン、鉄などのミネラル類を多量に含んでいることが多いため注目されており、一日120g以上摂取するのが理想的と言われています。
2009. 8. 04
「緑黄色野菜の大腸がん発生の抑制効果」に関するニュースです。 埼玉県立がんセンター・臨床腫瘍研究所(川尻要専門員)らのグループは、緑黄色野菜に多く含まれるインドール化合物が大腸がんの発生を抑制する仕組みを解明、このたび米科学アカデミー紀要電子版に発表した。グループによると、緑黄色野菜が大腸がんの予防に効果があることは以前から知られていたが、どのような仕組みで効果が生じるのかは分かっていなかった。今回の研究で、インドールがAhRというタンパク質を活性化させ、がんを引き起こす物質β-カテニンを分解するメカニズムが初めて明らかになった。大腸がんの予防法の開発への応用が期待されます。インドール化合物は、ブロッコリーやキャベツ、カリフラワーなどアブラナ科の野菜に多く含まれています。
2009. 8. 03
太陽電池パネル付きの携帯電話用充電器を紹介します。パソコン周辺機器メーカーのグリーンハウス(東京・渋谷)は、太陽電池パネル付きの携帯電話用充電器「ケータイ用ソーラーチャージャー」を8月上旬に発売すると発表した。太陽電池パネルで発電した電気を蓄電しておき、携帯に供給する仕組み。携帯につなぐと、30~40分程度でほぼフル充電の状態にできるという。太陽光だけで蓄電を完了するには約35~40時間かかるため、携帯電話用のAC充電器からも蓄電できるようにした。約300回繰り返して使える。大きさは縦横4センチメートル強で、厚さ2センチ弱。色は黒、白、紫、ピンクの4種類をそろえた。NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、KDDIの携帯電話で使える。オープン価格だが、店頭では1980円前後と想定しているとのことです。
2009. 8. 01
「赤ん坊がうるさのは親の責任ではないのかもしれない」という興味深い研究を紹介します。カナダ・ハミルトン大学の研究者らは、DRD4遺伝子と脳の前頭皮質の活性との間に相互作用があるかどうかを調査。9ヶ月児の脳活性を調べ、4歳になったとき母親からの子どもの振る舞いアンケートやDNAサンプル摘出を終了した。それらのデータを分析したところ、右側の前頭皮質活性が高く、DRD4遺伝子の長いバージョンをもつ乳児は、そうでない乳児と比べて、48ヶ月時点でより簡単になだめられる傾向にあることが分かった。このことから、おとなしい赤ん坊になるか、うるさい赤ん坊になるか?このことに関しては、特定の遺伝子の組み合わせと特定の脳活性パターンが乳児の気質を決定する可能性があるので、母親の育児スキルは無関係かもしれません。
2009. 7. 31
広島平和記念都市建設法制定60周年に関する話題です。郵便局会社中国支社(広島市中区)は8月3日、広島平和記念都市建設法制定60周年を記念したフレーム切手を発売する。平和記念公園となった旧中島地区の1930年代の様子や、50年代の平和大通り、現在の原爆ドームなどの写真を採用した。80円切手10枚セットのB5判。1200円で3千部を販売する。広島市、府中町、海田町の簡易郵便局を除く郵便局と広島空港郵便局(三原市)の計173局で扱う。
2009. 7. 30
積水ハウスと千葉工業大学は共同で、高齢者向けのロボット開発に乗り出す。高齢者とコミュニケーションを取りながら、健康管理などの手助けをできるようにする。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が2010年度までに1億3000万円を支援する。 開発するロボットは日常会話のように高齢者と対話し、体調などの情報を収集する。一人暮らしでも健康を管理しながら自立して生活できるようにする。複雑な操作をせずに移動や簡単な作業をできる技術も搭載する予定。NEDOの支援期間が終了後、3年後をメドに事業化を狙うとのことです。
2009. 7. 29
国民健康保険中央会は、メタボリック症候群対策として2008年4月から始まった特定健診(メタボ健診)の受診率が、市区町村が運営する国民健康保険(国保)の全国平均で28.3%だったと発表した。国保には自営業者やその家族ら約3600万人が加入しており、メタボ健診の対象はそのうち40~74歳の約2400万人。国は12年度までの国保の目標として受診率65%を掲げているが、初年度は平均で半分にも達しなかった。都道府県別に見ると、最も高いのは宮城の43.7%で唯一4割を超えた。次いで富山39.6%、東京38.8%となっている。一方低いのは、なんと広島県で16.1%、次いで和歌山16.3%、北海道19.6%となった。まだ健診を受けておられない方は、ぜひ受診をお願いします。
2009. 7. 28
いまだ梅雨明けせず曇りや雨の日が続いていますが、気象庁が発表した8~10月の3カ月予報によると、エルニーニョ現象の影響などで太平洋高気圧の張り出しが弱まり、北日本(北海道、東北)と西日本を中心に冷夏となる見通し。「稲作に影響が出る可能性がある」(気候情報課)という。予報によると、8月の気温は沖縄・奄美で平年より高くなる。北日本と西日本は平年より低く、東日本は平年並みか平年より低いとした。台風の発生は少なくなる可能性があるという。
2009. 7. 27
2008年に新たに結核を発症した患者は、前年から551人減少し2万4760人、人口10万人当たりの患者数を示す罹患率も0.4減少し19.4と、ともに9年連続で減少したことが厚生労働省 のまとめで分かった。70歳以上の患者が1万2109人(48.9%)と半数近くを占め、割合は増加傾向。特に80歳以上では前年より100人以上多かった。20代の約4人に1人は外国籍の患者で、この割合も増加傾向が続いている。罹患率は都市部で高く都道府県別では大阪(32.8)、東京(25.1)の順。政令市も含めると大阪市(50.6)が最高で、最も低い長野県(10.2)の約5倍だった。結核症(肺結核)の主な症状は2-3週間以上続く咳、痰、熱、胸痛、体重減少、倦怠感などです。気になる症状があれば病院受診をお願いします。
2009. 7. 25
失明につながることもある「緑内障」の発症にかかわる6種類の遺伝子変異を、京都府立医大のチームが突き止め、米科学アカデミー紀要電子版に発表した。6種類すべての遺伝子変異を持つ人は、正常な人に比べて緑内障に4倍なりやすいことを確認。DNAチップなどを使った新たな診断法に応用できると期待される。田代啓教授(ゲノム医科学)は「緑内障は早期発見すれば失明を防ぐことができる病気。発症後でしか分からない従来の眼底検査に代わる新たな診断が将来可能になるかもしれない。」と話している。緑内障は目の中を流れる水分が排出されにくくなって視神経が障害を起こし視野が欠けてくる病気で、日本人の後天的な失明原因の25%を占めており、早期発見、早期治療が大切です。
2009. 7. 24
厚生労働省は22日、感染症法施行規則を改正し、5月の国内発生以来続けてきた新型インフルエンザ患者の全数把握を中止することを決めた。大流行の恐れがある秋以降、新型か従来の季節性インフルエンザか確定する遺伝子検査の作業が追い付かなくなることが予想されるほか、どちらも治療法に大差がなく、確定診断そのものの必要性も低いため。24日からは、学校などで集団感染が起きた場合の一部についてのみ報告を求める。一方、ウイルスの毒性変化を監視するため、国内約500カ所の定点医療機関に限り、症状のある全患者の検体を採取し、集団感染でなくても遺伝子検査に回す。22日午前11時現在、都道府県などから報告があった国内の新型インフルエンザ患者は4433人で、秋以降に大流行した場合、数千万人の感染の恐れがあるとされている。
2009. 7. 23
昨日(22日)は皆既日食、部分日食が日本各地で観測され話題となりました。皆既日食といえば、太陽と地球の間に月が来て、ちょうど太陽を覆い隠す現象ですが、この日食が起きるには驚くべき自然界の偶然が作用しています。まず、太陽と月の実際の大きさを比較してみましょう。太陽は地球の約100倍、月は地球の約4分の1ですから、太陽は月の約400倍の大きさです。次に地球からの距離を考えてみると、太陽は地球から約1億5000万キロメートル、月は約38万キロメートルですから太陽は月の約400倍遠いわけです。このため、約400倍大きい太陽と月の地球上からの見かけの大きさはほとんど等しくなり、月が太陽を覆い隠すことができるのです。日本の陸地から皆既日食が観測できたのは、1963年7月21日以来46年ぶりで、次回は2035年9月2日に北陸や北関東で見られます。
2009. 7. 22
柑橘系果物由来のフラボノイド(ナリンゲニン)は、体重増加や他のメタボリックシンドローム徴候を防ぐ可能性があることを、西オンタリオ大学ロバーツ医学研究所のチームが示唆した。マウスを、高脂肪の西洋食を食べさせる群と、同様の食事をしてかつナリンゲニンを用いた治療を行う群に分けて観察を行った。その結果、ナリンゲニンはトリグリセリドとコレステロールの上昇を補正し、インスリン抵抗性の発症を防いで、完全に糖代謝を正常化した。また食事の影響で増したマウスの肥満はナリンゲニンによって予防されたとのこと。更なる研究に期待しましょう。
2009. 7. 21
08年の日本人の平均寿命は男性が79.29歳、女性は86.05歳で、前年をそれぞれ0.10歳、0.06歳上回り、3年連続で過去最高を更新した。厚生労働省によると、女性は24年続けて世界で最も長寿で、男性は4位だった。がん、心疾患、脳血管疾患の3大疾患による死亡率が下がった影響が、最も大きかった。 厚労省が把握している海外の最新データと比較すると、男性の平均寿命が最も長いのはアイスランドで79.6歳、スイスと香港が79.4歳で続いた。女性は日本に次ぐ香港が85.5歳、フランスが84.3歳だった。 日本人が3大疾患により死亡する割合は、男性が約55%、女性が約52%。もし、3大疾患による死亡がなくなったとすると、平均寿命は男性が87.39歳、女性は93.05歳まで延びるとのデータもあり、これら疾患の予防や早期発見が大切です。
2009. 7. 18
ちょっと意外な商品がけっこう売れています。それが、日本気象協会が発売した「携帯型熱中症計」。発売された6月26日には、同協会のネットショップ「てるてる君☆Web Shop」にアクセスが集中してサーバもダウン、入荷分があっさりと完売した。現在、オノデンオンラインショップでようやく販売を再開したところだ。 「携帯熱中症計」とは、気温と湿度から独自の計算手法によって算出した熱中症指標値(WBGT近似値)に基づいて、熱中症の危険度ランクを5段階で知らせる機器。電源をオンにすると、気温と湿度を計測して液晶画面に表示、LEDランプの点灯で「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」のいずれかを知らせ、危険性が高い「厳重警戒」「危険」ではブザーが鳴るという仕組みだ。本品は従来品に比べ、掌サイズときわめてコンパクト。ストラップ付きで気軽に持ち運べるのが最大の特長である。価格が1050円とリーズナブルなあたりも人気の要因だろう。熱中症対策のひとつとして紹介させていただきました。
2009. 7. 17
化粧品会社ドクターシーラボは、老廃物や菌などを取り除き、加齢臭や足のにおいを抑える、渋柿やハーブに含まれる成分を使ったせっけん「シーラボ ハーバルDソープ」を8月1日に発売する。古来から消臭成分として重用されてきた「柿渋エキス(カキタンニン)」を配合、これに含まれるポリフェノールがニオイ成分を捕捉消臭し、さらに、「チョウジエキス」「ウコンエキス」が菌の繁殖を防ぎ、ニオイの発生しにくい環境を整え、「ケイヒエキス」が肌をひきしめるとのこと。においの気になる季節であり、紹介させていただきました。
2009. 7. 16
ウェザーニューズは、今年の花粉シーズンは、昨年に比べ花粉飛散が81%の大幅増だったと発表した。雄花の生産量が少ない翌年は花粉の飛散が多くなる「表年」にあたり、とくに中部地方の飛散数の多さが特徴的だったという。 一般の参加者らと共に展開した「花粉プロジェクト」の調査結果からの分析で、県別で総飛散数が最も多かったのは岐阜県。以下、奈良県、長野県、静岡県、愛知県の順。逆に最も少なかったのは佐賀県だった。 2010年の花粉飛散予想は、今年の夏は晴れる日が多く暑くなると予想されるほか、雄花の生産量が多い翌年は少なめな「裏年」になることなどから、関東、東北、北海道は前年比「同じ~やや多め」、九州、四国、中国、近畿、東海、北陸は「同じ~やや少なめ」と予想している。今後も、新しい情報があればお伝えします。
2009. 7. 15
60歳以上の高齢者の3~4割は新型の豚インフルエンザウイルスに対する抗体を持っていて何らかの免疫があるという調査が日米で報告されていたが(当ページ7.09参照)、60~80歳代には抗体がなく、安心できないことがわかった。90歳代の人には抗体があった。東京大医科学研究所、河岡義裕教授のチームは、1999年と今年4月に採取した250人分の血清を調べた。いずれの年でも、1918~19年に世界的大流行したスペイン風邪以前に生まれた90歳代以上の人の血清では、新型インフルへの抗体を持っている血清が多かった。一方、1920年以降に生まれたそれ以下の年代の血清では、抗体がある人はほとんどいなかった。 新型インフルエンザについては、少しずつ新しいことがわかってきている状況です。今後も情報を紹介していきたいと思います。
2009. 7. 14
イェール大学の研究者らは、テレビでの食品コマーシャルの影響を検査するために一連の実験を実施した。ある検査で、食品コマーシャルが含まれた漫画番組を30分間見た7~11歳の小児は、食品コマーシャルが含まれていない漫画を同様に見た小児に比べて、テレビを見ている間に45%多くスナック食品を食べたことが分かった。さらなる実験で、不健康な食品のTV広告を見た成人は、良い栄養や健康食についてのメッセージを宣伝した広告を見た成人よりも、たくさん食べたことが報告された。コマーシャルの影響はやはり大きいですね。
2009. 7. 13
血液検査でうつ病かどうかを診断する方法を、厚生労働省の研究班(主任研究者・大森哲郎徳島大教授)が開発した。研究班は、うつ病患者と健常者で白血球の特定の遺伝子の反応が微妙に異なることを突き止めた。医師の面接によってうつ病と診断された17~76歳の患者46人と健常者122人を分析した結果、うつ病患者の83%(38人)、健常者の92%(112人)で、特定の遺伝子が突き止めた通りに反応し、正しく判定できた。研究班は今年から2年間、対象を増やして診断し、実用化できる精度か確かめる。問診以外に、数値化できる簡便な診断法が使えることはうつ病の診断に有用であり、早期の実用化に期待します。
2009. 7. 11
日本薬剤師会(児玉孝会長)はこのほど、2008年度の「薬と健康の週間(毎年10月17-23日)」にちなみ都道府県薬剤師会などが行った市民アンケートの結果をまとめ、ホームページで発表した。それによると、「お薬手帳」を持っている人は全体の6割近く(58.7%)で、持っていて役立った経験については、「記録として」が20.9%で最も多く、「同じ薬による副作用の防止」12.9%、以下「薬の重複や相互作用のチェック」、「医師や薬剤師などとのコミュニケーション」と続いた。当院でも、「お薬手帳」を交付しております。記録としてのみならず、皆さまに薬について正しく理解していただけるよう努めていきたいと思います。
2009. 7. 10
40~74歳を対象にした特定健診、いわゆる「メタボ健診」の2008年度の受診率は、大企業のサラリーマンらが加入する健康保険組合の平均で59.8%(速報値)だったことが、健康保険組合連合会の集計で分かった。特定健診は昨年4月に導入され、健保組合には扶養家族も含め約3000万人が加入。国は12年度までの目標として、加入者の受診率80%を掲げているが、初年度はこれを大幅に下回った。健保加入者本人の受診率が75.0%なのに対し、扶養家族は32.5%にとどまっています。家族の方もぜひ検診を受けてください。
2009. 7. 09
国内の高齢者の一部が、新型インフルエンザウイルスに対して一定の免疫を持っている可能性があることが、国立感染症研究所などが実施した調査で分かった。調査によると、若者(平均年齢27.8歳)と高齢者(同83.4歳)の2グループ各30人を対象に、新型インフルエンザウイルスに反応する抗体が血清中にあるかどうかを調べた。すると高齢者グループの40%で抗体の保有が確認され、新型ウイルスに対してある程度の免疫を持っている可能性が示唆されたが、若者では3.3%だった。ただ調査対象が少ない上、この抗体によって新型ウイルスの感染を実際に防ぐことができるかどうかは不明。感染研は今後、さまざまな年齢層でどのぐらい新型への抗体を保有しているか、1千人規模の調査をするとのことであり、結果が注目されます。
2009. 7. 08
若い喫煙者は同年代の非喫煙者よりも生活習慣病を防ぐとされるホルモン「アディポネクチン」の血中濃度が低く、糖尿病の指標となるグリコヘモグロビン(HbA1c)の血中濃度は高いという研究結果を、青森県立保健大の渡部一郎教授(リハビリテーション医学)らがまとめた。同大の男子学生45人(平均22.3歳)を対象にアディポネクチンとHbA1cの血中濃度と喫煙習慣の有無を調査したところ、アディポネクチンの血中濃度は非喫煙者は1ミリリットル当たり平均5.0マイクログラムだったのに対し、喫煙者は平均3.5マイクログラムであり、HbA1cは非喫煙者が4.7%で、喫煙者は5.0%であった。若いうちから喫煙すると生活習慣病や糖尿病になるリスクが大きくなる可能性があり、注意が必要です。
2009. 7. 07
幼稚園や保育所に通わせている保護者の15%が、ビタミンなど特定の成分を濃縮した健康食品のサプリメントを、子どもに与えていることが、国立健康・栄養研究所(東京)が初めて実施した調査で分かった。保護者の6割は「栄養補給」が利用目的と回答、「病気予防」、「体質改善」がそれに続いており、食生活に何らかの改善が必要と感じて、サプリに頼る実態が浮かんだ。研究所は、幼児への有効性や安全性など検証したデータは乏しいとし「身体に必要な成分でも安易に与え続けると過剰摂取につながり、幼児に有害な作用が出る恐れがある」としているため、過剰摂取には十分注意してください。
2009. 7. 06
厚生労働省は今年度から始めた子宮頸(けい)がんと乳がんの無料検診を、来年度以降も継続する方針を固めた。この制度は、対象年齢に限定があり(「子宮がん」が20、25、30、35、40歳。「乳がん」が40、45、50、55、60歳。)、全女性が無料になるわけではない。対象の女性には各自治体からクーポン券と検診手帳が配られる。子宮頸がんと乳がんは早期発見すれば完治する可能性が高く、政府は2年に1度の定期的な検診を勧めているが、現在の受診率は20%前後に低迷しています。この制度が受診率アップにつながればと思います。
2009. 7. 04
厚生労働省研究班は、適量でも1人で酒を飲む男性は、友人や家族との社会的交流の多い男性に比べて、飲酒による脳卒中のリスクが高くなるとみられるとの調査結果を発表した。1日ビール大瓶2本未満程度の飲酒の場合、社会的支えの多い人は脳卒中の発症危険度が飲まない人の0.7から0.8倍と低くなったのに対し、社会的支えのない人は発症危険度が飲まない人の1.2から1.8倍になった。仲間と楽しく飲んだほうがストレスを発散でき、脳卒中の予防につながる可能性があるという。友達や家族は大切ですね。
2009. 7. 03
昨年度の食中毒の発生件数は1369件で、2万4303人の患者が出ていたことが、厚生労働省の調べで分かった。都道府県別の発生件数では、なんと広島県がもっとも多く273件、東京106件、大阪の順であった。患者数は多い順に大阪2071人、広島1602人、東京で広島県は2番目であった。原因別発生件数では「魚介類」が最多、次に定食や弁当などの「複合調理食品」であった。月別発生件数は、多い順に10月、8月、9月であり、これからの時期、食中毒には十分ご注意ください。
2009. 7. 02
人間の皮膚には約1000種類の細菌がすんでおり、従来考えられていたよりはるかに多いことが米国立ヒトゲノム研究所などの分析でわかった。最も多種の細菌がいたのは前腕で、最少だったのは耳のうしろだった。皮膚の細菌には、古い細胞や皮脂を食べたり、他の病原菌を撃退したりする善玉菌も含まれている。皮膚にいるのは、ほとんどブドウ球菌の仲間と考えられていたが、興味深い報告であり紹介しました。
2009. 7. 01
禁煙補助薬「ニコレット」シリーズの新製品となるフルーツ味のガム、「ニコレットフルーティミント」が発売されました。禁煙をお考えのあなたの少しでも助けになればと思い紹介しました。
なかた内科循環器クリニック
〒734-0036 広島市南区旭1丁目5-31(大河小うら)
電話番号:082-298-7799
アクセスマップはこちら→「地図」
クリニック情報
◆ 「骨密度検査」のご案内
・ 以前からご要望の多かった「骨密度検査」が可能となりました。骨粗しょう症の早期発見・予防に骨密度検査を受けませんか?広島市骨粗しょう症検診にも対応しています。
・
DEXA法による測定を行っているため、正確、簡便で痛みもなく、検査時間は1分程度です。
◆ 「ウォーターマッサージベッド」を導入しました
・
ウォーターマッサージベッドは、水の浮遊感により水圧を使って全身をマッサージする器械です。水圧刺激により、首・肩から腰、下肢にかけての筋肉・腱・靭帯の凝りをやさしくほぐし、血行の改善を促進します。
・
心地よい浮遊感と、指圧に近い感覚の水圧によるマッサージを体験してみて下さい。
◆ 「家庭用血圧計」の無料貸し出しのお知らせ
・ 健康診断や病院などで高血圧といわれたが、普段の血圧は分からないという方が多く受診されます。そのような方のために、10日間程度、 「家庭用血圧計」を無料で貸し出します。
受診された方は、是非ご利用下さい。
◆ 「栄養指導」始めました
・ 当院は、2010年8月より、 管理栄養士による、「栄養指導」を開始しました。
(管理栄養士:中田 早美)
・
生活習慣病をはじめとし、更年期障害、腎臓病、貧血などの各疾患には、食生活と密接な関係を持つものが多く、医療だけではなく栄養面からの治療も大切であり、食生活の改善が健康づくりにつながるため、栄養指導は重要です。
・
食事、栄養に関することは何でもお気軽にご相談ください。個別指導です。
◆ 「禁煙外来」について
・ 10月にはいりタバコが値上がりしました。 これを機会に禁煙してみませんか?
・ タバコをやめられないのはニコチンのもつ強い依存性が原因で、「ニコチン依存症」といわれます。これは病気であり、薬を使った治療が必要です。
・ 禁煙治療を希望される方は、お気軽にご相談下さい。
◆ スパイロメトリー検査(肺機能検査) について
・ 当院では、スパイロメトリー検査(肺機能検査)が可能となりました。この検査は、肺がどのくらいの量の空気を吸い込めるか(肺活量)、どのくらいの速さで吐き出すことができるか(一秒量)を測定し、肺年齢や肺の病気を評価する検査です。お気軽にご相談下さい。
◆ 血管年齢検査(血圧脈波検査)について
・
当院では、血管年齢検査(血圧脈波検査)が可能となりました。この検査は、 「血圧」 、 「血管の硬さ」、「血管の詰まり」を測定し、血管の状態や動脈硬化の程度を見ることができます。心臓や動脈硬化に関する健康診断として、血管年齢の把握は大切です。お気軽にご相談下さい。